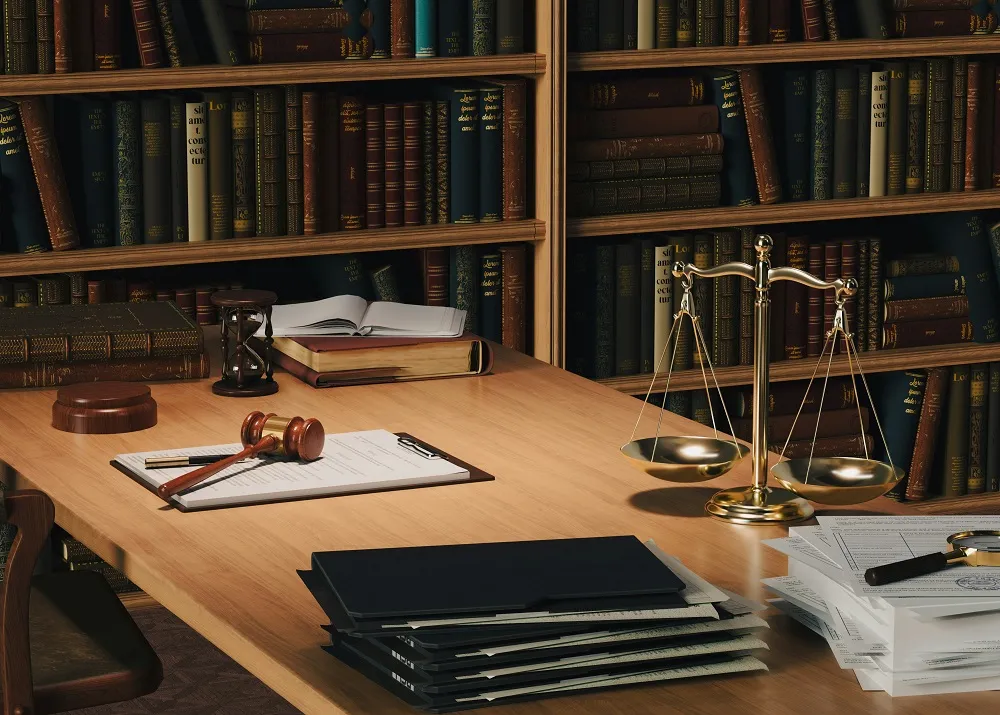『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.1 解決手段の検討』はこちらから
『紛争事例で学ぶ国際紛争 vol.2 管轄の検討』はこちらから
1 はじめに
国際取引においては、それぞれの当事者が所在する国で法律が異なります。これは、どちらの国の法律が適用されるのかによって、契約の成立条件や契約条項の効力が大きく異なる可能性があることを意味します。そのため、国際取引においては、準拠法、つまり、契約の成立条件や契約条項の効力を判断する際に適用される法律が、一体どこの国の法律となるかを検討しておくことが大切です。
そこで、今回は、国際紛争における準拠法について概観します。
2 裁判所が準拠法について判断するプロセス
(1) はじめに
一般的に、取引が何のトラブルもなく進んでいる間は、準拠法が問題となることはありません。どの国の法律が準拠法となるかが問題となるのは、取引当事者間に紛争が生じた場合です。
そこで、第一に、紛争が発生し、裁判にまで発展した場合において、裁判所が準拠法についてどのように判断するかを知っておくことが必要となります。
(2) 裁判所が準拠法について判断するプロセス
どの国の法律が準拠法となるかは、訴訟提起された裁判所が、裁判所がある国の法律に従って判断します。どの国も「準拠法についてどのように決定するか」を定めた法律を持っているので、訴訟提起された裁判所が、自国のこの法律に従って準拠法を判断するのです。
つまり、裁判所が準拠法について判断するプロセスは、以下のとおりとなります。
① 当事者が、ある国の裁判所へ訴訟提起する。
② 裁判所が、裁判管轄権の有無を判断する(その裁判所で訴訟を進めることができるかどうかを判断する)。
③ 裁判管轄権がある場合、裁判所は、その国の「準拠法についてどのように決定するか」を定めた法律に従い、どの国の法律が準拠法となるかを判断する。
④ 準拠法が決まった後は、裁判所は、その準拠法に従い、法律上の争点について判断していく。
例えば、A国裁判所に対して国際取引に関する訴訟が提起された場合、A国裁判所は、A国の国際民事訴訟法に基づいて、A国裁判所に裁判管轄権があるか否かを判断します(管轄の問題。第2回の記事参照)。
そして、A国裁判所に国際裁判管轄権が認められる場合、A国は、A国の「準拠法についてどのように決定するか」を定めた法律に基づいて、その紛争で問題となっている契約上の争点についてA国法によって判断すべきなのか、B国の法律に従って判断すべきなのかを決定する(=準拠法について決定する)のです。
よりイメージしやすいよう、日本の裁判所が準拠法について判断する場合を解説します。
(3) 法の適用に関する通則法
日本には、「準拠法についてどのように決定するか」を定めた法律として、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)があります。日本の裁判所は、この通則法に従い、契約その他法律行為の成否や効力などの争点について、どの国の法律を準拠法とすべきかを判断するのです。
まず、通則法第7条は、
「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」
と規定しています。つまり、当事者間において、準拠法について合意している場合には、その合意した準拠法に基づき、契約その他法律行為の成否や効力が判断されることになります。そのため、例えば、契約書の中に、
「本契約は、A国法を準拠法とし、A国法に従って解釈されるものする。」
という条項が含まれている場合には、A国法が準拠法となります。
次に、当事者が準拠法について合意していなかった場合には、通則法第8条1項に従って準拠法が判断されます。
通則法第8条1項は、
「前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。」
と規定しています。つまり、準拠法の合意がない場合には、法律行為に最も密接な関係がある地(最密接関係地)という客観的観点から、準拠法が決定されるのです。
この点、最密接関係地は、契約締結地、契約交渉地、当事者の国籍や所在地、法律行為の行為地や義務履行地、目的物の所在地などの様々な事情を総合的に考慮して判断されます。そのため、どの国の法律が最密接関係地の法律となるか(つまり、準拠法となるか)を具体的に予測したり決定したりすることには困難が伴います。そこで、通則法は、第8条2項以下に推定規定を置き、その予測や判断を容易にしています。
例えば、通則法第8条2項は、
「前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。」
と規定しています。この条項は、特徴的な給付を当事者の一方だけが行うようなケースにおいて、どの国の法律が最密接関係地の法律であるかを推定する規定です。ここで「特徴的な給付」とは、ある契約を他の種類の契約から区別する基準となる給付をいいます。例えば、動産の売買契約では、売主による動産の引渡しが特徴的な給付に該当します。他方、買主の金銭の支払は他の種類の契約にも共通する給付であるため、特徴的な給付に該当しません。つまり、動産の売買契約の場合は、特徴的な給付である動産の引渡しを行う売主の常居所地の法律が、最密接関係地の法律として推定されるのです。
したがって、動産の売主が日本企業であった場合は、日本法が最密接関係地の法として推定され、この推定が覆されない限り、売買契約の準拠法は日本法となります。
その他、不動産を目的物とする法律行為については、通則法第8条3項により、不動産の所在地の法律が最密接関係地の法律として推定されます。
なお、消費者契約に関しては通則法第11条、労働契約に関しては通則法第12条にて、準拠法の決定に関する特例が定められていますので、注意を要します。
(4) タイの場合
なお、タイでは、「法の抵触に関する法律(Act on Conflict of Laws)」(以下「タイ抵触法」といいます)が、準拠法の決定方法について定めています。
そして、契約の重要な要素や効力については、当事者の意思によって準拠法を決定すべきこととされています(タイ抵触法第13条1項)。つまり、日本と同様、まず当事者の意思が尊重されるのです。
ただし、当事者の意思が明らかでない場合には、当事者の国籍が同一のときは当事者の国籍地の法を適用し、国籍が異なるときは契約を締結した地の法を適用することとされており(タイ抵触法第13条1項)、日本のように最密接関係地により決定するわけではないことに注意が必要です。
(5) 小括
以上のとおり、準拠法は、裁判が行われる国における「準拠法についてどのように決定するか」を定めた法律に従って判断されることとなります。
そのため、どこで紛争を解決するかという管轄の問題とも密接に関連します。
したがって、準拠法について合意することを検討する場合には、管轄の問題も合わせて検討することが大切となります。
3 事例を通じた検討
事例
日本の工業用部品メーカーであるA社は、タイのB社との間で、日本の工場で製造した工業用部品1000個を5000万円で売却する契約を締結し、製造した工業用部品1000個を全て輸出した。ところが、B社は支払期日経過後も5000万円を支払わない。
(1) 準拠法が定まっている場合
ア 管轄裁判所が日本の裁判所である場合
A社が日本の裁判所に工業用部品代金5000万円の支払いを求めて訴訟を提起した場合、通則法に基づき準拠法が決定されます。
そして、A社とB社との間で「日本法を準拠法とする」(又は「タイ法を準拠法とする」)という合意があれば、通則法第7条に基づき、その合意に従い、日本法(又はタイ法)が準拠法となります。
イ 管轄裁判所がタイの裁判所である場合
A社がタイの裁判所に工業用部品代金5000万円の支払いを求めて訴訟を提起した場合、タイ抵触法に基づき準拠法が決定されます。
そして、A社とB社との間で「日本法を準拠法とする」(又は「タイ法を準拠法とする」)という合意があれば、タイ抵触法第13条1項に基づき、その合意に従い、日本法(又はタイ法)が準拠法となります。
(2) 準拠法が定まっていない場合
ア 管轄裁判所が日本の裁判所である場合
A社が日本の裁判所に工業用部品代金5000万円の支払いを求めて訴訟を提起した場合、A社とB社との間には、準拠法に関する合意がありませんので、合意に従った準拠法の決定はできません。
そこで、通則法第8条1項に基づき、最密接関係地の法律が準拠法となります。
A社とB社の契約は売買契約であり、売主であるA社の工業用部品の引渡しという給付が特徴的給付といえます。そのため、A社の常居所地の法律が最密接関係地の法律であると推定されます(通則法第8条2項)。
したがって、通常、日本法が準拠法となります。
イ 管轄裁判所がタイの裁判所である場合
A社がタイの裁判所に工業用部品代金5000万円の支払いを求めて訴訟を提起した場合、A社とB社との間には準拠法に関する合意がありませんので(かつ、当事者の意思を推測することも困難と思われるので)、当事者の意思に従った準拠法の決定はできません。
そこで、当事者の国籍が同一のときは当事者の国籍地の法を適用し、国籍が異なるときは契約を締結した地の法を適用するという規定に従って判断されることとなります(タイ抵触法第13条1項)。この点、A社は日本企業、B社はタイ企業ですので、国籍が同一とはいえません。そこで、契約締結地の法律が準拠法となります。つまり、日本で契約が締結されたのであれば日本法が準拠法となり、タイで契約が締結されたのであればタイ法が準拠法となるのです。
もっとも、A社とB社が契約書類を郵送するなどして遠隔地にいながらにして契約を締結したという場合もありえます。この場合は、「承諾の通知が申込者に到達した地を契約が成立した地とみなし、その地が不明の場合は契約の行為地の法律を適用する。」という規定に従い(タイ抵触法第13条2項)、準拠法を決定することとなります。
4 準拠法に関する合意
これまでに述べたとおり、日本でもタイでも、契約上の問題に関しては当事者間の合意ないし意思に従って準拠法を決定すべきというルールをこととされています。また、日本やタイと同様に、多くの国が当事者の意思を尊重して準拠法を決定することとしています。
そのため、国際取引契約においては、準拠法について以下のような条項を設けておくのが一般的です。
「本契約は、A国法を準拠法とし、A国法に従って解釈されるものする。」
もっとも、一般的に、当事者双方が自国の法律を準拠法とするよう望み、交渉がなかなか進まないという場面も少なくありません。
そのようなときには、例えば、次の方法がありえます。
ー 準拠法のみに着目せず、他の点で相手方に譲る代わりに準拠法をこちらの希望に合わせてもらう。または、その逆で、他の点で譲歩してもらう代わりに準拠法を相手の希望に合わせる。
例えば、「タイの裁判所を管轄とする代わりに、準拠法は日本としてもらう。」などです。
ー 第三国の法律を準拠法とする。
必ずしも当事者いずれかの国の法律を準拠法としなければならないわけではありません。そのため、間をとって第三国の法律を準拠法とするという方法もありえます。もっとも、この方法を用いる場合には、当然ながら、その第三国の法律の内容についてあらかじめ調査をしておくことが重要となります。
ー あえて準拠法を定めないでおく。
準拠法の合意は必須ではないため、あえて合意しないでおくことも一つの方法です。ただし、どこの裁判所で、どのようにして、どの国の法律が準拠法とされうるか、という点や、準拠法とされうる法律の内容について、あらかじめ把握しておくことが重要となります。
これらに加えて、そもそも取引相手の国の法律を準拠法としても全く問題がない状況にしておくよう、あらかじめ取引相手の国の法律に関して信頼できる専門家を見つけておき、取引相手の国の法律を準拠法とした場合を前提として契約書のドラフトを事前チェックしてもらうというのも一つの方法です。
5 補足:ウィーン売買条約について
補足として、一部の類型の取引については、各国の法律ではなく、特定の条約が適用される場合があります。
その代表的なものが、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods。以下「ウィーン売買条約」といいます。)です。
これは、国際的な物品の売買取引に適用される条約であり、売主や買主の権利義務等について定めたものです。現在、日本、アメリカ、中国、シンガポールなど、90か国以上が締約しています。
当事者の所在する国がいずれも締約国である場合は自動的にウィーン売買条約が適用されることとされています(ウィーン売買条約第1条1項)。また、一方のみが締約国である場合も、締約国の法律が準拠法とされる場合にも適用されます(ウィーン売買条約第1条2項)。 そのため、取引相手の国が締約国である場合のみならず、非締約国である場合でも、ウィーン売買条約が適用される可能性があるのです。
もっとも、ウィーン売買条約は、当事者が合意することにより適用を排除できます。そのため、ウィーン売買条約の適用を排除したい場合には、契約書などで明示的に、適用を排除する旨を定めておくことが重要です。
6 まとめ
本コラムでは、事例を通して、国際紛争における準拠法について検討しました。準拠法の検討は紛争解決手段を検討する上でとても重要になってきますので、本記事が準拠法を決定する際の手助けになれば幸いです。