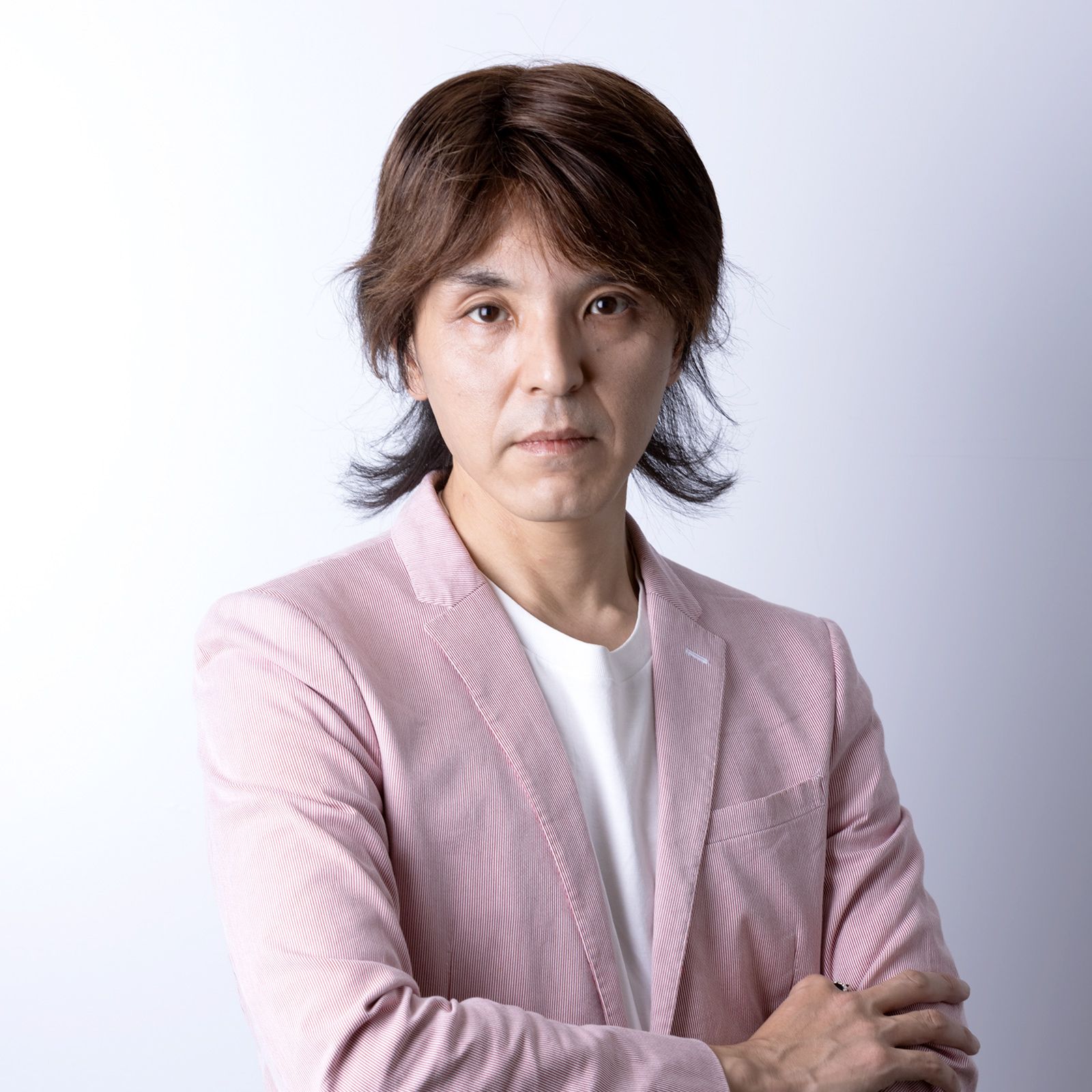執筆:弁護士 早崎 智久 (メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
連載:薬機法とは ~薬機法の基本~
『第1回 薬機法の全体像』はこちらから
『第2回 「医薬品等」とは』はこちらから
『第3回 医薬品の販売と薬局 ① -医薬品の種類-』はこちらから
『第4回 医薬品の販売と薬局② -医薬品の販売と薬局-』はこちらから
『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから
『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから
『第7回 製造販売後の医薬品 -医薬品の安全管理と有効性の再確認-』はこちらから
『第8回 医薬品情報の消費者への表示-医薬品の表示、添付文書、広告-』はこちらから
1.はじめに
GVA法律事務所では、メディカル、美容、ヘルスケア領域に関して専門チームを設け、各分野について多様なサポートをさせていただいております。
薬機法の基本に関する連載の第1回目では、薬機法の全体像を簡単にご説明しましたが、第2回目となる今回は、「医薬品等」とは何か、について解説いたします。
2.「医薬品等」とは
薬機法や、関連規則、適正広告基準や多くの関連ガイドラインには「医薬品等」というワードが頻繁に出てきます。
そして、「医薬品等」に該当しなければ、基本的に薬機法の適用はないことになります。
そのため、対象とする商品が「医薬品等」に該当するかどうかということが、まずポイントになります。
この「医薬品等」の定義(=内容)を定めているのが、薬機法の第1条になり、そこでは、
医薬品等=
「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)」とあります。
つまり、医薬品等というのは、
①医薬品、②医薬部外品、③化粧品、④医療機器、⑤再生医療等製品の5種類
であり、これに該当しないものは、薬機法の適用対象とはなりません。
そのため、重要なのは、
「販売や広告を考えている製品が、この5つのどれかに該当するのかどうか」
ということです。これが分かれば、薬機法の適用対象であることが分かりますし、さらに、それぞれにどのような規制があるのかも分かります。
しかし、これは簡単なようで、実際には悩む場面が非常に多いのが実情です。
例えば、かぜ薬や傷薬が医薬品で、マスカラや口紅が化粧品というのは、なんとなくではあっても誰でも分かります。しかし、歯ブラシはどうでしょうか。マスクはどうでしょうか。さらに、シャンプーはどうでしょうか?さらに、シャンプーにもいろいろなものがあります。「薬用シャンプー」という言葉を聞いた方は多いと思います。ビタミン剤は?足つぼのマッサージ機はどうでしょうか?
そして、これだけ悩ましいのに、仮に、医薬品等なのにそうじゃないと勘違いしてしまい、薬機法の規制を無視してしまうと、非常に厳しい罰を受けることもあります。
そのため、
対象商品が医薬品等なのかどうかを区別する方法
を正しく理解しておくことが重要になります。
この医薬品等については、前述のように薬機法の第2条の定義にそれぞれ記載されていますが、内容も複雑で一読して理解するのは難しいところです。
そこで、以下では、5つについて、順番にその内容を分かりやすくご説明します。
3.医薬品(薬機法第2条第1項)
医薬品について、薬機法では、次の3つのどれかに当てはまるものとされています。
⑴ 日本薬局方に収められているもの(第1号)
まず、「日本薬局方に収められている物」です。
この「日本薬局方」というのは、古風な名称ですが、厚生労働大臣が定める医薬品の規格基準書です。明治19年に定められた歴史のあるもので、幾多の改正を経て、現在は「第十八改正日本薬局方」が公示されています。繁用されている医薬品が収載されています。
全部で2800頁程あり、通読するようなものではありませんが、医薬品の長い歴史とその多様さを理解できるものとなっています。
⑵ 人・動物の疾病診断等に使用することが目的であるもの(第2号)
次は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。
こちらを、分かりやすくしますと、
① 使用目的
人か動物の病気の診断、治療、予防
② 形状
機械器具等ではないもの
となります。
②で「機械器具等ではない」ことが要件になっているのは、機械器具等の場合は医薬品ではなく医療機器になるためです。この要件は、医薬品と医療機器を区別するための要件といえます。
機械器具等については医療機器のところで詳しく説明しますが、ある商品が「機械器具等」に該当するかどうかは、感覚的にも理解しやすいと思います。
他方で、①については注意が必要です。
使用目的が、「人か動物の病気の治療」の場合、①に該当することになりますが、医薬品ではない(例えば化粧品)のに、医薬品であるかのように扱ったり、広告してしまった場合に、①の要件に該当してしまう(結果的に、「医薬品」として規制されてしまう)ことです。
例えば、肌にうるおいを与える化粧品を広告する際に、「この化粧品はお肌に関するあらゆるトラブルを治します」などと書いてしまう場合などが考えられます。この場合、「トラブル」という言葉には、一般的には肌の疾患を含むと読めますので、「治します」と書いてしまうと、本当は化粧品なのに、医薬品である「人の病気の治療」目的があることになってしまいます。この場合、この製品の広告は、医薬品の広告ということになってしまいますが、当然、この製品は医薬品としての承認を受けていないため、「未承認医薬品の広告」となり、違反となってしまうのです。
⑶ 人・動物の身体の構造などに影響を及ぼす目的があるもの(第3号)
最後は、「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」です。
これを分かりやすく言えば、
① 使用目的
人か動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと
② 形状
機械器具等ではないもの
③ 種類
医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品ではないもの
となります。
②については上記⑵と同じく医療機器との区別です。
重要なのは①ですが、これだけ見ても分かるものではなく、実際には、③の要件との関係で判断する必要があります。つまり、「人や動物の身体の構造又は機能に影響を与える目的を持ちつつ、化粧品、医薬部外品などの定義を超えるもの」=化粧品などよりも身体への影響が強いもの、と理解するのが分かりやすいと思います。
⑷ 医薬品のポイント
以上の⑴~⑶を見ても、その内容は複雑です。そのため、大まかには、
・機械器具等であれば医薬品ではない(医療機器に当たるかどうかが問題になる)
・日本薬局方に書いてあるものは全部医薬品
・病気の診断、治療、予防に関するものは基本的には医薬品
・化粧品、医薬部外品より影響が強ければ(これらの効能効果を超えれば)医薬品と理解しておけば、基本的には問題がないと思います。
また、薬機法の対象ではありませんが、医薬品との区別が必要になるのは、医薬部外品になるビタミン剤や食品です。特に、食品について、医薬品に該当するような広告などをしてしまうと、(未承認の)医薬品として扱われることになるため、注意が必要です。
4.医薬部外品(薬機法第2条第2項)
医薬部外品についても、非常に読みにくい条文となっていますが、これは、もともと医薬部外品として定められていたものに加え、法改正に伴う規制緩和により、新たに医薬部外品となったものが含まれているためです。
具体的には、医薬部外品を定義する薬機法の第2条第2項のうち、第1号と第2号がもともとのもの、第3号が新たに加わったもの、となります。
以下、詳しく解説します。
⑴ 従来から医薬部外品であったもの(第1号と第2号)
まず、もともとのものである第1号と第2号を見ると、以下のようになっています。
第2条第2項
柱書
次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なもの
第1号
次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛(第2条第2項第1号)
第2号
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの柱これを整理すると、以下のようになります。
① 使用目的が以下のどれか
・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛又は除毛
・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
② ①の目的があっても、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることや、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことも、併せて目的としているものは除く(これらは医薬品になります。)
③ 人体に対する作用が緩和であること(緩和でない場合は医薬品になります。)
④ 機械器具等ではないこと(機械器具等の場合は医療機器になります。)
つまり、特定の限定された目的をもった物で、医薬品や医療機器には当たらないものが医薬部外品、ということになります。
⑵ 指定医薬部外品(第3号)
第3号が、新たに医薬部外品として認められることになったものになります。いわゆる「指定医薬部外品」と呼ばれるものです。
第2条第2項
柱書
次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なもの
第3号
前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するものこれについても、上記のとおり、人体に作用が緩和であることなども条件になっていますが、これらの条件に適うものから厚生労働大臣が指定しますので、単に、「厚生労働大臣が指定する医薬部外品のこと」と理解すれば問題ありません。
現在、以下の27種類のものが指定されています。
胃の不快感を改善することが目的とされている物
いびき防止薬
衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。)
カルシウムを主たる有効成分とする保健薬(第十九号に掲げるものを除く。)
含嗽薬
健胃薬(①及び㉗に掲げるものを除く。)
口腔咽喉薬(⑳に掲げるものを除く。)
コンタクトレンズ装着薬
殺菌消毒薬(⑮に掲げるものを除く。)
しもやけ・あかぎれ用薬(㉔に掲げるものを除く。)
瀉下薬
消化薬(㉗に掲げるものを除く。)
滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物
生薬を主たる有効成分とする保健薬
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物
整腸薬(㉗に掲げるものを除く。)
染毛剤
ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物
のどの不快感を改善することが目的とされている物
パーマネント・ウェーブ用剤
鼻づまり改善薬(外用剤に限る。)
ビタミンを含有する保健薬(⑬及び⑲に掲げるものを除く。)
ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物
化粧品としての使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物
浴用剤
⑥、⑫又は⑯に掲げる物のうち、いずれか2つ以上に該当するもの
なお、指定は「通知」という形で行われますが、この通知の年度別に、新指定医薬部外品、新範囲医薬部外品、防除用医薬部外品などと区別されています。しかし、この区別にそれほど敏感になる必要はありません。
5.化粧品(薬機法第2条第3項)
⑴ 化粧品の定義
化粧品の定義自体はとてもシンプルです。
条文では、
第2条第3項
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。となっていますが、整理すると、
① 使用目的
・人の身体を清潔、美化、魅力を増し、容貌を変えるため
・皮膚か毛髪を健やかに保つため
② 使用方法
・身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用
③ 人体に対する作用が緩和(作用が緩和でないものは医薬品になります。)
④ ①の目的があっても、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることや、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことも、併せて目的としているものは除く(これらは医薬品になります。)。
⑤ 医薬部外品は除く
となります。
上記のうち、③と④は医薬品との区別で、⑤は医薬部外品との区別になります。
※なお、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、医薬品や医薬部外品とは異なり、「機械器具等ではないもの」という条件がありません。つまり、機械器具等であっても、化粧品になる場合があります(いわゆる「着る化粧品」など)。
⑵ 化粧品のポイント
以上から、化粧品のポイントは、①と②ということになりますので、抑えておくべきポイントを挙げれば、
・「人」に対して使うものだけ(動物に使うものは含みません。)
・人の「身体に対して」使うもの
・人の身体を「清潔にする」もの
人の身体を「美化し、魅力を増す」もの
人の「容貌を変える」もの
・身体に「塗擦、散布その他これらに類似する方法」で使うもの
となり、医薬品や医薬部外品と比べると内容が明確です。
しかし、これに含まれる範囲は非常に広く、さらに、医薬品との区別、雑貨(医薬品等にならないもの)との区別が不明確なケースも多いのが現状です。そのため、明確に「これは医薬品で、これは化粧品で、これは雑貨です」と言い切るのが難しいことも多いことになります。
そのため、化粧品の定義はシンプルだが、該当するかどうかの判断は悩ましい、ということになります。
雑貨等として扱ったが、実際には化粧品になるケースの場合は薬機法の適用があり、広告などで厳しい規制が発生しますので、注意が必要になります。
6.医療機器(薬機法第2条第4項)
⑴ 医療機器の定義
医療機器の定義はシンプルなものとなっています。
条文を見ると、
第2条第4項
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいうとありますので、整理すると、
① いずれかの使用目的
・人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること
・人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと
② 機械器具等であること
③ 政令で定めるものであること
となります。
補足知識:「機械器具等」とは
ここで、医薬品や医薬部外品のところでも出てきた②の「機械器具等」について確認しますと、薬機法の第2条第1項第2号において、
機械器具等=
・機械器具
・歯科材料
・医療用品
・衛生用品
・プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの)
・プログラムを記録した記録媒体
とされています。ここでは、プログラムが含まれていることを記憶していただければと思います。 上記の医療機器の条件のうちの①「使用目的」は、医薬品の使用目的と同様に考えられますので、「医薬品と同様の使用目的を持つ機械器具等」が医療機器であり、①と②を踏まえて、医療機器として政令で指定されることとなるので、まずは「政令」を確認すればよいことになります。
この「政令」とは、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」という名称の法令で、これの「別表第一」に列記されたものが医療機器になります。
こちらには、現在、以下のものが定められています。
・機械器具 84品目
・医療用品 6品目
・歯科材料 9品目
・衛生用品 4品目
・プログラム 3品目
・プログラムを記録した記録媒体 3品目
・動物専用医療機器 14品目⑵ 医療機器のポイント
以上のように、医療機器の定義はシンプルですので、医療機器に該当するかどうか悩んだ時は、まずは政令を確認することになります。政令に似た名称のものや機能が似ているものがあれば注意が必要になります。
ただし、政令にそのような製品があったからといっても、直ちに医療機器になるわけではありません。この判断の際に、先ほどの①②に該当するかを検討する必要があります。
例えば、ハサミを考えてみると良いと思います。
別表第一の「機械器具」の35号に「医療用はさみ」というものがあります。では、医療用はさみの機能は、文具の「はさみ」や調理で使う「台所用はさみ」と違うかといえば、ほぼ同じです。どちらも何かを切るために使います。しかし、医療用はさみは医療機器であり、文具のはさみや台所用はさみは雑貨等になります。
この判断は、「医療機器該当性」という難しい問題になり、①と②の要件に当てはまるのかを、製品の使用目的や使用される状況、販売する市場、どのような広告をしていくのかなどを総合的に検討する必要があります。
この判断については、ガイドラインや監督官庁などでも相談窓口を設けておりますし、薬機法に詳しい弁護士などにご相談したうえで対応することも必要になります。
7.再生医療等製品(薬機法第2条第9項)
⑴ 再生医療等製品の定義
最後は再生医療等製品になりますが、条文の定義は以下のとおりです。
第2条第9項
次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたものこれを整理すると、以下の①か②のいずれかになります。
① 人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもので、
【使用目的】人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
人又は動物の疾病の治療又は予防
のために使用するもので、政令で定めるもの
② 遺伝子治療を目的として、人又は動物の細胞に導入して使用するもので、政令で定めるもの
なお、医薬部外品、化粧品は除くものとされていますが、いずれにしても政令で定めるものとされています。
⑵ 再生医療等製品のポイント
最近は、再生医療技術の発展により、ヒト幹細胞コスメなどが話題になっていることもあり、今後は、医薬部外品や化粧品と再生医療等製品の区別が重要になってくると思います。
8.まとめ
以上、医薬品等に含まれる5つのものを順番に見てきました。
最後に重要なポイントをおさらいすると、
Ⅰ 形状での区別
① まず、機械器具等かそれ以外か、で区別する
⇒機械器具等であれば、医療機器、化粧品、雑貨のいずれに該当するかの判断になる
⇒機械器具等でなければ、医薬品、医薬部外品、化粧品、食品や雑貨のいずれに該当するかの判断になる
(※厳密には、再生医療等製品も含まれます)
② 機械器具等でない場合、
ⅰ 口に入れる(服用する)場合
医薬品、医薬部外品、食品のいずれに該当するか
ⅱ 身体に塗るなどして使用する場合
医薬品、医薬部外品、化粧品、雑貨のいずれに該当するか
Ⅱ 使用目的で注意するポイント
ⅰ 病気の診断、治療、予防などに関わる場合は医薬品か医療機器になる可能性がある
ⅱ 化粧品は身体を清潔にしたり美化するのみ
ⅲ 医薬部外品はⅰとⅱの中間
ⅳ 人の身体の修復、再生、遺伝子治療などに関わる場合は再生医療等製品の該当性を 判断する
といった視点を持っておくことが重要になります。
※次回からは、医薬品の販売について基本事項を解説します。そこでは、医薬品の種類、販売業に関する規制、「薬局」に関する基本事項について順次解説いたします。
連載:薬機法とは ~薬機法の基本~
『第1回 薬機法の全体像』はこちらから
『第3回 医薬品の販売と薬局 ① -医薬品の種類-』はこちらから
『第4回 医薬品の販売と薬局② -医薬品の販売と薬局-』はこちらから
『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから
『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから
監修
弁護士 鈴木 景
(都内法律事務所からインハウスローヤーを経て、2017年GVA法律事務所入所。 スタートアップから大手上場企業まで、新規事業開発支援、契約書作成レビュー支援、株式による資金調達、M&AやIPOによるExitの支援など幅広く対応。 対応領域も、医療・美容に関する広告規制対応や、食品関連ビジネス、旅行関連ビジネス、NFT関連ビジネスと幅広い。)