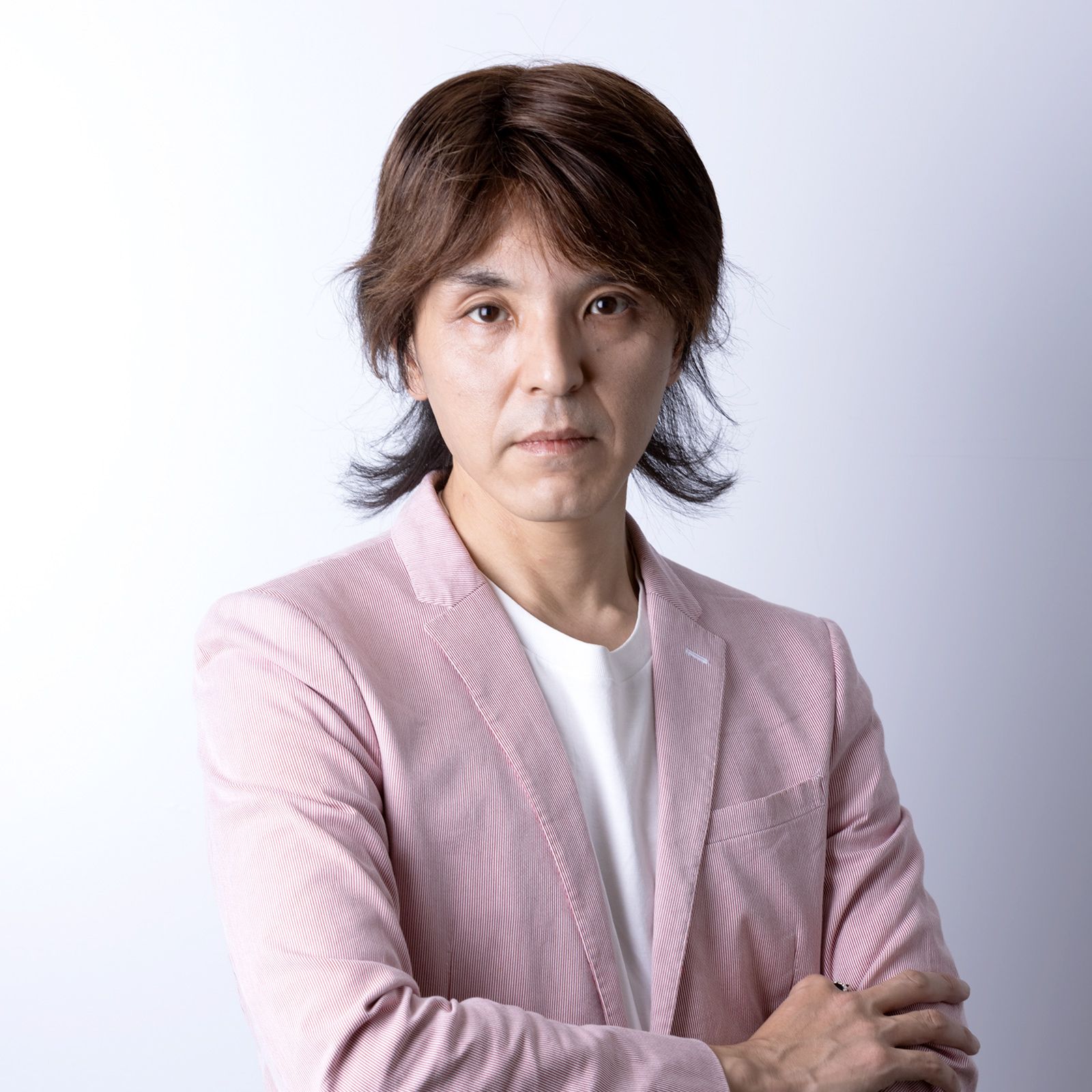執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
(※2022年3月9日に公開。2023年8月15日に記事内容をアップデートいたしました。)
1 はじめに
GVA法律事務所では、メディカル、美容、ヘルスケア領域に関して専門チームを設け、各分野について多様なサポートをさせていただいております。
その中で、もっともご相談の機会が多く、この業界の基本となる法律が薬機法(やっきほう)です。
しかし、薬機法は改正も多く、その内容も複雑ですので、基本的な事項を知りたいという声を多く耳にしております。
そこで、GVA法律事務所では、薬機法の基本を、簡単に分かりやすくお伝えするため、連載で薬機法について解説いたします。
第1回目の本稿では、薬機法の全体像や薬機法を理解するために大切な視点をご説明します。
※なお、各連載は以下のとおりです。
連載:薬機法とは ~薬機法の基本~
『第1回 薬機法の全体像』はこちらから
『第2回 「医薬品等」とは』はこちらから
『第3回 医薬品の販売と薬局 ① -医薬品の種類-』はこちらから
『第4回 医薬品の販売と薬局② -医薬品の販売と薬局-』はこちらから
『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから
『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから
『第7回 製造販売後の医薬品 -医薬品の安全管理と有効性の再確認-』はこちらから
『第8回 医薬品情報の消費者への表示-医薬品の表示、添付文書、広告-』はこちらから
2 薬機法とは?
⑴ 薬機法の名称、薬事法との関係
薬機法は、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。とても長い名前の法律ですが、要するに、
① 医薬品、医療機器等に関して、
② その有効性と安全性を確保するための法律
ということになります。
医薬品や医療機器などの医療に関係する物は、ちゃんとした効き目がないと困りますし、人の体や命に危険があるものでも困ります。そのようなことがないようにするための法律です。
薬機法は、もともとは「薬事法(やくじほう)という名前で、昭和35年に制定されましたが、それから何度も改正され、名称も変更されています。なお、名称は変わりましたが、同じ法律です。 医薬品の「薬」と医療機器の「機」から「薬機法」と略されています。英語ではPharmaceutical and Medical Device Actになります。
⑵ 薬機法の全体像
条文数は91条まで(その中に追加されたものも多くあるため、実際の条文数は100を超えます)あり、条文も読みやすいものではないので、全体像を掴めない方も多くいらっしゃると思います。
まず、薬機法の目次を見てみましょう。
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 地方薬事審議会(第三条)
第三章 薬局(第四条―第十一条)
第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業(第十二条―第二十三条)
第五章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業(第二十三条の二―第二十三条の二の二十二)
第二節 登録認証機関(第二十三条の二の二十三―第二十三条の十九)
第六章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業(第二十三条の二十―第二十三条の四十二)
第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
第一節 医薬品の販売業(第二十四条―第三十八条)
第二節 医療機器の販売業、貸与業及び修理業(第三十九条―第四十条の四)
第三節 再生医療等製品の販売業(第四十条の五―第四十条の七)
第八章 医薬品等の基準及び検定(第四十一条―第四十三条)
第九章 医薬品等の取扱い
第一節 毒薬及び劇薬の取扱い(第四十四条―第四十八条)
第二節 医薬品の取扱い(第四十九条―第五十八条)
第三節 医薬部外品の取扱い(第五十九条・第六十条)
第四節 化粧品の取扱い(第六十一条・第六十二条)
第五節 医療機器の取扱い(第六十三条―第六十五条)
第六節 再生医療等製品の取扱い(第六十五条の二―第六十五条の五)
第十章 医薬品等の広告(第六十六条―第六十八条)
第十一章 医薬品等の安全対策(第六十八条の二―第六十八条の十五)
第十二章 生物由来製品の特例(第六十八条の十六―第六十八条の二十五)
第十三章 監督(第六十九条―第七十六条の三の三)
第十四章 医薬品等行政評価・監視委員会(第七十六条の三の四―第七十六条の三の十二)
第十五章 指定薬物の取扱い(第七十六条の四―第七十七条)
第十六章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品等の指定等(第七十七条の二―第七十七条の七)
第十七章 雑則(第七十八条―第八十三条の五)
第十八章 罰則(第八十三条の六―第九十一条)このように見ると、全部で18という多くの章に分かれていることが分かりますし、表題にも専門用語が使われておりますので、目次だけ見ても全体像はつかみにくいと思います。
そこで、この中で特に重要な部分を整理すると、以下のようになります。
第1章 「定義」(※対象となる医薬品等の範囲)
第3章の「薬局」に関すること
第4章~第7章の「事業者」に関すること
第8章・第9章の「基準、取扱い」に関すること
第10章の「広告」に関すること
第11章の「安全対策」に関すること
第13章の「監督」に関すること
第15章の「指定薬物」に関すること
※第13章の「監督」は、規制法という性質から当然のものです。また、第14章の指定薬物については、刑事法としての意味合いが強いものとなります。
※ここに挙げていないその他の事項も制度としては重要ですが、特殊な事項であり、薬機法の全体像を把握する意味での優先度は低いと考えられます。これを整理すると、
① 医薬品等を扱う「薬局」に関するルール
② 医薬品等の「製造販売事業者、販売業者」に関するルール
③ 医薬品等の「広告」に関するルール
④ 医薬品等の「安全対策」に関するルールとなります。
⑶ 薬機法の2つの視点
このように見ると、薬機法は、
①医薬品等に関して関わる人々である薬局、事業者に対するルール
②医薬品自体を対象とした広告、取扱い、安全対策に関するルールを定めているものであることがお分かりになるかと思います。
要するに、医薬品等を扱う「人々」に対する規制と、医薬品等という「物」自体に対する規制の2つです。
この「人々」と「物」という2つの視点は、薬機法を理解する上で重要な視点となります。
3 薬機法を分かりやすくする視点~医薬品などは「特別な物」~
多くの法律、特に事業法は、特定の「事業」(ビジネス)を対象に規制をしています。
特定の事業では、特有の様々な問題が生じるので、それを防ぐため、必要な規制を設けています。
一方で、世の中には様々な商品や製品(物・モノ)があります。この「物」に関しては、民法で「物(ブツ)」として、所有権などの基本的な事項を定めているものの、その扱いについてはそれほど多くの規制があるわけではありません。
しかし、「物」のなかには、取扱いに配慮が必要なものもあります。つまり、人体や環境のような大切なものに影響を与えるようなものです。例えば、人体に影響する物としては「食品」や「毒物」、「覚せい剤」や「大麻」等の薬物がありますし、環境に影響する物としては「廃棄物」があります。このような「物」については、特別なルールが必要です。
そして、このような特別な物に、医薬品や医療機器もあてはまります。直接に人体に使う物なので、特別の規制が必要になります。このイメージを持つと、薬機法の規制についても理解しやすいと思います。
医薬品や医療機器 ⇒ 人体に直接使う
⇒ 影響が大きいので、特別なルール「薬機法」が必要になる4 連載の内容
以上を踏まえて、この連載では、薬機法の重要なものを分かりやすく伝えていきます。以下、今後の内容を簡単にご説明します(なお、内容は変更になる可能性もあります)。
⑴ 「医薬品等」とは?
薬機法は、医薬品と医療機器だけなく、「医薬品等」に適用されます。
第2回目では、薬機法が対象とする「物/モノ」である「医薬品等」について解説します。「医薬品等」には、医薬品のほか、医療機器、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品が含まれていますが、これらに該当しなければ薬機法の適用はありません。
『第2回 「医薬品等」とは』はこちらから
⑵ 医薬品の販売/「薬局」に関するルール
医薬品等は、病院やクリニックで処方されるほかに、薬局やドラッグストアで購入できます。ただ、医薬品は自由に販売することはできません。医薬品を販売するためには、ルールに従うことが大切です。また、薬局とドラッグストアは異なります。
そこで、3回目と4回目では、もっとも身近な「医薬品の販売」について、2回に分けて医薬品の販売や薬局に関するルールについて重要な事項を解説します。販売を理解することで、次の製造販売や製造が理解しやすくなるので、まずここから始めます。
『第3回 医薬品の販売と薬局 ① -医薬品の種類-』はこちらから
『第4回 医薬品の販売と薬局② -医薬品の販売と薬局-』はこちらから
⑶ 医薬品の製造販売・製造に関するルール
薬機法では「製造販売」という特殊な言葉が登場します。製造でも、販売でもない「製造販売」です。「薬事申請」とも密接に関わります。販売や製造とは何が違うのか、という視点が大切です。
第5回、第6回の2回に分けて解説します。
『第5回 医薬品の製造販売① -全体像と製造販売業・製造業・製造管理-』はこちらから
『第6回 医薬品の製造販売② -医薬品の製造販売承認-』はこちらから
⑷ 市場流通後の医薬品に関するルール
医薬品の重要なポイントとして、事業者にとっては、販売しても終わらない、ということが挙げられます。市場に流通した後も、安全性などを確認することが必要になります。
そのため、第7回では、医薬品の市場流通後のルールを説明します。
『第7回 製造販売後の医薬品 -医薬品の安全管理と有効性の再確認-』はこちらから
⑸ 医薬品の消費者への表示に関するルール
医薬品は特別な物なので、注意事項や使い方(使用方法、服用方法)が決められているなど、普通の物とは扱いが異なります。そのため、消費者にも、このことを正確に伝えることが必要です。厳しい広告ルールがあるのもそのためです。
そのため、第8回では、医薬品の表示、添付文書、そして広告について解説します。
『第8回 医薬品情報の消費者への表示-医薬品の表示、添付文書、広告-』はこちらから
⑹ 医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品に関するルール
薬機法は、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品にも適用されます。医薬品に関するルールと共通する部分もありますが、独自のルールもあります。そのため、第9回以降で、各製品ごとのルールを解説していきます(順次公開します)。