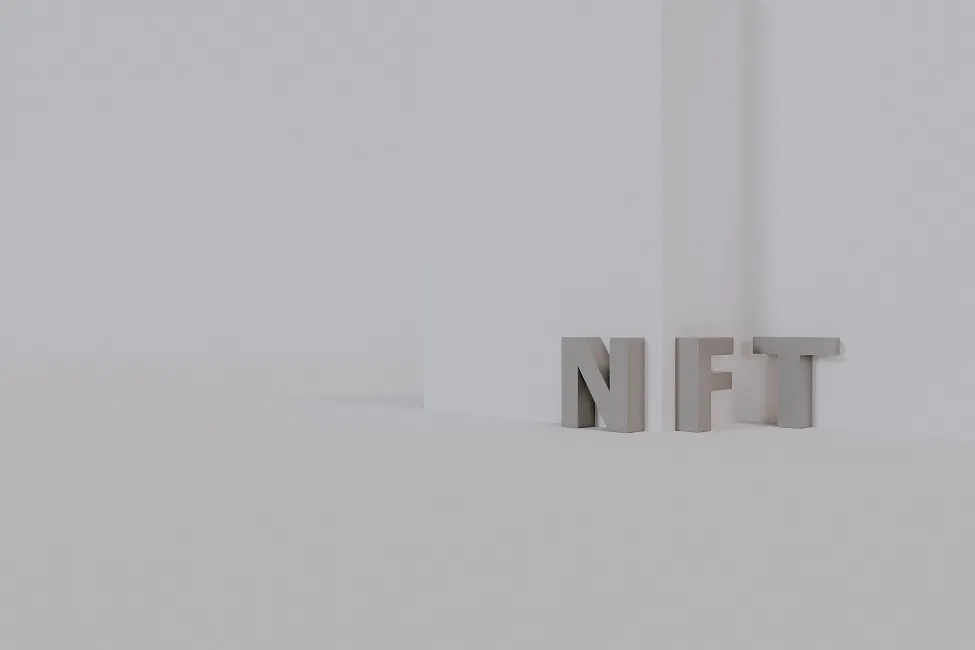『NFT連載記事「弁護士がNFTを発行して分かったこと」 第1回 NFTと法律』はこちらから
1. 何をNFTにするか?
さて、今回弊所でNFTを発行するにあたって、法律事務所としてどんなコンテンツをNFT化するかをまず検討する必要がありましたが、多くのNFT事例の相談を受けてきたものの、いざ自分達がNFTを発行するとなると難しいものです。やるからには、法律事務所ならではで、かつ、比較的新規性のあるコンテンツをNFTにしたいね、ということで、一般的なNFTの発行事例なども踏まえつつ、プラクティスチームのメンバーでアイデアを出し合って検討しました。
(1)一般的なNFT事例
OpenSeaを初め、各NFTマーケットプレイスで販売されている一般的なNFT事例としては、絵画・写真・コラージュ等のアート作品、音楽作品、動画コンテンツ、Twitter上での著名人のツイートといった事例がぱっと思い浮かびます。特にアート作品については驚くほど高額でデジタルアートやゲームキャラクターのNFTが取引される事例が世界的にも有名であり、視覚的にも分かりやすい部分があります。
(2)法律事務所が発行するとしたら?
上記のとおり、一般的な事例を踏まえると、アート作品のNFTはまず選択肢に上がってきましたが、我々が書いた落書きのような絵をNFT化しても…ということで、GVA法律事務所のロゴ等をNFT化する案を検討しました。さすがに、現ロゴをNFT化すると事務所の活動に支障が大きいですが、最近GVA法律事務所では、ロゴやHPを大幅にリニューアルしたため、使用頻度の下がる旧バージョンのロゴをNFT化するあるいは、このNFT化プロジェクトを主導する産業別チーム「Web3(ウェブスリー)チーム」専用のロゴをデジタルデータ化してNFTと紐づけるのはどうかと考えました。ただ、世に多数のデジタルアートNFTが発行されている時分において、法律事務所の使わなくなったロゴや内部のチームロゴを単にNFT化したとしても面白味がなく、注目度も下がるため、没となりました(我々所属弁護士からすると、レアではあるのですが…笑)。
他にも、顧問契約上の地位、相談割引の権利を付与するなど法律事務所として提供可能なサービスに関する何らかの権利をNFT化するということも考えましたが、あまり複雑な内容だとメリットが理解されず、逆に魅力が低減してしまう可能性がありました。
上記のように色々と検討した結果、最終的には、Twitter上のツイートのNFT化の事例なども参考に、弊所で作成した法務記事をNFT化することに決定しました。我々弁護士ならではの価値が提供できるものであること、シンプルであり、かつ、ツイートやアートなどのように、唯一性が際立つものであること、購入者もNFTを購入して何ができるか想像しやすいと思われること、当該記事を購入者のHP等に掲載してPV数が上がれば購入者にメリットもあるのではないか思われること、といった点が決め手でした。
具体的には、弊所HPに過去に掲載していたNFTに関する解説記事をNFT化します。ただ、弊社のHPに掲載中の法務記事を閲覧可能、というだけでは旨味がないので、掲載中の当該法務記事は弊所HPでの掲載を取りやめ、NFT購入者が当該法務記事を独占利用できるという権利を付けてNFT化することとしました。詳細を以下で説明をしていきます。
2. 記事をNFT化するにあたって検討したこと
(1)販売対象(ライセンス)
法務記事をNFT化する、として、まず、NFTを購入した人が如何なる権利を取得するか検討しましたが、結論としては、法務記事の著作権そのものではなく、当該法務記事のライセンスを付与することとしています。具体的には、法務記事のNFTを購入した方(NFT保有者)は、インターネット上で、当該法務記事をそのまま自身のHP、ブログ等で有償又は無償を問わず掲載することができる権利をライセンスとして付与することにしました。
(2)著作権の取扱い
アート、音楽などのコンテンツでも同様ですが、当該コンテンツをNFT化する際に特に重要となるのが、当該コンテンツの著作権の取扱いです。
まず、第1回記事でも取り上げたとおり、NFT自体はブロックチェーン上に記録されるデータ(トークン)にすぎず、基本的に著作権法上の著作物(同法第2条第1項1号)には該当せず著作権は発生しませんが、NFTと紐づけるアセット、コンテンツは著作物として著作権が発生する場合が多く、NFTを販売する際に、当該著作権の取扱いを検討する必要があります。
この点、法的には、著作物の著作権は、当該著作物の著作者に帰属するのが原則ですので、まず作成者であるGVA法律事務所に帰属します(厳密には、原始的には当該記事を作成したGVA法律事務所の弁護士個人に帰属しますが、ここではシンプルに契約等によりGVA法律事務所にその権利を帰属させたものとしてGVA法律事務所に著作権が帰属するものとします)。
その上で、NFTの販売時に、対象とするコンテンツ(法務記事)の著作権をNFT購入者に移転させるかどうか、検討しましたが、著作権を移転させるとなると、当該記事を自由に改変等できることになり、法務記事そのものの価値が揺らいでしまう可能性がありましたので、著作権はあくまでGVA法律事務所に帰属する形としました(なお、著作者である我々弁護士は法務記事について著作者人格権という譲渡不可能な権利を保有していますので、著作権が譲渡されたとしても当該権利を行使することは可能です)。一般的にも、アート、音楽NFTでは、著作権自体は譲渡しないケースが基本的なスタイルかと思います。
したがって、NFT購入者には、法務記事の著作権を譲渡するのではなく、NFTと紐づけた法務記事を所定の範囲で自由に利用いただくためのライセンスを付与する形としました。具体的には、購入した法務記事をインターネット上で独占公開できるよう、著作権法上の公衆送信権(インターネット等により、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利。著作権法23条)、複製権(著作物を複製する権利。著作権法21条)のライセンスを付与します。
また、法務記事を安全にご利用頂く観点や内容の正確性を維持する観点から、ライセンスの細かい内容として、
紙の状態での利用(出版・譲渡等)は利用状況の把握が難しくなることから対象から除外する
法務記事内容の改変は原則不可能とし、改変を要望される場合には、個別に著作権者であるGVA法律事務所の承諾が必要である
法務記事の掲載時には、法務記事の著作権者がGVA法律事務所であることを表示する義務がある
といった条件を規定することとしました。
(3)転売時の取り決め
次に発行した法務記事のNFTが、初回購入後にNFTマーケットプレイス等で初回購入者から第三者に転売される際の取り決めをどのようなものとするかも検討する必要があります。
まず、今回の法務記事のメリットは、独占的に法務記事を公開できる、という点にありますので、初回購入者(転売元)がライセンスを保持したままで、転売元が引き続き当該NFTを自由に掲載することができる権利を保有する形にしてしまうと、転売先(買主)がNFTを保有するメリットが少なくなってしまうため、サブライセンスは不可能であり、かつ、NFTを転売した場合は、転売元では法務記事の利用を停止する、という取り決めとしました。
したがって、法務記事のライセンサーであるGVA法律事務所とライセンシーである初回購入者との間のライセンス契約におけるライセンサーとしての契約上の地位がNFTの移転(転売)に伴って転売先に譲渡される(以後の転売も同様)、ということになります。
また、法務記事の安全な取扱いを担保する観点から、“転売時には、転売元から転売先に対してNFTの利用条件を引き継ぐ”旨の条件と、NFTが転々譲渡された際に、ライセンサーが誰であるか、弊所で把握できるよう、“転売時にはGVA法律事務所に対して転売先が誰であるかを報告する”旨の条件も設定することとしました(報告条件に関しては一般的にはそこまで設定はしない例が多いとは思いますが、コンテンツの特性に応じて、このような条件を設定することも有効かと思います)。
以上、この連載第2回では、NFTとするコンテンツの検討過程と著作権や転売時の条件などのベースとなる条件の設定について解説しました。
次章以降では、このNFTをどのプラットフォームで販売するか、また、本記事で検討した条件も踏まえて、どのようなNFTの利用規約を作成するか、について解説していきます。
『NFT連載記事「弁護士がNFTを発行して分かったこと」 第1回 NFTと法律』はこちらから
監修
弁護士 熊谷 直弥
(2012年の弁護士登録以来、一貫して企業法務を扱う。中小企業から上場企業まで広く担当し、契約法務、人事労務、紛争、渉外法務、商標等で研鑽を積む。2019年GVA法律事務所入所後、スタートアップ企業の法務支援に注力し、IPOやその先の成長までの伴走を複数経験。顧問先スタートアップSaaS企業の監査役を務める。 所内のWEB3チームのリーダーとして、NFT関連ビジネスや暗号資産、STO、その他トークンビジネス等の研究及び実務を対応。NFT書籍の監修の他セミナー等でのNFTに関する情報発信も多数。)