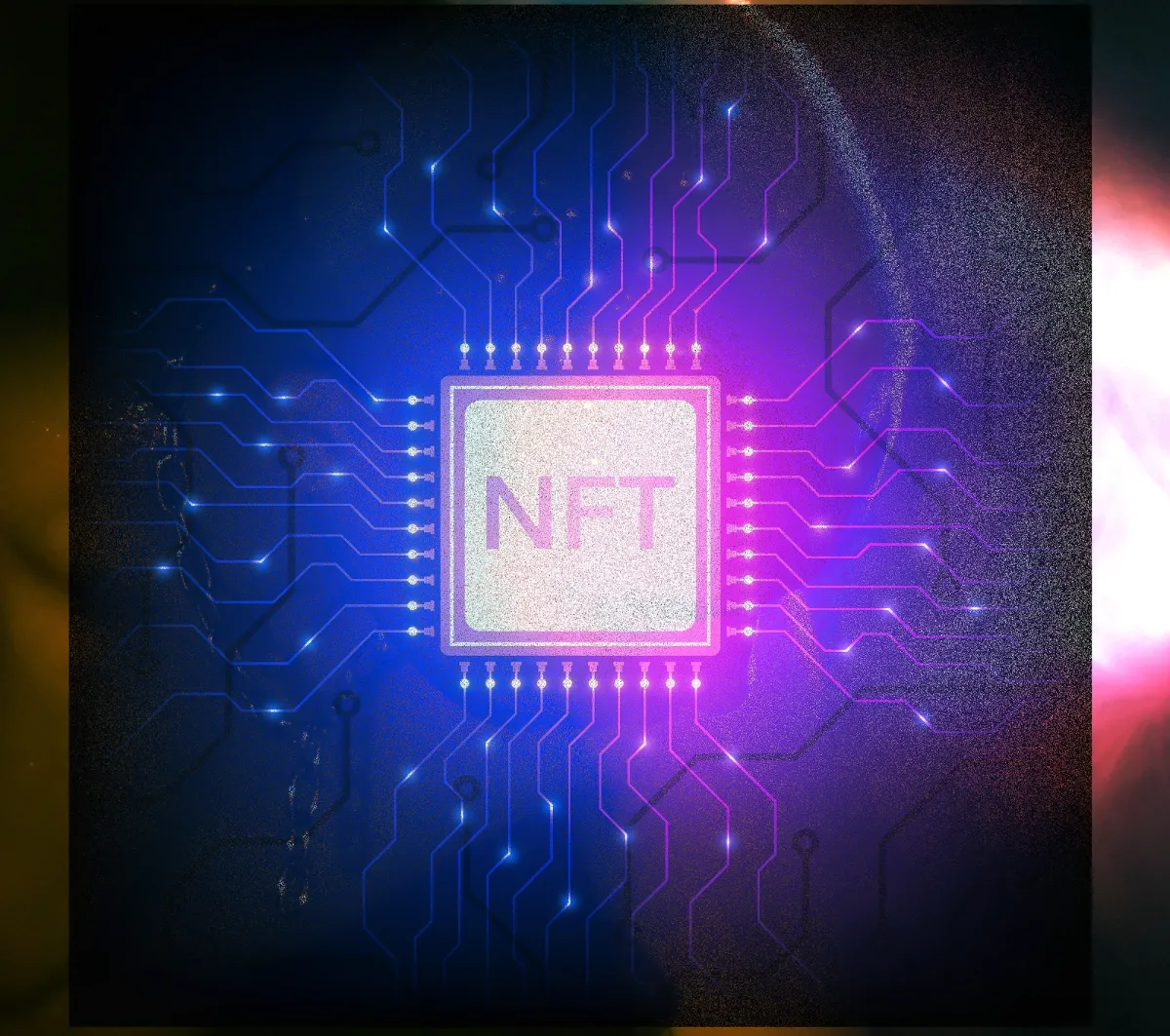本稿では、デジタルアートの高額販売事例や国内の二次流通サイトの出現などで昨今注目が高まっているNFT(Non-Fungible Token)と賭博罪の関係について概説します。
(※2022年3月30日に自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討PT(平将明 PT座長)より「NFTホワイトペーパー(案)~Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略~」が発表されため、一部加筆致しました。)
(※2022年7月25日、最新の議論状況等を踏まえて一部加筆修正しました)
1 NFTと賭博罪
(1)NFTの代表例-ゲームのキャラクタ・アイテムなど
ブロックチェーン技術を活用したNFTによってトークン化する対象の代表例としては、ゲームのアイテムやキャラクターが挙げられます。
これらは、従前、あるタイトルのゲームという閉ざされた世界においてのみ価値を有するデータであり、ゲームを離れては存在できず、現実世界での資産性を持たないものでした。スマートフォンによるアプリゲーム等のオンラインゲームが主流になっていく中で、一部のユーザーによるいわゆるリアルマネートレード(RMT)というアカウントの売買等により、ゲーム上の資産の現金化を図ろうという行為もみられましたが、RMTは通常ゲームの運営事業者の利用規約等で明確に禁止されている行為であり、ゲーム内資産の健全かつ適法な資産化とは言えないものでありました。
ゲーム内アイテムやキャラクターのNFT化は、ゲームの運営事業者が公式にゲーム内資産を現実世界の資産として認めようという試みであり、ユーザーにとっては、ゲーム内で獲得した資産が現実世界の資産になるという点で、大きな意義を有するものとなりました。NFT/ブロックチェーンゲームの普及は、Play to Earn (遊んで稼ぐ)の概念を生み出し、WEB3.0の世界へもつながっていくものであります。
(2)有償ガチャ等
主にスマートフォン上でプレイするアプリゲームや基本無料の課金制オンラインゲームなどでは、いわゆるガチャと呼ばれるくじの方式でキャラクターやアイテムを獲得できる仕組みが多く採用されています。また、ガチャは、一定のプレイ時間やプレイ成果に応じて無料で獲得できるゲーム内トークンで利用できる場合に加えて、ゲーム内トークンをクレジットカードや携帯電話のキャリア決済等で購入することで利用できるとする仕様とされることが多くなっています。
上記のガチャのうち、ガチャを回すために金銭の支払いが必要となる有償ガチャは、ガチャによって獲得できるNFTのキャラクター等に市場価値が生じ、いわば値段が付くことによって、ガチャを回すのに必要となるゲーム内トークンの価値以上のキャラクター等が獲得できたり、反対にゲーム内トークンの価値を下回るキャラクターしか獲得できない場合が生じたりすることによって、一種のギャンブルが成立することから、刑法上の「賭博」行為(第185条など)への該当性が問題となります。
また、この問題は、有償ガチャに限らず、ランダム型販売、Reveal型販売等といわれるような購入するまで取得できるNFTの内容が分からないような販売形態についても同様です。
2 賭博罪の構成要件
刑法上、賭博罪(第185条)は、次のように規定されています。
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。そして、賭博とは一般に「偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」(西田典之『刑法各論』第3版弘文堂・362頁)と解釈されています。したがって、但書も含めて「賭博」行為を構成する要素(「構成要件」と言います。)を再整理すると、次の4点になります。
①偶然の勝敗により
②財物や財産上の利益の
③得喪を争うこと
④賭けの対象は、一時の娯楽に供する物ではないこと
上記のうち、特にポイントとなることが多いのは、③の要件です。例えば、年始の風物詩として定着した福袋や、高額ワインが当たるワインBOXについては、一定額を支払って購入し、その中身の経済的価値は様々であるという点で、ギャンブル的な要素があるものの、これらのケースでは、福袋の中身等が少なくとも購入額以上となっていることを保証していることで、利用者の側に「損」=「喪」がないことから、賭博には該当しないものと考えられます。
また、④の「一時の娯楽に供する物」としては、財産的価値が大きくなく、その場で直ちに消費されるものが想定されており、飲食物やタバコなどが典型例とされています。
3 有償NFTガチャ等の賭博行為該当性
上記2の整理を前提に、改めて有償NFTガチャ等の賭博罪該当性を検討すると、一定の確率にしたがって特定のNFTアイテム等が獲得できるプログラムは、①偶然の勝敗性の要件を充足します。
次に、対象となるNFTアイテム等がゲーム内のみならず、ゲーム外のNFTプラットフォーム等において流通可能となることで、いわば「値段が付く」状態になることから、当該NFTは②財物や財産上の利益に該当します。この点、当該NFTアイテム等の価値がごく少額(ガチャを回すのに必要な対価が極めて安い)であって、なおかつ有効期限もごく限られている(獲得から●時間後に使用不可になる等)のであれば、④一時の娯楽に供する物に該当する可能性が無い訳ではありませんが、通常の設計であれば、④の例外要件を充たすのは難しいと考えます。
最後に、ガチャを回すことで獲得できるNFTアイテム等の価値が当該ガチャを回すのに必要な金銭を上回ったり、下回ったりする場合、ハズレが含まれていて全く何もNFTアイテム等を獲得できない場合などは、プレイヤーの側に「得喪」が生じており、③の要件を充足するものと考えます。具体的にガチャで獲得できるNFTアイテム等の価値をどのように算定するかというのは難しい問題となりますが、例えば同じNFTアイテム等をガチャ以外でも1点●●●円で販売している場合には、その価格が参考にされるものと思われます。
この点、二次流通時の価格は必ずしも一次流通時の価格とはイコールではなく、仮に二次流通時の価格に差が出るNFTアイテムであったとしても、一次流通時=ガチャによるアイテムの入手時にプレイヤーは、何らかのNFTアイテム等を入手できていれば、得喪を生じていないとの見解も出てきました(※1)。確かに、プレイヤーとしては、A~CまでのいずれかのNFTアイテムを入手できるガチャを1ETHでプレイして、A~CのいずれかのNFTアイテムを入手できたのであれば、一次流通の時点でA~Cの価値はいずれも1ETHであり、したがって、プレイヤーに得喪は生じていないと考えることも合理的です。一次流通の時点でアイテムショップでの個別販売や二次流通での取引事例が無ければ、仮にレアリティの差があって、将来の二次流通価格が異なることが予想されたとしても(それでも将来の二次流通価格は誰にも分らないはず)、プレイヤーの得喪は確定しておらず、この時点で違法賭博だと断じられるのは違和感があるところです。ただし、この見解に拠る場合も、ハズレがあり、全くNFTアイテム等を入手できないことがある場合には、得喪は生じていると考えられます。
以上から、有償NFTガチャのプレイはNFT/ブロックチェーンゲーム事業者側の設計次第で賭博罪(刑法第185条)に該当する可能性が高い場合も低い場合もある、との結論になります。現時点では、法解釈について様々な意見が出されているところであり、確定的な見解を得るのは難しい状況ですが、例えば、有償ガチャのNFTアイテム等を個別に単品販売しない、発行事業者が自らNFTアイテム等をユーザーから買い取ることはしない、有償ガチャにハズレを作らない等の工夫により、有償NFTガチャの仕組みを提供するNFT/ブロックチェーンゲーム事業者の側に賭博場開帳罪(同第186条第2項)が成立する可能性を低減することは可能であるため、ガチャの仕組みによるNFTアイテム等を配布する場合には、その制度設計等に慎重な検討が必要となります。
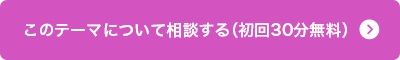
4 各業界団体のガイドラインにおける整理
(1)日本暗号資産ビジネス協会のガイドライン
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会が策定した「NFTビジネスに関するガイドライン」(第1版・令和3年4月26日策定)では、次のとおり記載して、有償でのNFTガチャと賭博罪の成立の可能性について注意喚起を行っていました。
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
■ガチャ
NFTサービスにおいてガチャを行うことは、当該NFTサービスの仕組み次第では、賭博に該当する可能性があるため、ガチャの実装について慎重な検討を要します。
すなわち、ガチャとは、ゲーム内通貨等を消費し、ランダムに貴重なアイテムを得られる仕組みです。そのため、例えば、専らプログラムによって獲得するアイテムがランダムに決定され(①)、当該獲得可能なアイテムが財産的価値を有し(②)、かつゲーム内通貨等を消費して当該ゲーム内通貨等と価値の異なるアイテムを獲得するような場合(③)、賭博罪が成立する可能性が高いと思われます。上記は、昨今の賭博罪に関する議論の深化を受けて、令和4年3月31日改訂の第2版で下記のとおり、賭博罪に該当しないと考えられる範囲について一歩踏み込んだ内容に修正されました。
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
NFTは通常、財産的価値を有すると考えられるため、NFTを利用したゲーム(以下、NFTゲーム)では、サービス設計によっては賭博該当性に留意すべき場合があります。
各会員企業にて弁護士等の専門家に照会する等して、適法性を確保したサービス設計となるようご留意ください。
特に留意を要するケースとして、パッケージ販売やガチャの手法を用いてNFTを販売する場合、こうした手法ではNFTの獲得に偶然性があるのが通常であることを考慮しますと、販売者と購入者との間や購入者と他の購入者との間で財産上の利益の得喪を争う関係(②・③)が認められるかを検討すべきこととなります。その判断のためには、サービス形態に応じた個別具体的な検討が必要ですが、例えば、販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなりますので、購入者において、その販売価格に応じたNFTを獲得していると評価できる事情があれば、当該サービスは購入者が販売者との間で財産上の利益の得喪を争うものではないと整理しうると考えられます。(2)ブロックチェーンコンテンツ協会のガイドライン
一般社団法人ブロックチェーンコンテンツ協会が策定した「ブロックチェーンコンテンツ協会ガイドライン」(第2版・2020年12月25日策定)では、NFTアイテム等が「一時の娯楽に供する物」との賭博罪成立の例外要件に該当しないとの見解を示したうえで、より具体的に同協会として賭博罪に該当し得ることを理由に次の事項を禁止事項(同ガイドライン1-1)として提唱しています。
1)NFT 等その他換金性を有するゲーム内アイテムを排出する有償ガチャを行うことは賭博に該当する可能性が高いため、実施できないと考えます。
2)イベント参加者から有償で参加費を徴収し,イベント参加者への報酬を当該参加費から分配する形でゲーム内イベントを実施することは賭博に該当する可能性が高いため、実施できないと考えます。
3)ゲーム内アイテムを掛け合わせて消滅させることで、ランダムに新たな NFT 等その他換金性を有するゲーム内アイテムを排出(合成)する場合、消滅するゲーム内アイテムと、それにより排出される NFT 等の価値に差が生じることが財産上の利益の得喪と評価され、賭博罪に該当しうることから、その取扱いについては十分な注意が必要です。
4)ゲームプレイにおいて換金性を有するゲーム内アイテムを報酬として付与する場合、当該報酬付与の仕組みが財産上の利益の得喪と評価され、賭博罪に該当する場合もあり得ることから、その取扱いについては十分な注意が必要です。
※有償:法定通貨、暗号資産、それらから購入したゲーム内通貨などを対価として使用すること
※換金性:法定通貨、暗号資産に転化が可能な性質
※ゲーム内アイテム:ゲーム内において利用・消費することのできる有償・無償のアイテム全般※NFT:ゲーム内アイテムのうち、ERC721 等の規格による非代替性トークンで発行された換金性を有するもの5 自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討PTのホワイトペーパー案
2022年3月30日、自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討PT(平将明 PT座長)より「NFTホワイトペーパー(案)~Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略~」が公表され、NFTと賭博罪についての論点は、「NFTビジネスの賭博該当性をめぐる解釈の整理」という形で第1番目に取り上げられました。
問題状況の整理として、ランダム型販売について、
日本でも多くの事業者が類似したサービスの提供を試みているが、このようなサービスに関する賭博罪(刑法185条)の成否が明らかではないため、事業者の間に萎縮効果が発生し、その結果、NFTビジネスの発展が大きく阻害されている状況にある。
このようなサービスの賭博罪の成否については、これまで法務省を始めとする関係省庁からその見解が示されたことはなく、事業者が委縮し、新しいNFTビジネスに取り組むことを阻害している状況が継続している。
(※7頁3(1)ア)との指摘がされており、これに対して、
①事業者が新たなNFTサービスを展開するに際して賭博罪の成否について関係省庁から事前に見解を求めることができる仕組みの整備
②特にNFTを用いたランダム型販売と二次流通市場の併設は、海外での普及状況に鑑みて、少なくとも一定の事業形態が賭博に該当しないことを明確にすべき
③ただし、消費者保護の観点から一定のルール整備は必要で、事業者によるガイドラインの制定等が期待される
(※7頁3(1)イ参照)との3点が提言されています。
上記のホワイトペーパー(案)の内容は、その後、自民党デジタル社会推進本部の「デジタル・ニッポン2022~デジタルによる新しい資本主義への挑戦~」の一部として2022年4月26日に正式公表されており、同年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)にも「ブロックチェーン技術を基盤とするNFTやDAOの利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備の検討を進める。さらに、メタバースも含めたコンテンツの利用拡大に向け、2023 年通常国会での関連法案の提出を図る。」(17頁、文注省略)との表現で盛り込まれています。
今後、具体的にどのような形でNFTと賭博罪に関する論点整理と環境整備が進んでいくかは引き続き注視をしていく必要がありますが、①及び②が実現することで、本論点の多くが解消されることが期待されます。また、現在業界団体において進められている③ガイドラインの制定が①及び②の立法的な解決の呼び水となることが期待されます。
6 まとめ
上記のとおり、NFTアイテム等を有償ガチャ等の仕組みによって販売するサービスの導入は、今のところ実際の摘発例や確立された裁判例等は見当たらないものの、現状では、賭博罪に該当する可能性はあり、慎重な制度設計が必要です。自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討PTの提言を受けて今後、立法的な解決や業界団体における自主規制ガイドラインの制定など更なる環境整備が進むことが期待されますが、当面の間は、現行の法令に従い、最新の議論をキャッチアップしながら賭博罪に該当しないよう慎重な対応が必要となります。
本稿では言及しきれなかったNFTを使ったアイテム合成の仕組みなども賭博罪との関係で注意が必要です。
違法賭博に該当しないようにするため、NFTアイテム等の販売・配布方法に関するNFT/ブロックチェーンゲームの具体的な制度設計については、是非弊所にご相談ください。
(※1)2022年3月22日経済産業省「第5回スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に向けた権利の在り方研究会」資料5「賭博罪をめぐる論点について」(東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆
[PDF]
監修
弁護士 小名木 俊太郎
(企業法務においては 幅広いサービスを提供中。 ストックオプション、FinTech、EC、M&A・企業買収、IPO支援、人事労務、IT法務、上場企業法務、その他クライアントに応じた法務戦略の構築に従事する。セミナーの講師、執筆実績も多数。)
2022年3月1日 公開
2022年7月27日 更新