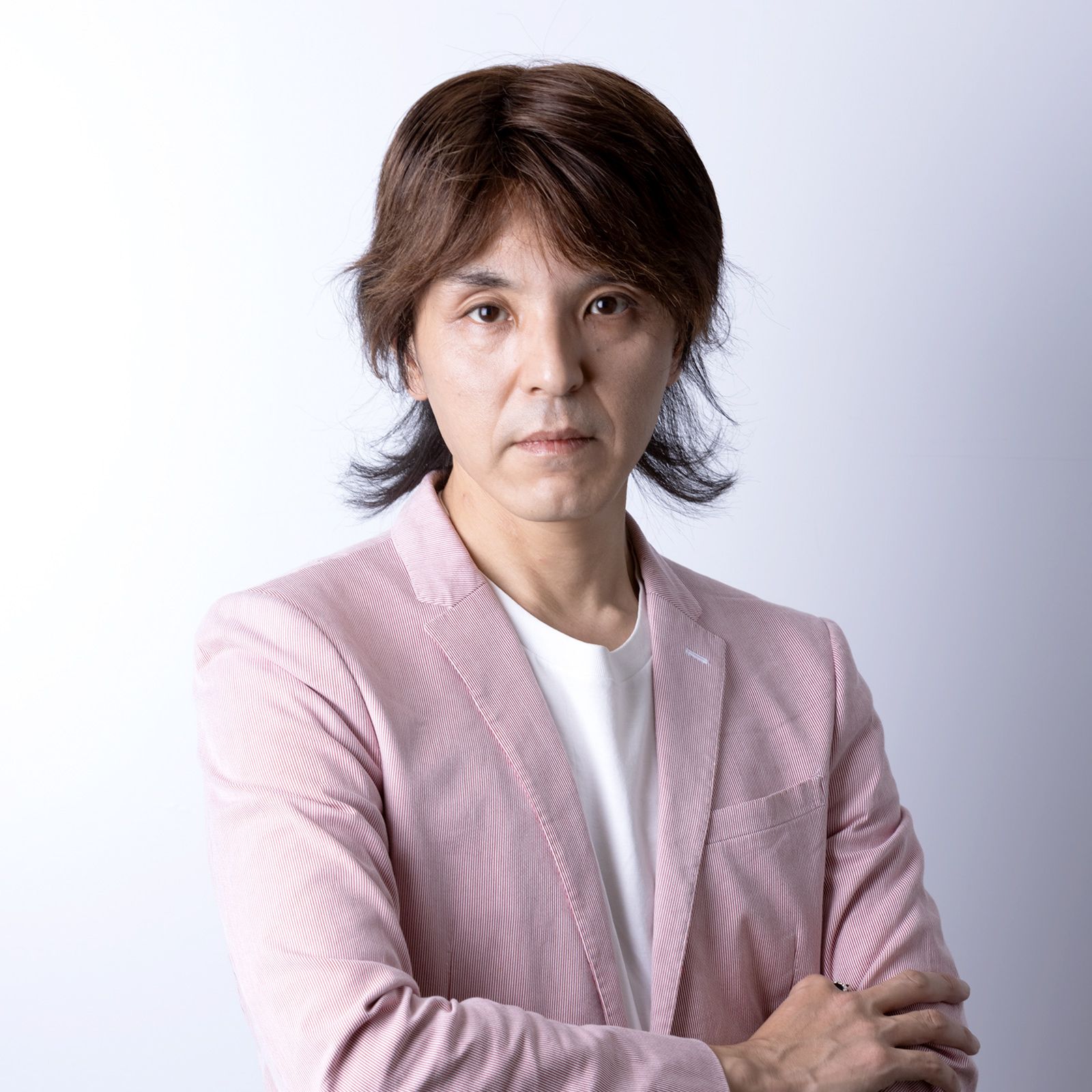執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
- 1 こんな広告していませんか?
- 2 病院・クリニックの広告ルールの概要
- ⑴ 広告ルールのきほん
- ⑵ 医療広告ルールの全体イメージ
- ⑶ 「限定解除」
- 3 「広告」になるのはどんなとき?
- ⑴ 「広告」の2要件
- ⑵ 「広告」にならないケース
- ⑶ 病院のホームページや医師個人のSNS
- ⑷ まとめ
- 4 病院の広告でできること
- ⑴ 業務の技能・療法・経歴以外のことは自由に広告できる
- ⑵ 広告してよいとされる事項は広告できる
- ⑶ 自由診療の内容は一定事項を併記すれば広告できる
- 5 やってはいけない広告
- ⑴ 虚偽の広告
- ⑵ 比較広告はしないこと
- ⑶ 診療の内容・効果に関する体験談は広告できない
- ⑷ 費用を強調する広告はできない
- 6 ありがちな違反ケース
- ⑴ 虚偽広告になってしまうケース
- ⑵ 比較優良広告になってしまうケース
- ⑶ 誇大広告になってしまうケース
- ⑷ 治療に関する体験談を広告するケース
- ⑸ 費用を強調するケース
- 7 違反してしまったらどうなる?
- 8 ポイントのチェックリスト
- 9 迷ってしまったときは
病院やクリニックでも患者を集めるために広告をすることができます。しかし、他のお店とは違って、病院やクリニックの場合、特に厳しい広告ルールがあります。この内容をまとめたものが医療広告ガイドラインです。
1 こんな広告していませんか?
病院やクリニックでも、多くの患者さんに来てもらおうと様々な広告がされています。インターネットだけでなく、電車やバスの広告、雑誌の企画広告など、私たちもよく目にします。
特にスマートフォンの普及で、インターネット広告が広く行われるようになりました。最近は、SNSを活用した広告も増えています。
こんな広告を見かけることもありますが、NGです。
・キャンペーン! 8月1日まで初診料はタダ |
どこがNGなのか、分かりますか?
もし、はっきりと「ここがNG。理由は・・・」と言えない方は、この記事を読んでいただき、医療広告ルールのポイントをしっかりと理解するのがおすすめです。
ここでは、病院・クリニックの広告ルールのポイントを、分かりやすく解説します。
2 病院・クリニックの広告ルールの概要
⑴ 広告ルールのきほん
病院やクリニックの広告は「医療広告」といわれます。つまり、「お医者さん、歯医者さんの広告」のことです。一方で、「薬や化粧品の広告」のことは「薬機広告」といい、ルールも別です。まずはここをしっかり区別しましょう。
・病院やクリニックの広告 = 医療広告 |
また、ありとあらゆる広告は、「景品表示法」(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」)という法律のルールを守る必要がありますが、医療広告や薬機広告には、さらに厳しく特別なルールがあります。
つまり、
・普通の広告のルール = 景品表示法 |
こんな感じに、景品表示法にプラスアルファでルールが追加される、ということです。
景品表示法のルールはとてもシンプルです。基本的なこと=商品やサービスの内容、価格などで嘘や大げさなをことを表示しない、ということを守っていれば、違反を防ぐことができるのがほとんどです。
しかし、プラスアルファのほうは、より複雑なルールになっているので、知らないと違反になってしまいます。
・景品表示法 = シンプルで基本的なルール |
そこで、次に、医療広告のプラスアルファを説明します。
⑵ 医療広告ルールの全体イメージ
「医療広告」は、医療法という、お医者さんのための法律が、プラスアルファの特別なルールを定めています。
見たことがない方も多いと思いますので、一度、医療法の第6条の5を見てみましょう(あとで分かりやすく説明しますので、ぱっと見で大丈夫です)。
第6条の5 |
法律なので、文字で書かれているのはもちろんですが、間違いのないように厳密に書いてあるので、とても読みにくいです。
なので、これを分かりやすく、また厚生労働省令の内容も追加して整理すると、以下のようになります。
1 嘘の広告は禁止 |
これでも、ずらっと列挙されていて読みにくい、と感じると思いますが、要するに、医療広告は、
・原則として、列挙された事項しか広告できない(上記表の3) |
ということです。
ただ、これだけで正しく理解するのは大変なので、広告の参考のために分かりやすく解説したものが、「医療広告ガイドライン」です。
⑶ 「限定解除」
医療広告では、重要なポイントがもうひとつあります。「限定解除」と呼ばれるものです。
上で見たように、医療広告では広告できる事項が限られています(限定されている)。この「限定されている」ことを、条件を守ることで「解除」する=「広告できるようになる」ことを、「限定解除」といいます。
「限定解除」というワードがわかりにくいのですが、
・条件を満たせば、広告できる事項が増える |
と理解すれば十分です。
以下では、医療広告ガイドラインのポイントを解説します。
・医療広告ガイドライン 厚生労働省
・医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) 同
◎関連する情報 |
3 「広告」になるのはどんなとき?
最初に、広告ルールを守らなければならない場合を確認しましょう。
広告ルールは、作成して配布したり、公開するもの(表示するもの)が「広告」になるときに適用されます。
では、どんな場合に「広告」になるのでしょうか?
⑴ 「広告」の2要件
医療広告ガイドラインによると、表示するものが、次の2つのどちらにも当てはまると「広告」になります。
❶ 患者に受診などをしてもらおうと誘引する意図があること(誘引性) |
❶は、病院・クリニックに来てもらおうとして表示をする場合のことです。お客さんを増やそうとして表示をすれば、これには当てはまります。
❷は、医師・歯科医師の名前や病院・クリニックの名称が表示されていることです。
そして、ここで、広告ルールに詳しい人なら、「なぜ2要件なのか?」と思います。ふつう、広告になるのは、上の2つに、
➌ 一般人が認知できる状態にあること(認知性)
という3つ目の要件を加えた3要件になるのがごくごく一般的だからです。
現在の医療広告ガイドラインでは、このことには触れられていませんが、従来、認知性がないとして規制の対象になっていなかったホームページにもルールを適用させようという意図があるように思われます。
もっとも、つい最近改正された獣医療ガイドラインでは、認知性が無いものとして、動物病院のホームページが例として挙げられています。つまり、一般人のほうからインターネットで検索しないと表示されないので、ホームページだけでは広告にならない、とされているのです。
しかし、医療広告ガイドラインでは、最近の改正でも2要件のままとされ、ホームページも除外されていませんので、特定性がないから広告にならない、と考えないほうがいいでしょう。
ただ、これを見ただけではイメージが付きにくく、「広告」になるケースはたくさんあります。医療広告ガイドラインには、「広告」にならないケースが具体例として書かれています。
「広告」にならない場合がわかれば、「それ以外は「広告」になる」とわかるので、以下では、この「広告にならないケース」をみながら、❶と❷の要件がどのように判断されるのかみてみましょう。
⑵ 「広告」にならないケース
① 学術論文、学術発表など
論文や学会での発表は、執筆した獣医師の名前や動物病院の名称が記載されることもありますが、飼育者などを来院させるためではなく、研究成果を発表するために執筆されます。そのため、❶の誘因性がありません。
② 新聞や雑誌などの記事
新聞や雑誌の記事は、獣医の名前や動物病院の名称は表示されています。そのため、❷の特定性はあります。
しかし、新聞広告や雑誌広告とは異なり、記事は、新聞社や出版社が企画して、医師などにインタビューして執筆されます。そのため、患者を来院させるために執筆されるものではないので、❶の誘因性がありません。そのため、「広告」にはなりません。
ただ、「記事」っぽい見た目でも、出版社に掲載費を支払って掲載を依頼する場合(いわゆる「記事広告」の場合)は、患者を来院させるために表示されたものになるので、この場合は❶の誘因性もあることになり、「広告」になります。
③ 患者などが自分で掲載する体験談(口コミ)
クチコミサイトや、Googleマップの口コミ欄などに、飼育者が自分から投稿することがあります。この場合も、動物病院や獣医が関与していなければ、❶の誘因性がないので広告にはなりません。
ただ、病院のほうから頼んで投稿してもらったり(いわゆる「サクラ」)すると、❶の誘因性があるので「広告」になります。「記事っぽいもの」と同じ構図です。
④ 病院内の掲示、施設内で配布するパンフレット
病院で行っている治療法を記載したポスターを病院の壁に貼る、または記載したパンフレットを院内に置く場合は来院した飼育者しか見られないので「認知性」が無いと思われますが、医療広告ガイドラインでは、受診している患者しか見られないので、❶の誘因性がないとされています。そのため、このケースも「広告」にはなりません。
しかし、同じポスターを路上の掲示板に貼れば「広告」になりますし、同じパンフレットを路上で配ればやはり「広告」になります。
なお、希望した人にだけ配信する電子メールは、医療広告ガイドラインでは除外されていますので、「広告」になる可能性があります。
⑤ 職員募集の広告
病院の職員募集する広告は、患者に向けられたものではないので、❶の誘因性がないとされています。そのため、このケースも「広告」にはなりません。
⑶ 病院のホームページや医師個人のSNS
上でも触れましたが、獣医療ガイドラインでは、動物病院のホームページは、飼育者等が検索をしないと表示されないので「認知性」がなく、通常は「広告」にならないとされていますし、SNS(LINEのようなメッセージアプリ系)の場合は、友達登録をしないとメッセージが届かないので、ホームページと同じく「認知性」がないとされます。
しかし、医療広告ガイドラインでは、「認知性」が広告に該当するかどうかの条件になっておらず、ホームページやSNSも例外として挙げられていませんので、「広告」になるという前提で対応することが必要です。
⑷ まとめ
表示をするときには、ふつう、病院・クリニックや医師・歯科医師の名前も記載します。なので、❷の特定性が無いケースはあまり無いでしょう。
また、動物病院や獣医師が、積極的に表示をするときは、ふつう、より多くの人に情報を伝えようと考えるはずですし、たくさんの人に病院に来てもらおうという気持ちがあるので、❶の誘因性が無いケースも少ないです。
そのため、「広告」になるかならないかは、他の広告でも➌の認知性が問題になることがほとんどですが、医療広告ガイドラインでは、認知性は条件にならないので、表示をするときは、「広告に当たる可能性がある」と考えて、きちんと広告ルールを守った表示にしておくことが安全です。
ケースごとに「広告」になるのかどうかの判断で迷うときは、ご相談ください。
4 病院の広告でできること
やろうとしていることが「広告」になる場合は、医療広告ガイドラインのルールを守ることが必要です。
まず、ポイントの1番目、病院・クリニックの広告では、広告できる内容が決められていることを理解しましょう。
ここでは、特にポイントになるものを説明します。
⑴ 業務の技能・療法・経歴以外のことは自由に広告できる
まず、病院・クリニックの業務や治療、医師・歯科医師の経歴とは関係のないこと、つまり、診察や治療、病気の予防とその治療法、また、医師・歯科医師の経歴に関すること以外は、自由に広告ができます。
⑵ 広告してよいとされる事項は広告できる
次に、以下の事項は広告できます。
列挙されていますが、要は、患者の主観的な判断で変わらない、あくまで客観的な情報です。
① 医師/歯科医師であること |
ただし、細かなルールが多いので、上の事項を広告するときも、医療広告ガイドラインのルールをよく確認しましょう。
繰り返しになりますが、上の事項には、具体的な診療内容や結果が含まれていないことに注意してください。
⑶ 自由診療の内容は一定事項を併記すれば広告できる
自由診療の内容、医師・歯科医師の技能や治療法は、限定解除により広告できます。
つまり、上の事項とは異なり、広告するためには一定の条件を守ることが必要になります。
この「条件」というのは、広告媒体が限られていること、広告と一緒に一定の事項を正しく記載すること(「併記」すること)です。この記載をしないと、違法な広告になりますので、以下の事項を正確に記載するようにしましょう。
まず、広告媒体から見てみましょう。
広告媒体 |
① ウェブサイト(ホームページなど) |
ここでの注意点は、これらは病院、医師などが自ら発信する情報であって、第三者に依頼する広告ではないということです。そのため、バナー広告、リスティング広告は認められていませんし、インフルエンサーなどによるSNSも認められていません。
次に、併記が必要な事項です。
併記が必要な事項 | 併記が必要な事項 |
|---|---|
① 問い合わせ先 | 診療施設の連絡先(診療時間外の連絡先も必要) |
② 通常必要となる診療の内容 | 診療内容、診療期間・回数 |
③ 診療に係る主なリスク、副作用など | ※長所だけでなく副作用やリスクを分かりやすく表示 |
④ 費用 | 診療内容にとって通常必要となる標準的な費用 ※金額が不明確なときは、最低金額~最高金額までの範囲 |
この一緒に併記する事項で注意が必要なのは、③のリスク、副作用と④の費用です。
③のリスクは、あらゆるリスクを書かなければいけないわけではなく、主なリスクや副作用です。詳細な説明まで必要ありませんが、広告を見る人が理解できるように、記載しなければいけません。
④の費用も、標準的な費用なので、一般的な金額を記載すれば大丈夫ですが、範囲の場合は、最低額と最高額を記載します。
この記載を正しくしないと、違法広告になってしまいます。
正しく記載できているかどうか不安な方は、専門家に相談しましょう。
5 やってはいけない広告
広告ルールのもう一つのポイントが、禁止されている広告をしないことです。
⑴ 虚偽の広告
当たり前ですが、広告で嘘をついてはいけません。嘘の広告は「虚偽広告」とされ、絶対に禁止です。ただ、注意が必要なのは、嘘をつくつもりがなかったのに、虚偽広告になってしまうというケースです。
⑵ 比較広告はしないこと
他の病院・クリニックや医師・歯科医師と比較して、自分のほうが優れているとする広告を、「比較優良広告」といいます。
この比較優良広告は、それが事実だとしても禁止されています。禁止されるのは「優良広告」なので、「比較広告はいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、広告で比較するというのは、結局、自分のほうが優れている、とアピールするためにします。
そのため、他の病院や医師などのことを挙げると、比較優良広告になるリスクが高いので、比較広告はしない、というのが安全です。
⑶ 診療の内容・効果に関する体験談は広告できない
現在、マーケティングでは、SNSマーケティングが流行っています。いわゆる「口コミ」です。
患者が、自分から口コミ投稿をすることは「広告」ではありませんので禁止されません。しかし、病院や医師らが、患者の体験談を引用することや、患者に依頼して投稿してもらう場合は、「広告」になります。
そして、患者やその家族が、病院や医師などに受診して、治療の内容や効果について体験したこと、たとえば、「この病院で治療を受けて、身体が元気になりました」といった内容を広告することは禁止されています。
結局、治療の内容や効果は、それぞれ患者の症状などで違うので、そのような広告は、誤解を招くためです。
ただ、たとえば「とても清潔な待合室でした」のように、診療の内容や効果とは関係のない体験談は広告できます。
⑷ 費用を強調する広告はできない
広告では当然に記載できる費用に関する広告も、強調することは禁止されます。
強調というのは、
「今なら●円でキャンペーン実施中」
「期間限定でこの治療法を50%オフで提供します」
「●療法に△療法をセットですると、割引になります」
「初診は無料で実施します」
といった、キャンペーンや値引きに関する表現です。
つまり、病院・クリニックの広告では、このようなシンプルなキャンペーンなどの広告もできません。
「強調」と聞くと、フォントが大きかったり、目立つ色を使用したりするようなイメージを持つかもしれませんが、お得な費用を伝えることが、「費用を強調している」ことになります。
違反ケースがとても多いので、特に注意が必要です。
6 ありがちな違反ケース
以上のルールですが、正しく理解していないとうっかり違反してしまうことが多いです。ありがちな違反ケースを見てみましょう。
⑴ 虚偽広告になってしまうケース
✕「絶対に安全な手術なので安心です」 |
⑵ 比較優良広告になってしまうケース
✕「この治療の分野では日本トップクラスの実績があります」 |
✕「芸能人●●さんも絶賛の治療法」 |
⑶ 誇大広告になってしまうケース
✕「東京都知事から認可を受けて運営しているクリニックです」 |
⑷ 治療に関する体験談を広告するケース
✕「●●病を患っていたAさんもこの治療のおかげで元気になったと話しています」 |
⑸ 費用を強調するケース
✕「7月限定、初診無料キャンペーン実施中」 |
7 違反してしまったらどうなる?
医療広告のルールに違反すると、各都道府県が調査をし、一般な場合は、行政指導が行われます。具体的には、その広告の内容の修正や中止をするように求められ、再発防止のための方法の報告を求められます。
ただし、調査に協力しないケースでは、報告をするように命令がなされ、立入調査がなされることもあります。また、指導に従わない場合には、中止命令・是正命令がなされることもあります。
これらに従わないときは、都道府県から刑事告訴がなされ、訴追の結果、犯罪になるリスクもあり、悪質な違法広告のケースでは、病院やクリニックの開設許可の取消や一定期間の閉鎖命令が出されることもありえます。
一度の違反で厳しい処分が下される可能性は高くありませんが、何度も繰り返すと相応のペナルティが課されることになります。
違反広告をしないようにすることが第一ですが、うっかり違反してしまった場合には、指導や指示に従って対応することがもっとも大切です。問題になるような対応をしないためにも、もし、調査が始まった場合には、専門家に相談し、誠実な対応ができるようにすることも有効ですし、再発しないようにするためにも、専門家の協力を検討するのが適切です。
8 ポイントのチェックリスト
最後に、医療広告ルールのポイントを見てみましょう。
以下のチェックリストを使って、違法な広告になっていないかを確認しましょう。
1 作成するものが「広告」になるのかどうかをチェックする |
2 表現している内容が、広告できる事項かどうか、広告できないことを記載していないかどうかを確認する |
3 自由診療の治療内容・効果を広告するときは、 |
4 費用を強調していないことを確認する |
5 他の医療機関よりも優れているような表現になっていないことを確認する |
6 患者の治療に関する体験談が無いことを確認する |
7 大げさな表現になっていないことを最後に確認する |
9 迷ってしまったときは
この記事では、医療広告ガイドラインの全体像やポイントなどをわかりやすく解説しました。
ただ、実際の広告にルールを当てはめても分からないケースはたくさんあります。私は、数多くの医療機関の広告をチェックして、問題のないように修正するなどのアドバイスをしています。
病院やクリニックの広告でお悩みの方や不安がある方は、初回相談は30分無料で受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。