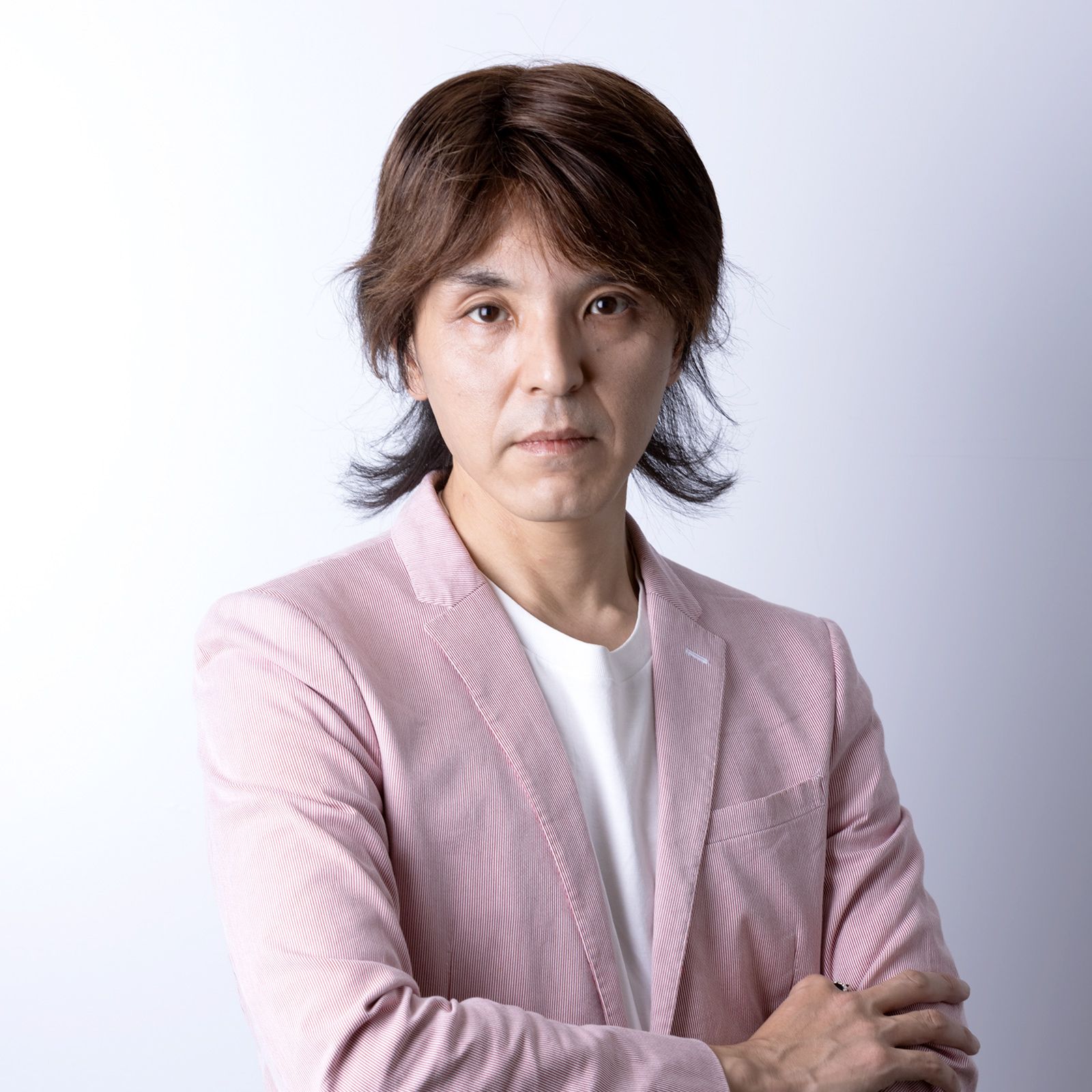執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
こちらでは、本年令和5年(2023年)の重要な法改正のうち、事業に一定の影響のある消費者法に関する内容を解説します。
1 概要
2022年の6月1日に、消費者契約法と消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)という2つの法律に関して、それぞれの一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、1年の期間を経て、本年令和5年6月1日から施行されます。そのため、本稿では、改正法の内容と、改正に合わせて対応が必要になる事項などを解説します。
2 各法律の内容
まず、改正されるそれぞれの法律について、概要を説明します。
⑴ 消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者との間の取引(契約)について、民法によるルール(民事ルール)を、消費者を保護する方向で修正する法律です。
もともと通常の民事ルールは、取引する当事者の双方にとって公平になるようにデザインされています。しかし、大きな組織である会社であったり、取引に慣れている事業者と比べると、一般の消費者はビジネスに関する知識や経験が不足していることが一般的です。そこで、法律は、そのような立場にある消費者を事業者よりも不利な立場に立っているものと考え、その立場を補うためのルールを設けることにしています。このルールを定める法律の一つが消費者契約法になります(労働基準法などの労働法も、同じ考えでデザインされています)。
具体的には、消費者にとって一方的に不利益な契約内容(条項)は無効になったり、消費者が取引を無かったことにできる場合(契約の取り消し)が定められています。
⑵ 消費者裁判手続特例法
消費者裁判手続特例法は、消費者裁判という裁判(民事訴訟)の特別なバージョンを定めたもので、平成28年に制定された比較的新しい法律です。
特定の商品やサービスから消費者被害が生じるような場合、同様の被害が多数の消費者に生じることが一般的です。そのような場合は、適切な消費者団体(特定適格消費者団体)が、多数の消費者を代表して訴訟追行をすることが、集団的な消費者被害の回復を効率的、効果的に行えると考えられることから、特別な手続を定めている法律になります。
この制度の特徴は、手続が2段階に分かれていることにあります。まず、一段階目の訴訟手続において、事業者が消費者に対して共通の責任(義務)を負うかどうかが判断されます。ただし、消費者被害として対象になる損害は財産的損害に限られ、被告も事業者に限定されています。判決のほか、和解をすることも認められていますが、事業者の責任(共通義務)があるかどうかに限られています。そして、判決か和解によって責任が認められると、第二段階の手続となり、そこでは、共通義務に基づき、事業者がどの被害者にいくらを支払うかを確定するものとされています。
つまり、第1段階では消費者団体が訴訟追行をし、第2段階で各消費者が手続に参加するという制度です。
3 今回の改正内容
今年の改正内容は、以下のとおりです。
⑴ 消費者契約法の改正事項
消費者契約法は、上記の説明のとおり、民法の民事ルールの原則よりも、消費者を保護するものですが、今回の改正は、更にその範囲を拡充するものです。
① 契約の取消ができる場合の追加
民法では、契約を取り消すことができる場合は騙されて契約した場合などに限定されていますが、消費者契約法では、様々な場合を追加しています。
そして、今回の改正により、
勧誘することを告げずに、消費者を退去困難な場所へ同行して勧誘した場合消費者を威迫する言動を交えて、相談の連絡を妨害した場合契約前に契約の目的となる物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした場合の3つがあった場合も、契約を取り消すことができることになりました。
今回の改正により、さらに取り消すことができる場合が拡充されますが、いずれも、常識から考えても不当な行為がなされた場合であり、主に不当な業者を念頭に置いたものといえます。
② 無効になる条項の追加
民法の原則では、公序良俗に違反するような場合などに限り、契約書の条項(契約内容)が無効になるとされていますが、消費者契約法は、消費者に一方的に不利益な内容の条項は無効になるとしています。
ところで、消費者契約においては、利用規約などのなかで、事業者の賠償責任を限定する条項が多く見られますが、従来の消費者契約法でも、事業者に故意や重大な過失があるような場合にも免責する条項は無効とされていました。もっとも、今回の改正では、免責の内容が不明確な条項についても無効とされることになりました。つまり、今後は、軽過失の場合に免責されることを明確に定めない限り、条項が無効になることとされました。
③ 事業者の努力義務の拡充
さらに、法的な義務ではないものの、事業者に対して努力を求める事項が追加されました。
この中でも特に注目されるのは、契約を解除する場合について、解除する場合に必要な内容の情報提供や、解約料の算定根拠の概要を説明するように努力することが求められることになります。不合理な解約料を要求することは、もともと不当条項とされますが、今回の改正により、解約料の算定根拠が合理的であることを説明するように努める必要があります。
また、勧誘するときの情報提供としても、相手方になる消費者の年齢や心身の状態を踏まえて行うように努力することが求められます。そのため、例えば、高齢により聴力が衰えた方を勧誘するときは、口頭で伝えるだけでは足りず、紙面でも補足して説明するように努めなければなりません。
さらに、利用規約などの「定型約款」については、民法548条の3第1項により、もともと事業者に対する表示請求権が認められていますが、今回の改正により、事業者には情報提供する努力義務も定められました(定型約款の内容を公開するなど、消費者が容易に知ることができる状態にしていれば、書面によって定型約款を交付する必要はありません)。
⑵ 消費者裁判手続特例法の改正事項
① 改正の背景
上記のように、消費者裁判手続は、社会にとっても有意義な制度として期待されたものでしたが、制限されている事項が多かったことの影響もあり、制定から5年の間で、この制度に基づく訴訟がわずか4件しかありませんでした。
今回の改正は、問題点の改善と環境の整備を通じて、この制度の活用を拡げ、社会に定着させることを目的になされるものです。
② 改正事項
具体的には、今回の改正点は以下のとおりになります。
現行法 | 改正法 | |
対象範囲 | 財産的損害に限定 | 損害に「慰謝料」を追加 |
和解の範囲 | 共通義務のみ | 様々な和解が可能 |
消費者への情報提供 | - | 事業者の消費者に対する個別通知の義務付け |
消費者団体訴訟等支援法人 | - | 特定適格消費者団体を支援する法人の認定制度を導入 |
特定適格消費者団体の負担軽減など | - | 二段階目の手続の申立てを柔軟にする |
消費者保護の充実 | - | 消滅時効の特例(完成猶予、更新)の整備 |
上の表のとおり、制度の細かなところまで含めて改正事項が多く、国において、この制度の活用を広げたいという意気込みを感じる内容となっています。
4 事業者に求められる対応事項
⑴ 消費者契約法の改正への対応
上記の改正を受けて、消費者向けの商品/サービスを提供する事業者には以下の対応が求められます。
まず、取消事由については、前述のとおり、社会的に見て不当とされるような行為が今回の改正で追加されたものといえますが、消費者には、十分な情報量や判断力が事業者と比較して不足しているということを改めて認識した上で、自社において、不当な勧誘などになっていないかを改めて検討することが必要になります。
次に、無効事由の追加については、利用規約などの損害賠償範囲を限定する条文の内容を再確認することが必須となります。軽微な過失の場合の損害賠償義務を限定すること自体は、引き続き有効とされていますので、そのことを明確に定める内容になっているかどうかを、早急に確認し、不明確な内容の条項の場合は、速やかに利用規約などの変更を行うことが必要です。
最後に、努力義務の拡充についてですが、努力義務については、法的な義務ではないことから遵守しなくても問題ないと理解される傾向も一部にありますが、法律が特定の行為を努力義務として定めるのは、努力義務に違反することが別の法的義務の違反に繋がることが多いためであり、また、法的義務として定めるまでの事実上の移行期間とされることも多いものです。
そのため、将来的に法的義務とされる場合に備えて、現時点から遵守することが望ましいだけでなく、努力義務を遵守することは、別の法的義務に違反することを防止することに繋がるものとして、積極的に遵守すべきものと考えます。特に、今回の改正の注目点でもある解約料の算定根拠については、現状の解約料が合理的なものとなっているかどうか(裏返せば、合理的なものでなく、平均的な損害を超える場合は、現行法においても無効になります)を再確認する機会にもなりますので、改めて検討した上で、解約を求める消費者に対しても、合理的なものであることをきちんと説明し、解約トラブルを防止するための対応をすることが適切なものと思われます。
⑵ 消費者裁判手続特例法の改正への対応
消費者向けの商品/サービスを提供する事業者に与える影響として、1番目に挙げられるのは、制度が利用しやすいものに変わることから、本制度に基づく訴訟提起をされる可能性が高まることにあります。この法律は民事訴訟法の特例であり、本質は通常の民事訴訟と変わるところがないものの、手続などが大きく異なっており、この手続に従った訴訟対応が必要になります。
2番目の影響としては、損害の範囲が拡大されたこと、具体的には、財産的損害に加え、慰謝料が認められるようになったことです。もっとも、この点は、本制度以外の訴訟手続では当然に請求が認められていたものであり、むしろ現行法の制限により本制度の利用がなされていなかったことを踏まえれば、大きな違いとは言えないとも考えられます。
また、消費者への情報提供方法の充実に伴い、事業者に求められる対応の範囲が拡大することも大きな影響があります。
いずれにしても、本制度の改正は、消費者向けの事業を行う事業者に対して、今まで以上に消費者被害を生じさせないような事業運営を求めるものといえます。
5 最後に
消費者を対象に商品/サービスの提供をする場合は、消費者法を踏まえた契約書を整備するだけでなく、業務全般において、消費者被害を防止する運用が求められます。消費者保護という方向性に変わりはないものの、その規制内容は複雑化する傾向にあります。
GVA法律事務所では、消費者保護という法律が求める趣旨を踏まえ、事業者向けのサービスを広く提供しておりますので、今回の改正対応を含め、お気軽にご相談ください。