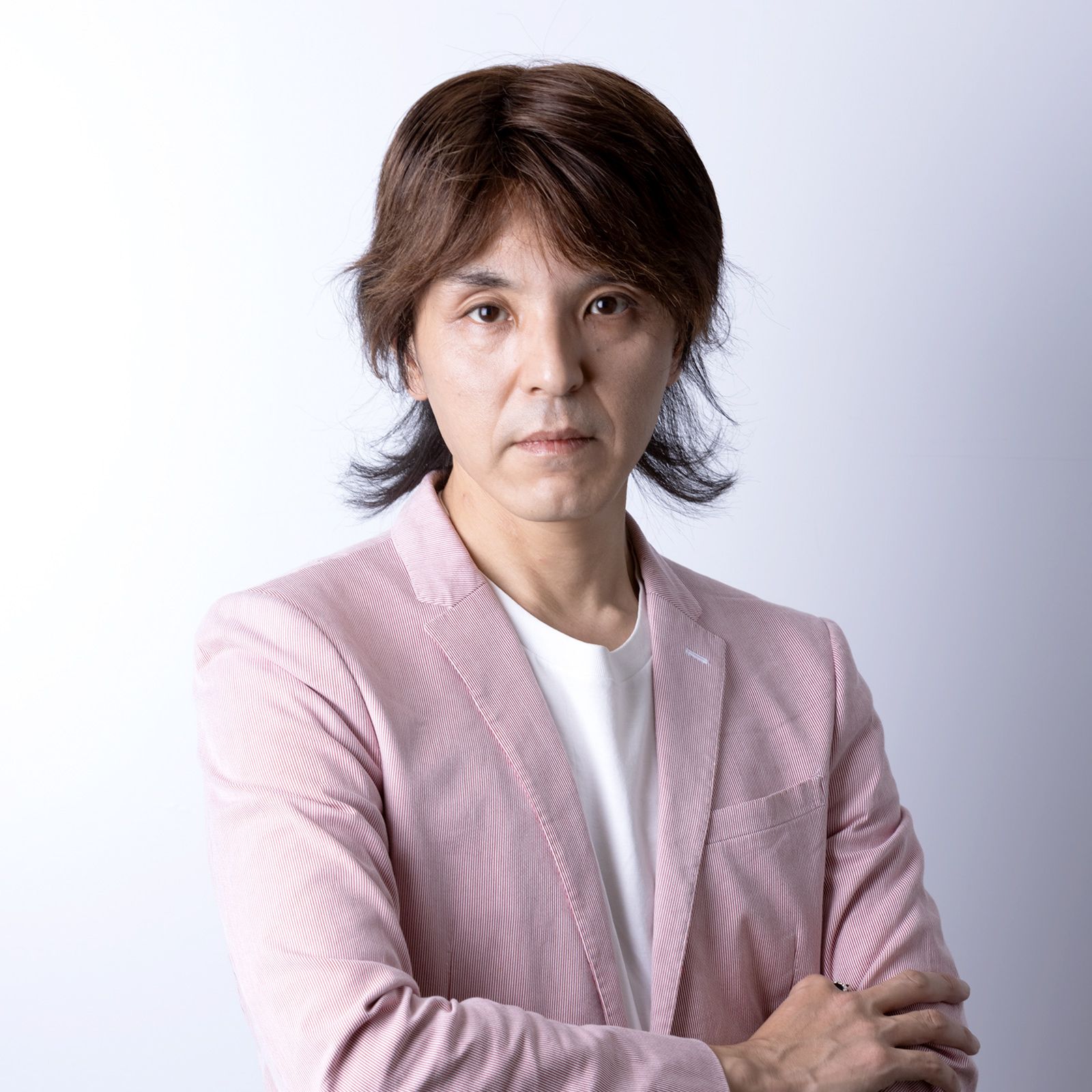執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
1 はじめに
令和6年4月1日から、動物病院の広告ルールが大きく変わりました。
診療内容を広告できるようになったなど、以前よりも広告できる内容が広がり、動物病院の広告がより自由になりました。
この記事では、動物病院の広告ルールのポイントを解説します。
2 動物病院の広告ルールの概要
動物病院に関しては、獣医療法という法律が規制しています。そして、獣医療法の第17条は、動物病院に関する広告ルールを次のように定めています。
(広告の制限)
第十七条 何人も、獣医師(獣医師以外の往診診療者等を含む。第二号を除き、以下この条において同じ。)又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならない。
一 獣医師又は診療施設の専門科名
二 獣医師の学位又は称号
2 前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることができる。
3 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
こちらは少し読みにくいかもしれません。例外的に広告ができるものと、広告の方法などに関する制限は、農林水産省令(=獣医療法施行規則)で定めるとしているので、これを読んだだけでは、何を広告できるのかがわかりません。
施行規則に定められていることも合わせて、分かりやすくすると以下のようになります。
1 獣医師/動物病院については、以下のものだけ広告できる
⑴ 業務の技能・療法・経歴に係わらない事項
⑵ 獣医師/動物病院の専門科名
⑶ 獣医師の学位/称号
⑷ 技能、療法/経歴について獣医療法施行規則で定めるもの
① 獣医師の免許を受けていること、動物病院を開設していること
② 獣医師の専門性に関する認定を受けていること
③ 動物用の医薬品等を用いる検査、手術その他の治療を行うこと
④ 医療機器を所有していること
⑤ 家畜体内受精卵の採取を行うこと
⑥ 犬/猫の生殖を不能にする手術を行うこと
⑦ 予防注射を行うこと ※説明の併記が必要
⑧ 寄生虫病の予防措置を行うこと
⑨ 飼育動物の健康診断を行うこと
⑩ マイクロチップの装着を行うこと ※説明の併記が必要
⑪ 獣医師の役職・略歴に関すること
⑫ 家畜防疫員であること
⑬ 伝染性予防措置を実施する団体から委託を受けていること
⑭ 日本獣医師会などの会員であること
⑮ 指定臨床研修診療施設であること
⑯ 愛玩動物看護師が勤務していること
⑰ 組合等の指定獣医師であること
2 1の③、④、⑥~⑩を広告するときは以下のルールを守ること
⑴ 比較優良広告の禁止
⑵ 誇大広告の禁止
⑶ 問い合わせ先などを併記すること
つまり、動物病院の広告は、
・広告ができる内容が決められている
・比較広告や誇大広告が禁止されている
・一定の事項については問い合わせ先などを合わせて表示しなければならない
ことがポイントになります。
※ 動物ではなく人間向けのふつうの病院・クリニックの広告(いわゆる「医療広告」)にも広告ルールがあります。今回改正された動物病院の広告ルールは、医療広告のルールとかなり共通しています。医療広告のルールに詳しい人なら、パラレルに考えると理解が早いでしょう。
動物病院の広告ルールのポイントは上でみたとおりですが、より詳しい内容は、獣医療広告ガイドラインにまとめられています。
・「獣医療広告ガイドライン」 農林水産省
・「獣医療広告ガイドラインQ&A」 同
以下では、このガイドラインに書かれているルールのなかで、特に大切なところを詳しく説明します。
3 「広告」になる場合
最初に、広告ルールを守らなければならない場合を確認しましょう。
広告ルールは、作成して配布したり、公開するもの(表示するもの)が「広告」になるときに適用されます。
では、どんな場合に「広告」になるのでしょうか?
⑴ 「広告」の3要件
表示するものが、次の3つの全部に当てはまると「広告」になります。
❶ 飼育者などを来院させようと誘引する意図があること(誘引性)
❷ 獣医師の氏名/動物病院の名称が特定可能であること(特定性)
➌ 一般人が認知できる状態にあること(認知性)※この3つの要件は、他の広告に関するルールとも共通します。
❶は、動物病院に来てもらおうとして表示をする場合のことです。お客さんを増やそうとして表示をすれば、これには当てはまります。
❷は、獣医師の名前や動物病院の名称が表示されていることです。
最後の➌は、不特定多数の人に対して表示されていることです。
ただ、これを見ただけではイメージが付きにくいと思いますが、「広告」になるケースはたくさんあるので、ガイドラインには、「広告」になるケースだけでなく、「広告」にならないケースが具体例として書かれています。
この「広告」にならない場合がわかると、それ以外は「広告」になることがわかるので、以下では、この「広告にならないケース」をみながら、❶~➌の要件がどのように判断されるのかを確かめてみましょう。
⑵ 「広告」にならないケース
① 論文、学会発表
論文や学会での発表は、執筆した獣医師の名前や動物病院の名称が記載されることもありますが、飼育者などを来院させるためではなく、研究成果を発表するために執筆されます。そのため、❶の誘因性がありません。
また、不特定多数の人向けに公開されるわけではなく、論文にアクセスするためには、学会誌の購入や、研究が集められているサイトにアクセスすることが必要になります。そのため,➌の認知性もないと考えられます。
② 新聞や雑誌の記事
新聞や雑誌の記事は、獣医の名前や動物病院の名称は表示されていますし、マスメディアとして、不特定多数の人に向けて公開されています。そのため、❷の特定性、➌の認知性はあります。
しかし、新聞広告や雑誌広告とは異なり、記事は、新聞社や出版社が企画し、獣医などにインタビューすることで執筆されます。そのため、飼育者等を来院させるために執筆されるものではないので、❶の誘因性がありません。そのため、「広告」にはなりません。
ただ、「記事」っぽい見た目でも、出版社に掲載費を支払って掲載を依頼する場合は、飼育者等を来院させるために表示されたものになるので、この場合は❶の誘因性もあることになり、「広告」になります。
③ 飼育者などが自分で掲載する体験談(口コミ)
クチコミサイトや、Googleマップの口コミ欄などに、飼育者が自分から投稿することがあります。この場合も、動物病院や獣医が関与していなければ、❶の誘因性がないので広告にはなりません。
ただ、動物病院のほうから頼んで投稿してもらったり(いわゆる「サクラ」)すると、❶の誘因性があるので「広告」になります。「記事っぽいもの」と同じ構図ですね。
④ 病院内の掲示、施設内で配布するパンフレット、送付する電子メール
動物病院で行っている治療法を記載したポスターを病院の壁に貼る、または記載したパンフレットを院内に置く場合、希望を受けて送信する電子メールは、来院した飼育者やメールの送信先しか見られないので、➌の「認知性」がありません。そのため、このケースも「広告」にはなりません。
しかし、同じポスターを路上の掲示板に貼れば「広告」になりますし、同じパンフレットを路上で配ればやはり「広告」になります。電子メールも、希望を受けていないのに送信すると、やはり「広告」になります。いずれも➌の「認知性」があるとされるためです。
⑤ 動物病院のホームページ
動物病院のホームページは、通常は「広告」にならないとされています。その理由は、飼育者等が検索をしないと表示されないので、➌の認知性がないためです。動物病院側から誘っているのではなく、飼育者等の検索が先立っているということです。
逆に、飼育者等が検索をしなくても表示がされる場合、例えば、リスティング広告やバナー広告、「広告」になるチラシやパンフレットのQRコードから遷移するような場合は、たとえホームページだけでは「広告」にならない場合でも、リスティング広告などとセットになって、ホームページもまとめて「広告」になります。
⑥ 獣医師が個人で開設するブログ、SNS
ブログは検索が必要なので、ホームページと同様に原則として「広告」になりません。SNSの場合、LINEのようなメッセージアプリ系の場合は、友達登録をしないとメッセージが届かないので、ホームページと同じく➌の認知性がないとされます。しかし、Xやインスタグラムのような交流系SNSの場合は、情報がどんどん拡散されていく性質があるので、➌の認知性があり、「広告」になるとされています。
このように同じ「SNS」と呼ばれるものでも、どんな機能なのかで変わってくるので、注意が必要です。
⑶ まとめ
表示をするときには、ふつう動物病院や獣医師の名前も記載します。なので、❷の特定性が無いケースはあまり無いでしょう。
また、動物病院や獣医師が、積極的に表示をするときは、ふつう、より多くの人に情報を伝えようと考えるはずですし、たくさんの人に病院に来てもらおうという気持ちがあるので、❶の誘因性が無いケースも少ないです。
そのため、「広告」になるかならないかは、➌の認知性が問題になることがほとんどです。この判断は複雑なので、上で紹介した「広告にならないケース」に当てはまる場合以外のケースでは、➌の認知性があることがほとんどだと思います。
そのため、表示をするときは、「広告に当たる可能性がある」と考えて、きちんと広告ルールを守った表示にしておくことが安全です。
ケースごとに「広告」になるのかどうかの判断で迷うときは、ご相談ください。
4 広告ができる事項
「広告」になる場合は、ルールに沿った広告にしなければいけません。
まず、ポイントの1番目、動物病院の広告では、広告できる内容が決められていることを理解しましょう。
ここでは、特にポイントになるものを説明します。
⑴ 業務の技能・療法・経歴以外のことは自由に広告できる
まず、動物病院の業務や治療、獣医師の経歴とは関係のないこと、つまり、動物の診察や治療、病気の予防とその治療法、また、獣医の経歴に関すること以外は、自由に広告ができます。
⑵ 診療内容は一定事項を併記すれば広告できる
これまでのルールでは、診療内容はほぼ広告できないとされていました。
しかし、今回の改正により、診療内容、獣医の技能や治療法を広告できるようになりました。
ただし、治療法などに合わせて、最初のポイントであげた一定の事項を正しく記載することが必要です。この記載をしないと、違法な広告になりますので、以下の事項を正確に記載するようにしましょう。
<併記が必要な事項>
①問い合わせ先 | 診療施設の連絡先(診療時間外の連絡先も必要) |
②通常必要となる診療の内容 | 診療内容、診療期間・回数 ※長所だけでなく副作用やリスクを分かりやすく表示 |
③診療に係る主なリスク、副作用など | ※長所だけでなく副作用やリスクを分かりやすく表示 |
④費用 | 診療内容にとって通常必要となる標準的な費用 ※金額が不明確なときは、最低金額~最高金額までの範囲 |
この一緒に併記する事項で注意が必要なのは、⑶のリスク、副作用と⑷の費用です。
③のリスクは、あらゆるリスクを書かなければいけないわけではなく、主なリスクや副作用です。詳細な説明まで必要ありませんが、広告を見る人が理解できるように、記載しなければいけません。
④の費用も、標準的な費用なので、一般的な金額を記載すれば大丈夫ですが、範囲の場合は、最低額と最高額を記載します。
同じような記載が求められている医療広告では、リスクや費用の記載がないために指摘されているケースが多いです。動物病院の広告も同じルールなので、特に注意しましょう。
正しく記載できているかどうか不安な方は、専門家に相談しましょう。
5 禁止される広告
広告ルールのもう一つのポイントが、禁止されている広告をしないことです。
⑴ 比較広告はしないこと
他の病院や獣医師と比較して、自分のほうが優れているとする広告を、「比較優良広告」といいます。
この比較優良広告は、それが事実だとしても禁止されています。禁止されるのは「優良広告」なので、「比較広告はいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、広告で比較するというのは、結局、自分のほうが優れている、とアピールするためにします。
そのため、他の病院や獣医師のことを挙げると、比較優良広告になるリスクが高いので、比較広告はしない、というのが安全です。
⑵ 診療の内容・効果に関する体験談は広告できない
現在、マーケティングでは、SNSマーケティングが流行っています。いわゆる「口コミ」です。
動物の飼い主が、自分から口コミ投稿をすることは「広告」ではありませんので禁止されません。しかし、動物病院や獣医師が、飼い主の体験談を引用することや、飼い主に依頼して投稿してもらう場合は、「広告」になります。
そして、飼い主やその家族が、動物病院や獣医師に受診して、治療の内容や効果について体験したこと、たとえば、「この病院で治療を受けて、ペットが元気になりました」といった内容を広告することは禁止されています。
結局、治療の内容や効果は、それぞれ動物の症状などで違うので、そのような広告は、誤解を招くためです。
ただ、たとえば「とても清潔な待合室でした」のように、診療の内容や効果とは関係のない体験談は広告できます。
⑶ 費用を強調する広告はできない
従来は、費用に関する広告はできないとされていましたが、今回の改正により、治療法などの広告では、逆に記載しなければいけないことになりました。
しかし、この費用を強調することは禁止されます。
強調というのは、
「今なら●円でキャンペーン実施中」
「期間限定でこの治療法を50%オフで提供します」
「●療法に△療法をセットですると、割引になります」
「初診は無料で実施します」
といった、キャンペーンや値引きに関する表現です。
つまり、動物病院の広告では、このようなシンプルなキャンペーンなどの広告もできません。
「強調」と聞くと、フォントが大きかったり、目立つ色を使用したりするようなイメージを持つかもしれませんが、動物病院の広告では、お得な費用を伝えることが、「費用を強調している」ことになります。
違反ケースがとても多いので、特に注意が必要です。
6 要注意のポイントまとめ
上で説明した注意が必要なポイントをまとめると以下のとおりです。
⑴ 治療法などを広告するときは併記事項を忘れないようにする
⑵ 他の病院や獣医師と比較しない
⑶ 診療の内容や効果の体験談は広告には使用しない
⑷ キャンペーンや割引を広告しないこの記事では、ルールのなかでも特に重要なポイントを解説しました。ガイドラインにはより詳細なルールが書かれていますので、動物病院の広告ルールでお悩みの方や不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。