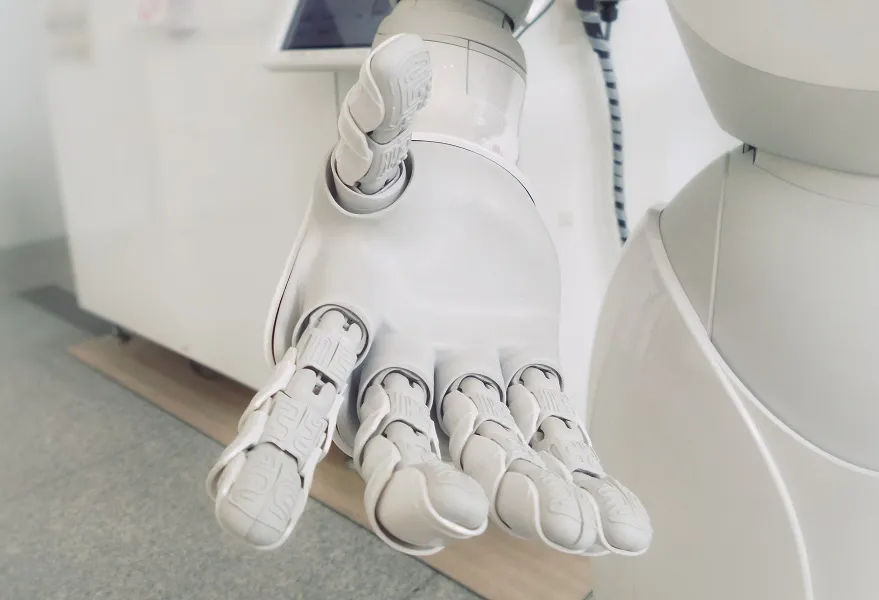執筆:弁護士 石川 泰輝(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
1.はじめに
GVA法律事務所では、メディカル、美容、へルスケア領域に関して専門チームを設け、各分野について、多様なサポートをさせていただいております。
本稿では、「介護関連ビジネスと法」に関する連載の第1弾として、介護ロボットの福祉用具該当性、つまり、介護ロボットが介護保険法の「福祉用具」に該当するかどうかについて解説をします。
2.背景としての「2025年問題」
皆様も「2025年問題」という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、2025年問題とは、2025年度以降に社会全体での労働人口不足が予想されていることをいいます。
2025年に65歳以上の高齢者数が3567万人(全人口に対して30.3%)、75歳以上は2179万人(全人口に対して18.1%)となると予測されています。これに対し、現役世代である労働人口は減少する一方であるため、結果的に、社会全体で深刻な労働人口不足になることが予想されています。
(参照:厚生労働省 今後の高齢者人口の見通しについて )
このため、本稿では、まず2025年問題の中でも特に人材不足が深刻な介護業界についてご紹介させていただきます。
厚生労働省が平成27年6月24日に報告した「2025年に向けた介護人材に係る需給推計(確定値)について」では
<2025年に向けた介護人材に係る需給推計(確定値)>
介護人材の需要見込み(2025年度) 253.0万人
現状推移シナリオによる介護人材の供給見込み(2025年度) 215.2万人
需給ギャップ 37.7万人
となっており、約38万人の介護人材不足が見込まれており、深刻な社会課題となっております。
また、要介護高齢者が増加するにもかかわらず、介護人材が不足することにより、人員配置規制等から、介護施設や介護事業所等の不足も深刻な社会課題になっております。
このような状況のなか、これらの社会問題を解決する一つの手段として注目を集めているものが介護ロボットの導入になります。
3.介護業界の市場規模
日本の高齢者人口・割合の増加に伴って、介護や支援を必要とする人口が年々増加していることもあり、介護業界の市場規模は拡大する見込みとなっております。2014年度における市場規模は8.6兆円でしたが、2025年には18.7兆円と、約10年間で倍以上の額になる見通しです。そして、高齢者人口・割合の増加が落ち着く2040年までは、この増加傾向が続いていくと予想されております。
このように市場規模が拡大しているため、社会的にもビジネスチャンスは大きいと予想されますが、その中でも業務効率化を図る目的の介護ロボットの導入・開発には大きな可能性があるとされております。
なお、介護ビジネスが、国の財源である介護保険料に依拠しており、国の社会保障制度を維持するためにも、今後は介護事業者が介護保険料以外のマネタイズも検討するべきという議論は本件では割愛させていただきます。
4.介護ロボットとは
そこで、介護ロボットについてご説明をしていきます。
まず、介護ロボット自体については、法律上の定義は現時点ではございません。
一方で、厚生労働省が定義を定めており、これによると、介護ロボットは、以下の(1)ロボット性と(2)介護機能性の2点で判断されます。
(1) ロボット性
以下の3つの要素技術を有する、知能化した機械システムであること
情報を感知(センサー系)
判断し(知能・制御系)
動作する(駆動系)
(2) 介護機能性
ロボット技術が応用され利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に役立つ介護機器であること
要するには、介護ロボットとは、介護に資する機能を有する知能化した機械システムのことだといえます。
この介護ロボットの開発には、多くの資金が必要になりますが、国も、そのような開発を支援するべく、開発費用の援助制度を設けております。
具体的には、厚生労働省と経済産業省は、「ロボット技術の介護利用における重点分野」を6分野13項目定め、その開発導入を支援しています。
この内容は以下のとおりになります。
(1) 移乗介助
・ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器
・ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機器
(2) 移動支援
・高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器
・高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援機器
・高齢者等の外出等をサポートし、転倒予防や歩行等を補助するロボット技術を用いた装着型の移動支援機器
(3) 排泄支援
・排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ
・ロボット技術を用いて排泄を予測し、的確なタイミングでトイレへ誘導する機器
・ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援する機器
(4) 見守り・コミュニケーション
・介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム
・在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム
・高齢者等とのコミュニケーションにロボット技術を用いた生活支援機器
(5) 入浴支援
・ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器
(6) 介護業務支援
・ロボット技術を用いて、見守り、移動支援、排泄支援をはじめとする介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等の必要な支援に活用することを可能とする機器
詳細に定められていますが、⑴~⑸が、実際に利用者への介護を行うものであり、⑹が介護業務自体をサポートするものとなります。この6分野13項目のいずれかに該当すれば、一般的には介護ロボットに該当すると判断され、国や地方自治体が定める各種の要件を満たすことで、開発費用の一部の補助金を受けることができます。
5.福祉用具該当性(介護保険法8条12項)
(1) 既存の福祉用具該当性
このように、介護ロボットの開発にあたって、国や地方自治体から補助金を受給し、開発を受けることができますが、仮に開発費用の援助を受けることができたとしても、介護ロボットを実際にエンドユーザーに利用していただけないと意味がありません。
そして、一般的に介護ロボットは高額であることから、エンドユーザーが費用を全額自己負担で利用することは期待できません。
この点、国は、開発費用の援助に加え、介護ロボットについても従来の介護機器と同様に介護保険の適用対象になるものとしています。
具体的には、
介護保険法第8条第12項に定める「福祉用具」に該当させることにより、介護保険の適用を受けることができます。逆に言えば、製造メーカーは、エンドユーザーが利用するにあたって、介護保険の適用を受けられるように、商品を開発する必要があります。
ここで、介護保険法において、「福祉用具」がどのように定義されているのかを見てみましょう。
介護保険法第8条第12項
12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
つまり、
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具
あるいは、
要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの
のいずれかとされています。
なお、この「福祉用具」に該当するかの判断は、保険者である市町村によって個別に判断されるものとされています(介護保険法第41条・第44条)が、福祉用具の対象種目は下記の図のように定められております。
■対象種目
【福祉用具貸与】〈原則〉
・車いす(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置
【特定福祉用具販売】〈例外〉
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部
・排泄予測支援機器(新設)
・入浴補助具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
参照
・厚生労働省ウェブサイト「介護保険における福祉用具」
・令和4年3月31日付 厚生労働省老健局高齢者支援課「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について
上記の種目ごとの仕様は、「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」(平成11年3月31日)で定められています。
そのため、上記の図のいずれかに該当し、厚生労働省の通達(厚生労働省老健局高齢支援課「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について(平成28年4月14日))の詳細な要件を満たすことで福祉用具に該当すると判断されやすくなります。
そして、直近のニュースになりますが、令和4年3月31日付の厚生労働省老健局高齢者支援課「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正により、令和4年4月1日より「排泄予測支援機器」が福祉用具の対象種目に追加され、トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社の「DFree HomeCare」が「排泄予測支援機器」に該当するとされました。
(2) 新しい福祉用具の開発
新しく開発する介護ロボットが既存の福祉用具に該当しない場合には、原則として、介護保険給付の対象とはなりません。そして、上記のように介護ロボットのほとんどは、未だに福祉用具の種目には定められておりません。
もっとも、国は、保険給付の対象とすることの要望を受け付けており、新しく福祉用具に該当するように厚生労働省に「介護保険給付対象化要望調査票」を提出することができます。
調査票では、その福祉用具が、①新規種目・種類(現行の告示種目に合致しない場合)、②拡充・変更(告示種目には合致するが、解釈通知上合致しない場合)、③その他(複合機能を有する、介護保険の対象外の種目が含まれているため保険対象とならない等)のいずれに該当するかを示し、かつ、4で記載した介護ロボットか否かを記載します。
上記の調査票を踏まえ、介護福祉用具・住宅改修検討会では、後述の「介護保険制度における福祉用具の適用の考え方」の各要素を踏まえ、介護保険の給付対象となる種目・種類の追加や拡充を議論します。
前述のとおり、直近で福祉用具の対象種目に追加された「排泄予測支援機器」は①に該当するとして追加が認められました。
介護ロボット自体は、開発費用を援助するなど、国もメーカーによる素晴らしい製品の開発を支援しているものであり、社会課題の解決に資するという意味でも、大きな期待を寄せているものといえます。
そのため、今後は、保険適用の対象製品として、介護ロボットが広く認められていくことが予測されます。
なお、介護福祉用具・住宅改修検討会での議論の内容が気になる方はこちら( https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_173590.html )をご覧になってみてください。
【介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方】
1 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
2 要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
3 治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
4 在宅で使用するもの
5 起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの
6 ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
7 取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
6.おわりに
介護ロボットと法律の関係について最新の動向を含め、簡単にご説明をさせていただきました。
日本の介護業界が抱える問題は深刻であり、その中でも介護人材の不足はその最たるものの一つです。介護現場への介護ロボットの導入は、介護を担う方々にとって良い影響を及ぼすものであり、執筆者としてもそうであって欲しいと強く思っております。
保険適用の対象化製品の拡大など、新たに切り開いていくべき世界でもありますが、GVA法律事務所では最新の介護業界の情報に基づき、事業者の方々の挑戦をサポートさせていただいておりますので、ご質問等についてもお気軽にお問合せください。
厚生労働省 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 第2回
排泄予測支援機器の種目追加に伴う取組について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000904811.pdf
厚生労働省 介護保険における福祉用具・住宅改修の種目・種類等に係る提案票記載要領
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000960527.pdf
監修
弁護士 早崎 智久
(スタートアップの創業時からIPO以降までの全般のサポート、大手企業の新規事業のアドバイスまでの幅広い分野で、これまでに多数の対応経験。 特に、GVA法律事務所において、医療・美容・ヘルスケアチームのリーダーとして、レギュレーションを踏まえた新規ビジネスのデザイン、景表法・薬機法・健康増進法などの各種広告規制への対応、医療情報に関する体制の整備などが専門。)