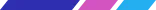書面の必要性
タイでも、日本と同様、契約は申込みと承諾により成立します。そして、一部の契約を除き、契約は(書面がなくとも)口頭の合意のみで成立することとされています。
しかしながら、口頭の合意だけでは、契約の成否・権利義務の具体的内容などについて争いが生じかねません。したがって、日本国内での契約と同様、必ず契約書を作成して合意内容を書面化しておくことが大切です。
なお、タイの民商法(以下、「CCC」といいます。)において、書面での合意が法的に要求されている契約の一例は、以下のとおりです。これらについては、口頭の合意のみでは効力が生じませんので(あるいは、訴訟等で権利行使できないこととなりますので)、注意しておきましょう。
- 不動産売買契約(CCC456条1項。なお、登記も必要。)
- 不動産の賃貸借契約(CCC538条)
- 保証契約(CCC680条2項)
- 和解契約(CCC851条)
- 株式譲渡契約(CCC1129条2項)
なお、タイでも、契約書を作成せず、見積書や発注書のやり取りだけで取引を進めることが珍しくありません。
しかしながら、一般的に見積書や発注書には契約条件が記載されておらず、又は、記載されていても一部の条件が片面的に記載されているにとどまります。そのため、単発的に少額の取引をするような場合はさておき、継続的な取引が見込まれる場合には取引基本契約書を作成し、今後の取引全体をカバーするかたちで取引の条件や権利義務の内容を明確化しておくべきです。また、単発であっても大型又は重要な取引をする場合には、見積書や発注書だけで済ませず、契約書を作成して取引の条件や権利義務の内容を明確化しておく方が望ましいです。
契約書の内容
契約書の内容として記載すべき事項は、後述するいくつかの事項を除き、日本国内での取引に関する契約書と同様です。
つまり、日本での国内取引に関する契約書を作成したりレビューしたりするときと同じように、将来的にどのような問題が生じる可能性があるか想定しつつ、当事者の権利義務の内容やその発生条件などを明確化し、当事者間での認識の相違や疑義が生じないようにすることが重要なポイントとなります。
この点、タイ企業が契約書(案)を提示する場合、しばしば、条項が少なく不足していたり、逆に条項が沢山あって条項間で内容に矛盾が生じていたりすることがあります。いずれの場合も紛争化したときに問題となりますので契約締結前の修正が必要となるわけですが、その量が多すぎると修正に時間を要したり漏れが生じたりしかねません。そのため、可能な限り、必要な条項を適切に網羅した契約書のテンプレートを自社で準備しておき、取引相手に自社のテンプレートを使うよう求めることができる状態を整えておくべきでしょう。
署名押印
契約書には当事者の署名が必要であり、会社の場合は署名権者の署名が要求されます。
また、タイの会社のほとんどは、社印をDBD(タイ商務省)に登録しており、契約書等には署名のみならず社印を押印することとしています。
したがって、万が一、相手方を代表して署名した者が実は署名権を持っていなかった、又は、社印の押印が必要なのに押印がされていなかった、といった問題を予防するため、契約締結前に、相手方の署名権者や社印の要否について確認しておくことが必要です。
なお、署名権者や社印の要否はAffidavitに記載されていますので、Affidavitを取得するのが簡便な確認方法です。
立会人(証人、Witness)
タイでは、契約書の中に、当事者の署名欄に加えて立会人(証人)の署名欄が設けられていることが珍しくありません。
この立会人の署名は、多くの場合において、当事者が契約書に自らの意思で署名したことを裏付ける(つまり、契約が有効に成立したことを裏付ける)ための実務的な方法であって、法的に要求されているわけではありません。したがって、仮に立会人の署名がなくとも、法的に契約が無効となるわけではありません。
ただし、例えば、株式譲渡契約など、立会人の署名が法的に要求されているものもあります(CCC1129条2項)。このように法的に立会人の署名が要求される場合、立会人の署名がなければ契約が無効となりますので、注意が必要です。
なお、立会人となるための資格は存在せず、第三者が立会人となることも要求されていません。そのため、一般的には、当事者の従業員が立会人として署名するケースが多いように思われます。
また、契約書には立会人2名が署名する場合が多いのですが、各当事者が1名ずつ準備すべきといったルールもありません。したがって、一方当事者のみが2名の立会人を準備することも理屈上は可能です。もっとも、後々、「相手方や相手方が準備した立会人に署名を強制された。」などと言われるリスクもゼロではないので、各当事者が1名ずつ立会人を準備することが基本となるでしょう。
契約書の言語
契約書の言語については、タイ語で作成することが法令上義務づけられているわけではありませんので、英語により作成することも可能です。実際、日系企業が当事者となる場合には英語で契約書を作成することも珍しくありません。
この点、契約書がタイ語など特定の言語で作成されて別の言語にも翻訳される場合、又は、契約書がタイ語と日本語など複数の言語の併記により作成される場合、言語間で内容に齟齬が生じることがあります。そこで、言語間の齟齬が生じた場合にどの言語の規定が優先するかについて契約書上で明記し、当事者の認識を統一しておくことが必要となります。
もし言語の優先関係が明確でない場合、CCCには、「書面が複数の言語で作成され、言語間で矛盾がある場合、言語の優先関係に関する当事者の意図が明らかでない限り、タイ語版が優先する。」との規定が置かれています(CCC14条)。そのため、タイ法の下では、契約書上の記載などから当事者の意図が判断できない場合、タイ語版が優先して当事者を拘束すると考えておくべきです。
また、契約書をタイ語と日本語など複数の言語の併記により作成すれば、母語が異なる者同士が契約する場合でも、両当事者が内容を確認しやすくなるでしょう。また、前述のとおり、言語間の齟齬が生じた場合の優先関係を定めておけば、どちらの言語の規定が適用されるかという紛争は回避できます。とはいえ、そもそも齟齬が生じない状態にすべきであることは明らかです。したがって、契約書を作成・レビューする過程では、認識の齟齬を予防するため、併記されている各言語の規定内容が一致しているか確認することが必須となります(つまり、作成・レビューの負担が増加する可能性があります)。
なお、日系企業やタイ企業と取引をする場合の契約書の言語に関する一つの方策は、英語によって契約書を作成し、日本語やタイ語への翻訳版が作成されたとしても英語版を優先させる、という方策です。
英語であれば、日本人もタイ人もお互いに相手方の母語よりも格段に理解でき、母語への翻訳版ではなく原文(英語版)での検討も可能です。
その意味において、お互いにとってフェアであり理解もしやすく、齟齬も生じにくいと考えます。
準拠法
タイ法人同士の契約である場合には、準拠法(適用される法令)は一般的にタイ法となるはずです。しかし、例えば日本法人とタイ法人との間の契約の場合、日本法とタイ法のどちらを準拠法とするかという問題が生じます。
この問題を解決するのが「抵触法」という種類の法令であり、日本では「法の適用に関する通則法」、タイでは「法の抵触に関する法律(Act on Conflict of Laws B.E. 2481)」がこれに該当します。
そして、このタイ法「法の抵触に関する法律」によれば、「契約の重要部分や効力について適用する法律は、当事者の意思に基づいて決定される」のが原則です(13条1項)。したがって、タイ(の裁判所)においては、原則的に、契約当事者が日本法を準拠法とする合意をすれば日本法に従って、タイ法を準拠法とする合意をすればタイ法に従って判断されることとなります。
この点、タイ法を準拠法とする場合には、契約書上の各条項がタイ法上無効とされるおそれや制限されるおそれがないか、というタイ法との整合性についても確認しておくことが大切です。
なお、紛争が発生した場合にタイの裁判所で解決するというケースを念頭においた場合、基本的には、タイ法を準拠法としておく方が簡便ではあります。なぜならば、タイの裁判官はタイ法のプロであって日本法のプロではないため、日本法が適用される場合には、当事者が日本法やその解釈などを主張立証する負担が生じるからです。
裁判管轄
国際契約の場合、準拠法と同様、紛争が生じた場合にどこの裁判所で審理するかという裁判管轄も問題となります。
この点、こちらからタイ法人に対して何らかの請求をするという場面を想定すれば、タイの裁判所に裁判管轄がある(タイの裁判所で紛争を解決する)という合意をしておく方が無難です。なぜならば、日本の裁判所で勝訴したとしても、日本の判決はタイ国内では(今のところ)執行できないからです。つまり、タイにある相手方の財産への差押えなど強制執行をおこなうためには、あらためてタイの裁判所で勝訴判決を得る必要が生じます。したがって、こちらからタイ法人に請求するという場面を前提とする場合には、「バンコクを管轄する裁判所」など、タイの裁判所により紛争を解決する旨の合意をしておくことが基本となります。
なお、タイの民事訴訟法には当事者が裁判管轄について合意できる旨の規定がないため、日本の裁判所を管轄裁判所として合意していた場合であっても、タイの裁判所に訴訟提起できる余地はあります。もっとも、相手方が「合意に従って日本の裁判所で解決すべき」などと反論する可能性もあり、タイの裁判所が訴えを受理しない可能性も否定できません。したがって、便宜だからという理由だけで軽々に日本の裁判所を管轄裁判所とすることは控えておくべきです。
電子署名
最後に、タイでも、電子署名により契約を締結することができます。しかしながら、その電子署名は、Electronic Transactions Act B.E.2544の定める基準に合致しなければなりません。
具体的には、次の基準を満たす必要があります。
- その電子署名が、当該データ内で利用されている範囲において、その電子署名の署名者にのみ紐づけられていること
- 署名時において、その電子署名が署名者により管理されており、それ以外の者の管理下にないこと
- 署名後、電子署名に対して行われた変更が検出できること
- 電子署名について、データに記載された情報の完全性を保証することが法律上要求されている場合、電子署名が付された時以降のデータ内容変更の有無が検証できること
大雑把に言えば、「署名者が特定でき、かつ、改ざんが防止できるもの」であることが必要です。
この点、タイ電子取引開発局のガイドラインによれば、PKI(Public Key infrastructure)技術を利用した「デジタル署名」は上記の基準を満たすものとされています。
なお、実務上、プリントアウトした契約書上に署名し、それをスキャンしてPDF化して相手方にメール送付するといった運用が取られることもあります。この場合、PDFデータが添付されたメールの送信元が取引相手方である限り、後日、署名の有効性に関する紛争が生じる可能性は極めて低いと考えられます。そのため、時間的な余裕がない場合や取引の重要性が低い場合などには、このような簡易的な手段を選んでもよいでしょう。もっとも、前述した書面での作成が義務付けられている契約の場合には、原則どおり、スキャンデータではなく紙(書面)のやり取りにより、又は、PKI技術を用いたデジタル署名を用いる方法により、契約書を作成しておくべきです。
まとめ
今回は、タイにおける契約書実務について概観しました。
タイでも、契約書は、将来の紛争を予防し、問題が発生した際に適切に権利行使できるようにするための道具です。自社の典型的な取引についてはテンプレートを準備しておくなど、適切な内容の契約書を円滑に締結できるよう、事前に準備しておくことが大切です。