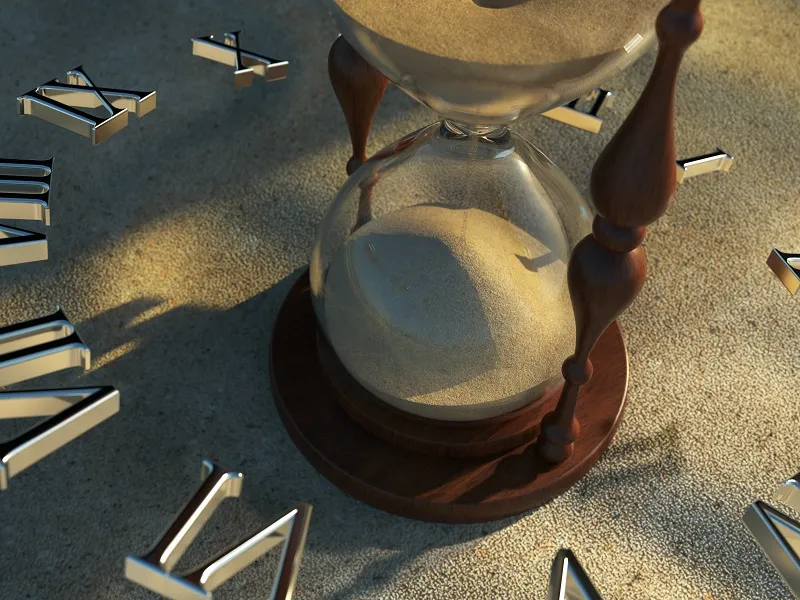今回は、タイにおける消滅時効制度の概要について解説します。
日本には、債権を一定期間行使しなかった場合に債権を行使できなくなるという消滅時効制度が存在しますが、タイでも同様の制度が存在します。
うっかり債権を消滅させてしまうことを防ぐため、タイの消滅時効制度の概要について把握しておくことが大切です。
概要
タイの消滅時効制度は、日本の旧民法における消滅時効制度と類似しています。
例えば、原則的な消滅時効期間があるほか、一部の債権については、短期間の消滅時効期間が定められています。また、時効を更新(中断)するための方策も定められています。
消滅時効の起算点
タイにおける消滅時効期間は、債権を行使できるときから進み始めます(民商法193/12条)。
つまり、支払時期が到来したときから消滅時効期間が進み始めます。
消滅時効の更新
たとえ消滅時効の進行が開始していても、次のいずれかの事由があれば、時効が更新されます。つまり、それまでに経過していた消滅時効期間が一度ゼロに戻り、再びゼロから進行を開始するのです。
【時効の更新事由(民商法193/14条)】
(1) 債務を承認する書面の作成、一部の履行、利息の支払、担保の提供、又は、債務者が債務を承認していると明確に示唆される他の行為により、債務者が、債権者に対し、債務を承認したこと。
(2) 債権者が、証拠を確立し又は履行を請求するため、訴訟を提起したこと。
(3) 債権者が、破産手続にて、債務の返済を求める届出をしたこと。
(4) 債権者が、仲裁を申し立てたこと。
(5) 債権者が、訴訟提起と同様の効果を有するその他の行為をしたこと。
このうち重要なのは、1.と2.です。
1.は、債務者の任意の行為により時効が更新される場合を規定しています。
2.以降は、債権者の行為により時効が更新される場合を規定しており、その中で一般的に行われている方法が、2.の訴訟提起です。
消滅時効による債権の消滅を防止するためには、まず、債務者の任意の行為による時効の更新を検討すべきこととなります。なぜならば、この方法が最も簡便で費用も時間も要しないからです。具体的には、債務者に対して、債務承認書への署名や一部支払などを求めていくとなります。
もっとも、債務者が債権者の求めに応じてくれるとは限りません。そのような場合には、債権者は、訴訟提起を検討すべきこととなります。
催告による時効の完成猶予制度・協議による時効の完成猶予制度の不存在
消滅時効期間の経過を防止する場面で注意しておかなければならないのは、タイには、催告による時効の完成猶予制度が存在しないということです。
日本の民法では、催告をすれば6か月間は消滅時効が完成しないという制度があります(日本民法150条1項)。これにより、たとえ訴訟提起しなくても、配達証明付き内容証明郵便などで債務の履行を求めれば、1回だけ、催告時から6ヶ月間に限り、消滅時効期間が経過して債務が消滅することを防止できます。
ところが、タイでは、このような制度がありません。したがって、いくら裁判外で支払を求めていたとしても、消滅時効期間の進行には何の影響もなく、無意味なのです。
同様に、タイには、協議による時効の完成猶予制度も存在しません。
日本の民法では、権利について協議する旨の書面合意がされた場合、消滅時効期間が経過して債務が消滅してしまうことを一定期間防止できるという制度があります(日本民法151条)。
ところが、タイでは、このような制度もありません。したがって、いくら協議する旨の書面合意があったとしても、消滅時効期間の進行には何の影響もなく、無意味なのです。
以上のとおり、債務者の協力が得られない場合、債権者としては、一般的に、訴訟を提起せざるを得ないこととなります。
時効援用の必要性
日本では、消滅時効期間が経過しても、当然に債権が消滅するわけではありません。債務者が時効を援用(消滅時効による債権の消滅を主張)して初めて、債権が消滅します。
これはタイでも同様であり、債務者による時効の援用が消滅時効による債権消滅の条件となっています(193/29条)。
消滅時効期間
タイの消滅時効期間の概要は、以下のとおりです。
1.原則的な消滅時効期間
原則的な消滅時効期間は、10年です(193/30条)。
また、次項で述べるもともとの短期消滅時効にかかわらず、確定判決に基づく債権や、和解契約に基づく債権については、時効期間は10年となります(193/32条)。
2.短期消滅時効(5年)
次の各債権については、消滅時効期間が5年とされています。
【消滅時効期間が5年とされるもの(民商法193/33条)】
(1) 未払の利息。
(2) 元本の分割払のための金銭。
(3) 財産の賃貸借の未払賃料。ただし、193/34条(6)に規定する動産の賃貸借の賃料を除く。
(4) 未払の月給、終身定期金、年金、扶養手当、その他同様に定期的な支払をすべき性質を持つものの未払の金銭。
(5) 193/34条(1)、(2)、(5)に規定する債権であって、2年の消滅時効期間が適用されないもの。
消滅時効期間が5年とされるものの典型例としては、
– 未払の利息(193/33条(1))
– 不動産の賃料(193/33条(2))
があります。
3.短期消滅時効(2年)
次の各債権については、消滅時効期間が2年とされています。
【消滅時効期間が2年とされるもの(民商法193/34条)】
(1) 商業又は産業に従事する者、職人、工業技術者、職工の債権であって、前払金を含め、商品の対価、作業の対価、他人の業務の処理の対価を請求するために行使できるもの。ただし、それが、債務者自身の事業のために行われたものである場合を除く。
(2) 農業又は林業に従事する者の債権であって、債務者の家庭だけで使用される農作物又は林産物の対価を請求するために行使できるもの。
(3) 旅客運送者又は物品運送者の債権、使者(messenger)の債権であって、前払金を含め、運賃、航空運賃、使用料又は手数料を請求するために行使できるもの。
(4) 旅館業又は宿泊業を営む者の債権、食品及び飲料を提供する者の債権、娯楽施設法に基づく娯楽施設業を営む者の債権であって、前払金を含め、宿泊料、飲食料、サービス料、宿泊もしくはサービス利用のための来訪者に対して行われた作業の料金を請求するために行使できるもの。
(5) 宝くじ、抽選券又はこれらに類似する性質を有するチケットを販売する者の債権であって、チケット代のために行使できるもの。ただし、転売のために販売する場合を除く。
(6) 動産の賃貸業を営む者の債権であって、賃料のために行使できるもの。
(7) 他人の業務の処理を営む者又は仕事の委託を受けた者のうち、第1号に規定する者以外の者の債権であって、前払金を含め、その対価を請求するために行使できるもの。
(8) 個人の仕事に従事する労働者の債権であって、前払金を含め、賃金その他仕事の対価を請求するために行使できるもの。また、使用者の債権であって、前払金の返還を請求するために行使できるもの。
(9) 無期、有期、日雇、実習を問わず、労働者の債権であって、前払金を含め、賃金その他対価を請求するために行使できるもの。また、使用者の債権であって、その前払金の返還を請求するために行使できるもの。
(10) 実習生の指導者の債権であって、前払金を含め、実習料金その他の合意された費用を請求するために行使できるもの。
(11) 教育機関又は医療施設のオーナーの債権であって、前払金を含め、学費その他の費用又は医療費その他の費用を請求するために行使できるもの。
(12) 他人の育成又は訓練を行う者の債権であって、前払金を含め、業務の対価を請求するために行使できるもの。
(13) 動物の育成又は訓練を行う者の債権であって、前払金を含め、業務の対価を請求するために行使できるもの。
(14) 教師又は指導員の債権であって、教育料を請求するために行使できるもの。
(15) 医師、歯科医師、看護師、助産師、獣医師、またはその他の医業に従事する者の債権であって、前払金を含め、業務の対価を請求するために行使できるもの。
(16) 弁護士、法律実務家、専門家証人の債権であって、前払金を含め、業務の対価を請求するために行使できるもの。また、依頼者の債権であって、その前払金の返還を請求するために行使できるもの。
(17) 技師、建築家、監査人、その他の独立した専門職に従事する者の債権であって、前払金を含め、業務の対価を請求するために行使できるもの。また、これらの業務の委託者の債権であって、その前払金の返還を請求するために行使できるもの。
消滅時効期間が2年とされるものの典型例としては、
– 商工業者の商品の売買代金、業務委託料・請負代金(193/34条(1))
– 従業員に支払われる賃金や解雇補償金(193/34条(9))
があります。
4.取引上の債権の消滅時効期間
会社の取引上の債権の消滅時効期間は、原則的に2年であると考えておくべきでしょう。
なぜならば、前述の193/34条(1)によれば、商工業者の商品の売買代金や、受注した業務の委託料・請負代金(以下まとめて「売買代金等」といいます。)の消滅時効期間は2年であることが規定されているからです。
ただし、同号には、「それが、債務者自身の事業のために行われたものである場合を除く。」というただし書きが付されていることにも着目すべきです。この文言からすれば、会社が販売した商品や提供した業務が取引相手の事業のためのものであった場合には、消滅時効期間は2年にはならないと考えられるのです。
では、この場合の消滅時効期間が何年になるかというと、5年になります。なぜならば、5年の短期消滅時効について定めている上記の193/33条(5)に、「193/34条(1)、(2)、(5)に規定する債権であって、2年の消滅時効期間が適用されないもの」は消滅時効期間を5年とする旨の定めがあるからです。
つまり、
– 会社の売買代金等の消滅時効期間は、原則として2年である。
– ところが、その商品や業務が取引相手の事業のためのものであった場合、2年という期間が適用されない。
– そして、会社の売買代金等であるものの2年という期間が適用されない場合には、193/33条(5)に基づき、消滅時効期間が5年となる。
ということになります。
この点、タイの判例でも、概略、「債務者が消費者である場合や、債務者が個人的消費のために取引した場合、消滅時効期間は2年となる。しかしながら、債務者が事業の継続のために取引した場合、193/33条(5)に基づき、消滅時効期間は5年となる。」と述べているものがあります。
企業間取引においては、商品等が取引相手企業の事業のためのものである場合が一般的であるはずなので、多くの場面で消滅時効期間は5年になると考えられます。
他方、小売業のケースなど、取引相手が個人の消費者である場合、その商品等は事業のためではなく自ら消費するため(生活のため)に必要なものと考えられますので、消滅時効期間は、193/34条(1)の原則のとおり、2年となります。
もっとも、このような条文の読み方においては、取引相手の地位や目的によって、消滅時効期間が左右されることとなります。
そのため、債権が時効により消滅するリスクを防止するという観点からすれば、企業間取引により生じたものであるか、消費者との間で生じたものであるかを問わず、「2年で時効消滅する可能性がある」という前提のもと、支払を請求できる時点から2年が経過する前には必ず訴訟提起するなどして、確実に時効を更新させておくべきです。
5.労働契約上の債権の消滅時効期間
前述のとおり、賃金や解雇補償金など、労働契約上の債権の消滅時効期間は、2年です(193/34条(9))。
この点、他の条項にも、労働契約上の債権を意味するように読める言葉が出てきます。例えば、193/33条(4)には「未払の月給」という言葉があり、月払の賃金がこれに該当するとなると、消滅時効期間は5年となるようにも思えます。
しかしながら、判例上、賃金を含め、労働契約上の債権の消滅時効期間は「193/34条(9)に基づき2年である」旨が示されています。したがって、賃金などの労働契約条の債権の消滅時効期間は、判例に従い、2年と考えておくべきでしょう。
その他注意すべき権利行使可能な期間
以上が一般的な消滅時効期間についての説明となります。
ただし、日本の民法と同様、権利行使できる期間が特に限定されている債権が幾つかあります。これらの債権については、それぞれ定められている期間内に権利行使しなければ、その後はもはや権利行使できなくなってしまいます。
注意を要する債権の一例は、以下のとおりです。
(1) 不当利得返還請求権(419条)
損失を被った者がその返還請求権を知ったときから1年、又は、返還請求権が発生したときから10年。
(2) 不法行為に基づく損害賠償請求権(448条)
被害者が不法行為及び賠償義務者を知った日から1年、又は、不法行為日から10年。
(ただし、刑事上の罰則を伴い、かつ、刑事上の時効期間がより長期である場合は、刑事上の時効期間となる。)
(3) 数量の不一致に基づく責任追及(467条)
引渡しから1年。
(4) 瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく責任追及(474条)
瑕疵が発見されたときから1年。
まとめ
今回のコラムでは、タイの消滅時効制度について概観しました。
タイの消滅時効制度は、日本の旧民法上の消滅時効制度に類似していますので、日本人にとっては馴染みやすく、基本的には日本国内の取引の場合と同じように債権管理して差し支えないといえます。
しかしながら、催告や協議による時効の完成猶予制度がないことに注意が必要ですし、日本の現行民法では撤廃されている短期消滅時効が存在しています。
そこで、自社のどの債権が、いつまでに消滅時効により消滅する可能性があるかという点をきちんと把握しておき、余裕を持って対策を取ることが大切です。