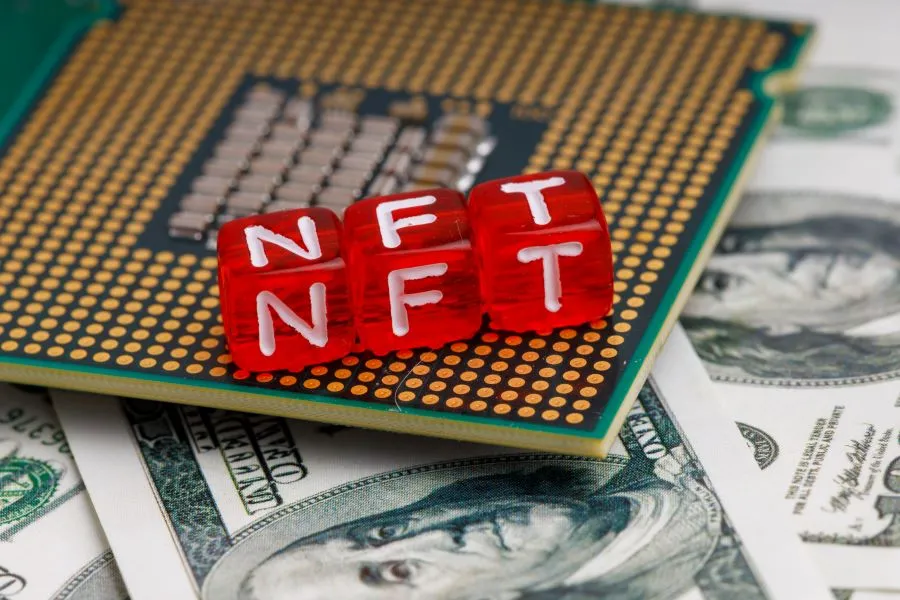※本記事は、2020年11月に公開した初稿「NFT(Non-Fungible Token)と法規制」に2023年12月現在の最新の法令改正等を加筆修正して、再度掲載したものです。
2017年4月施行の改正資金決済法により暗号資産(旧:仮想通貨)に該当するトークンの取扱いについて多くの場面で暗号資産交換業の登録が必要となり、そのハードルの高さからスタートアップ企業がブロックチェーンビジネスを行うためには、暗号資産交換業の登録を必要としないビジネス設計を模索する、というのが一般的な取り組みとなってきました。
そのような中、暗号資産交換業の登録を必要としないブロックチェーンビジネスとして、NFT(Non-Fungible Token、ノンファジブルトークン)を取り扱うビジネスが2021年頃から活況を呈し、ジェネラティブアート等のデジタルアートのNFTの高額販売事例が相次いだことから、いわばNFTバブルの状態となりました。2023年末現在は、流通量の減少等が指摘されているものの、ブロックチェーンゲームにおける活用など、依然としてNFTは、Web3の重要な牽引役となっています。
1 NFTとは何か
NFTとは、「代替不可能なトークン」などと訳されるものであり、代替性のない固有の価値を有するデジタルデータをブロックチェーン技術を用いて転々流通できるようにしたものです。ビットコイン(BTC)に次ぐ知名度を有する暗号資産であるイーサリアム(ETH)の仕組みを利用したブロックチェーン技術の規格である「ERC721」という規格で作成されることが多くなっています。
具体的なユースケースとしては、オンラインゲーム内のアイテムやキャラクターを紐づけたもの、デジタルアートを紐づけたもの、リゾート施設等の利用権・会員権を紐づけたもの、現物の美術品や酒等の所有権を紐づけたもの(いわゆる「RWA」=リアルワールドアセット(現物資産)型)等の実例があります。
以下、本稿では、NFTと暗号資産規制について概説を致します。
2 「暗号資産」の定義
ブロックチェーン技術を用いたトークンとして、最も代表的なものは、2009年に登場したビットコインであり、一般に「仮想通貨」として知られ、その投機性の高さが注目を浴びてきました。また、2014年の仮想通貨取引所の倒産、2018年の仮想通貨取引所におけるNEMコインの不正流出事件では、仮想通貨取引をめぐる規制の不備や一般投資家保護の問題が世間的な関心を集めました。
日本は、世界に先駆けて仮想通貨についての法整備を進めており、2017年4月施行の改正資金決済法にて、初めて仮想通貨が法律上、定義され、仮想通貨交換業につき登録制の規制が設けられました。その後、直近では2020年5月施行の改正資金決済法により、「仮想通貨」はその法律上の名称が国際的な名称である「Crypt currency」に合わせて「暗号資産」に変更されたほか、各種規制の強化が図られています。
NFTもブロックチェーン技術を用いたトークンとして、法定通貨や暗号資産による売買等の対象となるものであることから、この資金決済法上の「暗号資産」該当性が問題となります。
資金決済法上、暗号資産とは、
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(法第2条第14項第1号、1号暗号資産)
及び
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(同第2号、2号暗号資産)
と定義されており、ただし、金融商品取引法との規制対象の交通整理のため、「金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利(=電子記録移転有価証券表示権利等)を表示するものを除く」とされています。
非常に複雑な規定となっていますが、大まかな整理をすると、1号暗号資産については、
①代価の弁済のために不特定の者に対して使用できること
②不特定の者を相手方として購入及び売却をできること
③電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
であり、
④本邦通貨及び外国通貨、電子決済手段並びに通貨建資産ではないこと
⑤電子記録移転有価証券表示権利等ではないこと
が要件となっています。
①の要件は、不特定多数を相手に決済手段として利用できることを意味します。したがって、発行体の加盟店においてのみ使用できるような場合は本要件を充足しません。
②の要件は、法定通貨との売買・交換の市場の有無等から判断されます。トークンの移転につき、発行体の譲渡承認が必要な場合には本要件を充足しません。NFTのうち、譲渡性を機能的に制限したSBT(Soul Bound Token)は、本要件を充足せず、「暗号資産」に該当しません。
③の要件にある「電子情報処理組織」は技術的にブロックチェーンのみを意味するものではありませんが、ブロックチェーン技術がその典型例であり、コンピューター上で移転することができるものと換言することができます。
④のうち、通貨建資産は「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(略)が行われることとされている資産」(同法第2条第7項)と定義されており、その典型例は、前払式支払手段(同法第3条)などのプリペイドカード上のポイントなどがあります。
⑤の「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、いわゆるセキュリティトークン(ST)が該当し、詳細は省略しますが、典型的には集団投資スキーム持分等のみなし有価証券をトークン化してブロックチェーンにより移転可能としたものなど、収益分配機能を有するトークンが該当します。
2号暗号資産は、1号暗号資産の定義を前提として、
①不特定を相手方として1号暗号資産と相互に交換できる財産的価値であり、
なおかつ、
②電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
が該当します。
2号暗号資産は、要するに直接法定通貨との交換価値を有していなくとも、ビットコインやイーサリアムといった1号暗号資産との交換価値を有するものについては、1号暗号資産と同様に暗号資産としての規制を適用するというものであり、その該当性は、1号暗号資産と同等の経済的機能を有するかといった観点などから判断されるものです。
1号暗号資産及び2号暗号資産の該当性判断においては、金融庁が開示している事務ガイドライン第三分冊「16 暗号資産交換業者関係」(以下、「ガイドライン」といいます。)が実務上の重要な解釈指針となります。実際のケースで、この解釈指針に照らして該否判断が難しい場合には、金融庁への相談・照会を行いながら慎重な検討を要することになります。
3 「暗号資産交換業」登録が必要な場合
取り扱うトークンが資金決済法上の「暗号資産」に該当する場合、次に該当する行為を「業として行う」場合に、「暗号資産交換業」の登録が必要です(同法2条7項各号)。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
「業として行う」とは、ガイドラインにおいて、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうもの、とされています。したがって、例えば友人間で1回限りのビットコインの売買をする、という行為は「対公衆性」も「反復継続性」も欠くため、「業として行う」との要件に該当しません。
いわゆる暗号資産の取引所を営む場合、事業者が顧客と暗号資産を売買するか、顧客間の売買を媒介することになるため、上記1号又は2号に該当し、暗号資産交換業の登録が必要となります。
また、自ら暗号資産を発行して、顧客に対して直接販売することで資金調達を行おうとするいわゆるICO(Initial Coin Offering)は、「暗号資産の売買」として上記1号に該当します。
上記4号は、いわゆるカストディ業務規制であり、カストディ業務に該当するか否かは、事業者が独自に預り暗号資産の処分が可能な程度に顧客の秘密鍵を預かるか否かが一つの判断指標となります。ウォレットサービスを展開する場合などは、カストディ業務に該当するか否かで暗号資産交換業登録の要否が異なり、利用者の利便性や安全性を追求すると、カストディアルな交換業登録が必要なサービス設計となりやすくなるため、慎重な検討が必要です。
暗号資産交換業に該当する行為につき、無登録での営業を行った場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの両方(同法第107条第12号)という重い刑事罰の制裁が規定されており、想定するビジネスにつき、暗号資産交換業の登録を要しないか、という点は事業の開始前に必ず検討する必要がある事項です。
暗号資産交換業の登録を得るためには、大まかに次の基準をクリアする必要があります。
ア 資本金1000万円以上かつ純資産あり
イ 必要な社内体制の具備
・顧客の暗号資産の適切な管理
・顧客資産と事業者資産の分別管理
ウ 認定資金決済事業者協会への加入及び同協会の自主基準に準じた社内規程の整備
財産的な基準もさることながら、不祥事が相次いだことを受けてかなり厳格な人的・組織的な社内体制の整備が要求されており、2023年12月1日現在において、その登録が認められているのは全国でわずか29社に過ぎません。
実際の審査は、金融庁への事前相談から始まり、役員へのヒアリングや書類審査のほか、訪問調査も実施されるものであり、最低6か月間、多くは1年以上を要するものとされています。その対応に要する難易度の程度は、金融庁の公開している「暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」( https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20181024-2.pdf )から垣間見ることができますが、創業間もないスタートアップ企業には、ハードルが高いものと言わざるを得ません。
4 NFTは「暗号資産」に該当しないのか?
前置きが長くなってしまいましたが、改めて本稿の本題に戻ります。
上記1で整理した「暗号資産」の定義に照らしてNFTの暗号資産該当性を検討すると、例えばゲーム内アイテムのNFTを念頭に置くと、法定通貨やビットコイン等の暗号資産による売買・交換の対象となる場合、対象となるNFTのセカンダリーマーケットの発展状況等にもよるところもありますが、②不特定の者を相手方として購入及び売却をできること、との要件は充たす可能性が高くなります。また、NFTがブロックチェーン技術に依拠して、発行者による制限なく、転々流通することが可能な仕様となっていれば、③電子情報処理組織を用いて移転することができるもの、との要件も充たします。
しかしながら、あくまでゲーム内アイテムであれば、①不特定多数を相手とした決済手段としての機能は有さず、この点で暗号資産該当性が否定されることが多いと考えます。ビットコイン等の既存の1号暗号資産と交換が可能なことから、より具体的には2号暗号資産の該当性が俎上にのるところ、2号暗号資産についても1号暗号資産と同等の経済的機能を有することが判断要素となるため、決済手段としての機能を有さない点で、2号暗号資産の該当性が否定されるとの結論に至る可能性が高いです。
この点は、2019年9月3日公開の金融庁のパブリックコメントNo.4において「例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。」( https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20190903-1.pdf )との見解が示されていることが、実務上の重要な参考となります。
また、2023年3月24日にガイドラインが改訂され、同Ⅰ-1-1①に次の注記が追加されています(下線は執筆者追記)。
(注)以下のイ及びロを充足するなど、社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるものについては、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものという要件は満たさない。ただし、イ及びロを充足する場合であっても、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまらず、現に小売業者の実店舗・ECサイトやアプリにおいて、物品等の購入の代価の弁済のために使用されているなど、不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態がある場合には、同要件を満たす場合があることに留意する。
イ.発行者等において不特定の者に対して物品等の代価の弁済のために使用されない意図であることを明確にしていること(例えば、発行者又は取扱事業者の規約や商品説明等において決済手段としての使用の禁止を明示している、又はシステム上決済手段として使用されない仕様となっていること)
ロ.当該財産的価値の価格や数量、技術的特性・仕様等を総合考慮し、不特定の者に対して物品等の代価の弁済に使用し得る要素が限定的であること。例えば、以下のいずれかの性質を有すること
・最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること
・発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること
なお、以上のイ及びロを充足しないことをもって直ちに暗号資産に該当するものではなく、個別具体的な判断の結果、暗号資産に該当しない場合もあり得ることに留意する。
上記は、ガイドライン上、明記はされていないものの、複数発行されるNFTの暗号資産該当性について、金融庁が判断基準を示したものとされており、実務上の参照価値が高いものであります。より具体的には、パブリックコメントにおいて、上記ロ中の「最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること」とは「1000円以上」 、「発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること」とは「100万個以下」 を想定している旨の補足がされており、この単価の要件と発行数量の要件を前提に、上記イの条件も遵守することで、相当程度明確にNFTの暗号資産該当性を回避したビジネス設計が可能になるものと考えます。
5 その他の法規制
NFTについて、暗号資産該当性のほか、例えばゲーム内アイテムとしてユーザーに付与する場合には、景品として、景品表示法の規制対象となり、その上限額に注意が必要です。
また、ゲーム内アイテムの場合、いわゆるガチャやランダム型販売の仕組みによる配布が多くなるところ、NFTが暗号資産に該当せずとも換金性を有するものであるから、刑法上の賭博罪(法185条)の該否も問題となり得るところです。
その他に現物資産を紐づけるRWAトークンの場合、預託等取引に関する法律や古物営業法との抵触の検討が必要になる場合もあります。
以上、NFTに関する法規制について、暗号資産該当性を中心に概説を致しました。実際にNFTを活用したビジネスを展開される場合には、個別具体的なトークンの仕様や機能等を考慮のうえ、適用される法規制について弁護士との相談を踏まえた慎重な検討が必要となりますので、弊所Web3チーム所属の弁護士にご相談ください。