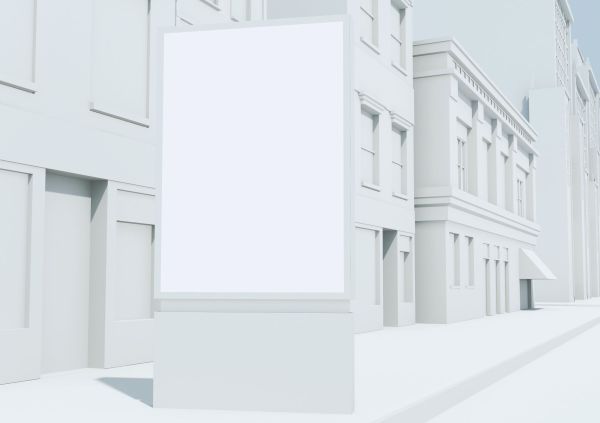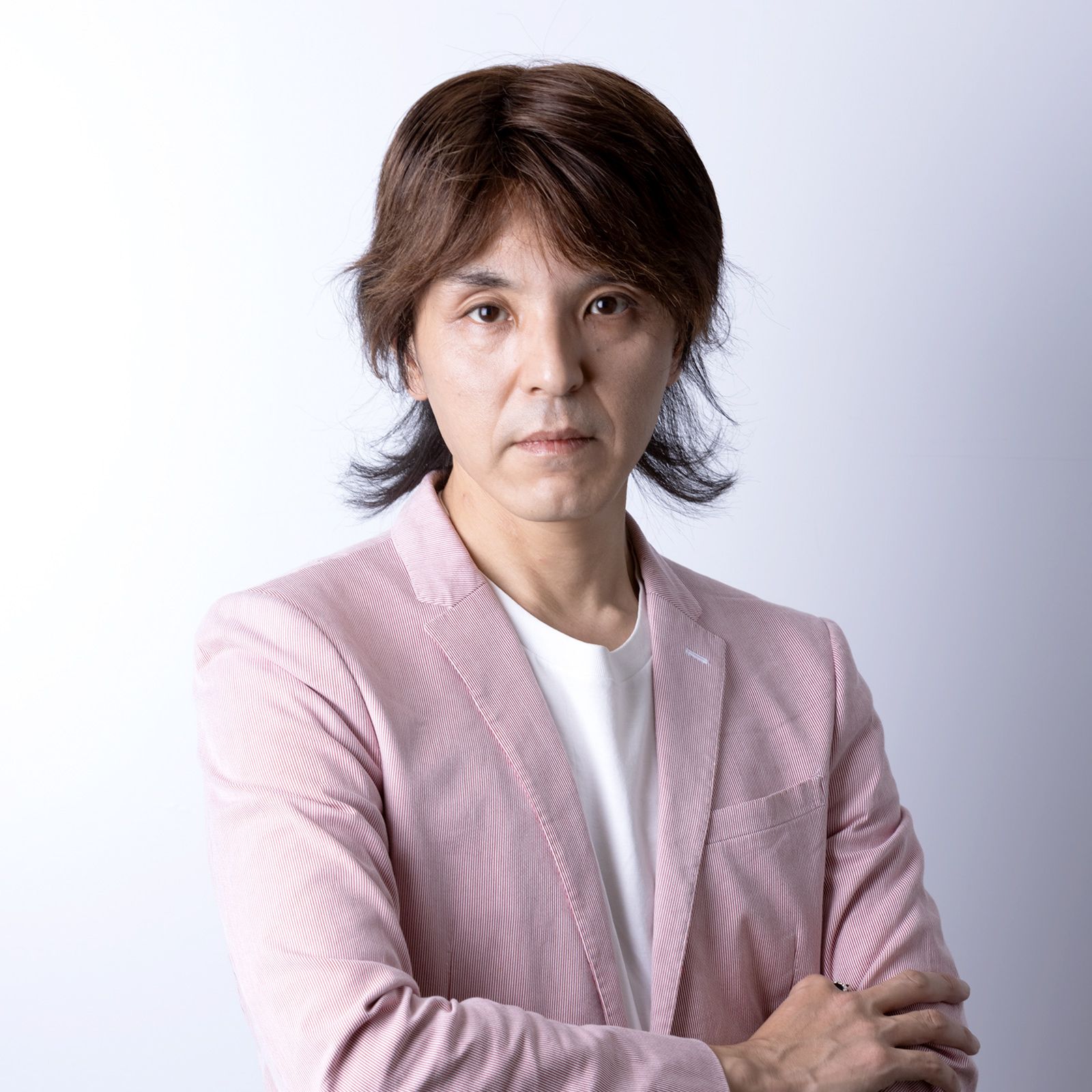執筆:弁護士 早崎 智久(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
(※2023年8月1日に公開。2023年10月17日、2024年3月7日、2024年5月31日に記事内容をアップデートいたしました。)
2023年8月1日 公開
2024年5月31日更新
景品表示法(景表法)は広告などのマーケティングに関わるすべての人が知っておかないといけない法律です。まず、景表法ルールの内容と、違反してしまうとどうなるのかを正しく理解しましょう。また、最近の違反事例は、監督官庁(消費者庁)が注視していることがわかるだけでなく、この記事を参考にすると、どこに落とし穴があったのか、どこに注意が必要なのかも理解頂けるでしょう。早速詳しく解説していきます。
- 1 景品表示法とは
- 2 表示規制を違反した場合の罰則は?
- 3 景品表示法の違反事例
- ⑴ 大幸薬品株式会社に対する課徴金納付命令事案
- ⑵ 株式会社ゼンワールドに対する措置命令事案
- ⑶ 大木製薬株式会社に対する課徴金納付命令事案
- ⑷ 株式会社W-ENDLESSに対する課徴金納付命令事案
- ⑸ 株式会社バウムクーヘンに対する措置命令事案
- ⑹ 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する措置命令事案
- ⑺ 株式会社ドミノ・ピザジャパンに対する措置命令事案
- ⑻ さくらフォレスト株式会社に対する措置命令事案
- ⑼ 沖縄特産販売株式会社に対する課徴金納付命令事案
- ⑽ 北海道電力株式会社に対する措置命令事案
- ⑾ 株式会社バンザンに対する課徴金納付命令事案
- ⑿ 中国電力株式会社に対する措置命令事案
- ⒀ マルキユー株式会社に対する課徴金納付命令事案
- ⒁ 糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対する措置命令事案
- ⒂ レック株式会社に対する課徴金納付命令事案
- ⒃ 株式会社アリュールに対する措置命令事案
- ⒄ 株式会社ハハハラボに対する措置命令事案
- 4 景品表示法の違反を防ぐためには?
- 5 まとめ
1 景品表示法とは
⑴ 景品表示法とは
景品表示法は、商品やサービスの広告(表示)と景品に関するルールを定めるものです。つまり、事業者のマーケティングやプロモーションを規制する法律です。
医薬品等の広告は薬機法、食品の広告は健康増進法など、特定の商品やサービスには特別なルールもありますが、景品表示法はありとあらゆる商品やサービスに適用される法律です。
この記事では、広告規制(表示規制)の違反事例を解説しますが、まず「不当表示規制」の概要を説明します。
⑵ 不当表示とは
景品表示法は、「不当表示」として不当な広告を規制しています。そして、不当表示とされるのは以下の3つです。
| 1 優良誤認表示 2 有利誤認表示 3 その他の不当表示 |
順番に見ていきましょう。
⑶ 優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスに関して、
| ① 実際のものよりも著しく優良であると示す表示 ② 事実に相違して、当該事業者と同種か類似の商品・サービスを供給している他の事業者のものよりも著しく優良であると示す表示 |
の2つをいいます。
分かりやすく言えば、①は実際の商品・サービスよりもはるかに良いものだと思わせる表示のこと、②は事実ではないのに、他の会社のものよりもはるかに良いものだと思わせる表示のことです。問題になることが最も多いケースです。
⑷ 有利誤認表示
「有利誤認表示」とは、商品・サービスの価格その他の取引条件について、
| ① 実際のものよりも著しく優良であると示す表示 ② 事実に相違して、当該事業者と同種か類似の商品・サービスを供給している他の事業者のものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 |
の2つをいいます。
優良誤認表示との違いは、優良誤認表示が商品やサービスに関して良いものだと思わせることであるのに対し、有利誤認表示は、価格や取引に関する条件などに関して良いものと思わせることです。①が単体、②が他社のものと比較、という点は、どちらも同じです。
⑸ その他の不当表示
その他の不当表示とは、
| 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定するもの |
があります。これは、告示で指定されたり、公正競争規約で定められます。最近公表されたステルスマーケティング規制は、この指定告示に当たります。
以上が景品表示法が禁止している表示です。
ルールはシンプルですが、「どんな場合に「優良誤認表示」になるのか?」、「どんな資料があれば、事実だと証明できるのか」などは、ガイドラインなどを参考にしながら、広告ごとに判断します。「この表現でいいのかわからない」「この資料で証明できるのかわからない」などのご相談は下記ボタンからお気軽にお問い合わせください。
2 表示規制を違反した場合の罰則は?
景品表示法に違反すると、様々なペナルティが課せられます。
ペナルティを理解することで、万が一指摘を受けた場合でも、最適な対応をすることができます。
また、ここでは、2023年の法改正の内容も含めて説明しますが、新しい制度である確約手続きを利用することで、ペナルティを回避しながら、再発防止体制を作ることができるようになります。
⑴ 消費者庁の調査の開始
景品表示法を扱う消費者庁が、景品表示法に違反していると疑うきっかけの多くは、消費者やライバル業者の通報によると言われています。
広告は、たくさんの人に知ってもらおうとお金をかけて実施しますが、違反広告の場合は、同時に、違法なことをしていることを広めていることにもなります。広告のリスクはここにあります。
消費者庁の調査は、様々な方法で行われますが、具体的には、問題となった「表示」に関する商品の購買や、実地調査による客観的資料の収集、事業者に対する報告命令、提出命令、立入検査、質問調査などが行われることになります。
そして、命令を受けた事業者が従わない場合や、調査を妨害した場合には、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになります。そのため、調査には、誠実に応じることが絶対に必要です。
⑵ 調査の結果を踏まえた行政の対応パターン
調査の結果に応じて、消費者は以下のいずれかの対応を行います。
※2023年の法改正により、遅くとも再来年までに確約手続きができるようになります。また、従来は措置命令に従わない場合などに限られていた罰則が、違反行為自体に科せられるようになります。
① 違反行為はないが、違反のおそれがある場合
事業者への行政指導
② 違反行為がある場合
措置命令、課徴金納付命令、罰金、確約手続き
⑶ 行政指導
行政指導は、違反の疑いはあるものの、違反行為がなかった場合に行われます。行政指導を受けた場合は、それに従って、違反行為をしないような体制を設けることが大切です。
⑷ 措置命令
調査の結果、不当表示に該当する行為があった場合は、消費者庁は措置命令として、違反行為の差止め、その行為の再発防止のために必要な事項の実施、今後は違反行為をしないことを命じると共に、それらの実施に関連する事項が公表されます。
この措置命令に従わない者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、情状により、懲役と罰金が併科される場合もあります。これに加え、事業者にも、3億円以下の罰金が科されます。併せて、措置命令違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その防止に必要な措置を講じなかった法人の代表者にも、300万円以下の罰金が科されます(景表法第39条)。
⑸ 課徴金納付命令
優良誤認表示・有利誤認表示を行った場合、課徴金として、課徴金対象期間における売上額の3%を課徴金として納付するべき、課徴金納付命令が出される場合があります(景表法第8条)。
課徴金対象期間は、原則として、課徴金対象となる不当表示を開始した日から、これをやめた日までですが、課徴金対象行為をやめた後に、当該行為に係る商品または役務の取引をした場合には、当該辞めた日から、一般消費者の誤認の恐れを解消するための措置を講じた日または表示行為終了日から6カ月経過日のいずれか早い日までも、課徴金対象期間に含まれることになります。
さらに、2023年の法改正により、消費者庁は、事業者が売上額に関する報告をしないときは、売上額を推計できるようになります。つまり、消費者庁は、事業者が報告をしない場合でも課徴金納付命令が出させるようになるので、これまで以上に課徴金の納付命令が出されることが増えることになります。
これに加え、10年以内に課徴金納付命令を受けたことのある事業者に対しては、課徴金額が1.5倍(つまり4.5%)になります。
なお、あまり使われていない制度ですが、消費者に返金措置を行うことで課徴金額の減額が認められます。そして2023年の法改正により、電子マネー等による返金も認められることになります。今後は、上記の売上額の推計により課徴金納付命令が出されるケースが増えると思いますので、仮に違反行為をしてしまった場合は、返金措置を行うことで、消費者被害を軽減させつつ、課徴金額を減額するという方法が有効になると考えられます。
⑹ 罰金(直罰)
これまでは、優良誤認表示や有利誤認表示は、たとえ故意で行った場合も、それ自体は刑事罰の対象ではありませんでした。しかし、2023年の法改正により、故意(表示と実際の内容が異なっていて、それによって消費者が誤認することを知っている場合))に優良誤認表示・有利誤認表示をした場合は、犯罪として、100万円以下の罰金が科せられることになります。
⑺ 確約手続き
以上の⑸と⑹の法改正は、いずれも事業者にとっては規制が厳しくなるものですが、確約手続きは、事業者が自主的に是正計画を策定して内閣総理大臣の認定を受けることにより、措置命令や課徴金納付命令を回避できる制度です。
違反行為をした場合は、従来は処分を受けることが前提であり、再発防止策も措置命令の中で命ぜられました。もっとも、これにより打撃を受ける事業者は、次の処分を避けるために改善に取り組むのが一般的でした。
この新しい制度は、この改善に取り組むことの認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令を回避できる点で画期的な制度であり、今後は有効な活用が重要になります。
ただ、指摘を受けないように、社内で広告ルールに対応できる体制を整えておくことがもっとも必要なことになります。
広告については社内に確認する部署などを作り、公開する前にチェックして違法な広告にならないようにすることが重要ですし、広告を作成する前に社内の上長または担当部署宛に相談できるようにしておくことで、後から作り直す無駄な作業を減らすこともできます。
しかし「社内に広告ルールに詳しい人がいない」のも多く、細かなルールを入れると、広告ルールは複雑ですし、新たなルールも生まれています。現在の社員や新入社員向けに社内セミナーを実施していくことも重要になります。
「改善に取り組むために何から着手すれば良いか分からない」「現状の表記をリーガルチェックしておきたい」「社員向けのセミナーを実施したい」などのご相談は、下記ボタンからお気軽に声掛け下さい。
3 景品表示法の違反事例
ここからは、2023年度の違反事例を解説していきます。
事例で問題となった表示やその原因などを理解することは、同様の違反を犯さないためにも重要です。
※定期的に事例を追加していきます。
⑴ 大幸薬品株式会社に対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年4月11日 |
| 処分 | 課徴金納付命令 6億0744万円 |
| 事業者 | 製薬メーカー |
| 商品/サービス | ウィルスの除菌製品(雑貨) |
| 広告の種類 | パッケージ、自社ウェブサイト、 テレビ広告、動画広告 |
| 広告の期間 | 2018年9月13日~2022年4月21日 |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり→合理的根拠と認められず。 |
② 表示内容と適用法令
2023年度の1号案件となったのは、従前から大きく話題になった案件で、既に別のタイプの製品では2022年度に措置命令が出ていました。事業者は、戦前に創業した歴史のある大企業で、これまで大きな不祥事を起こしたことのない企業です。
問題となった表示は、本製品から発生する二酸化塩素の作用によって、室内空間に浮遊するウイルスや菌が除去/除菌される効果がある、とするもので、製品の性能に関する表示です。
本製品は雑貨に分類されるので、問題になる法令は景品表示法の優良誤認表示であり、表示と実際の性能の間に「著しい」違いがあるかどうかが問題になります。
結果、本製品に関する資料は、実験で用いた空間では効果があったものの、一般的な室内ではそのような効果が認められなかったものです。
③ コメント
本件のポイントは、広告の内容を事実だと証明するのが難しい点です。
本件のように、実験をした時の環境と、製品が実際に使われる環境の違いが問題になったケースは過去にもありますが、実験という特殊な環境での性能結果が、その製品が実際に使用される場面でも同じ性能になるのか、より慎重な検証が必要です。
また、本件の製品は、販売期間が長く、たくさん売れた製品だっただけに、課徴金の額も大変高額になりました。本件は、株主代表訴訟が提起されるなど、事業者や役員にも大きな影響を与えています。
| ・製品の効果・性能を裏付ける資料(エビデンス)では、実験という特殊な環境での効果と、実際に製品が使用される場面での効果が同じであることの裏付けが重要 ・たくさん売れた製品のときは、課徴金額も高額になる |
⑵ 株式会社ゼンワールドに対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年4月27日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 建材メーカー |
| 商品/サービス | 空気清浄剤(雑貨)/同製品の塗布 |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、動画広告、プラットフォーム上の自社店舗サイト |
| 広告の期間 | 2022年6月20日~ |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり→合理的根拠と認められず。 |
② 表示内容と適用法令
2023年度の2号案件は、1号案件と同様に、空気の清浄に関するもので、製品及びその塗布(サービス)が対象になりました。
同社の製品は、光触媒を利用したもので、ホルムアルデヒドの低減に効果があるとされ、同製品を使用した居室については国土交通大臣の認定を受けているようです。
問題となった表示は、ホルムアルデヒドに限らず、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイルス、一般皮膚炎及び喘息の原因物質などの様々な空気中の物質を分解除去し、室内の空気を浄化する効果」とするもので、製品の性能に関する表示です。
本製品は雑貨に分類されるので、問題になる法令は景品表示法の優良誤認表示であり、表示と実際の性能の間に「著しい」違いがあるかどうかが問題になります。
結果、本製品に関する資料では、そのような効果が認められなかったものです。
③ コメント
この製品は、おそらく、ホルムアルデヒドに関しては効果が認められているように思います。
しかし、十分な検証もなく、ホルムアルデヒド以外の他の物質にまで、同じような効果があると広告した点は問題です。コロナ禍のなかで、ウイルスや除菌への社会の関心が高まっていた中で行われた点も影響しています。
また、処分の直前のタイミングで表示されたものが含まれており、指摘を受けているにもかかわらず、新たに同様の表示をしてしまったことも問題です。
課徴金納付命令は出ていませんが、課徴金は表示期間の長さで金額が増えるので、調査を受けた時点で、すぐに表示を取りやめましょう。
また、本件では、この事業者が出店していた大手プラットフォームにも今後の防止への協力が求められています。Webマーケティングではプラットフォームを利用しているケースが多く、広告を行った事業者だけでなく、プラットフォームの側でも、違反表示が無いように対策が求められることが増えると思われます。
なお、執筆時点では、同社の製品を紹介する複数の他社サイトに同様の違法な記載が残っています。消費者庁は事業者だけに指摘しますので、他社サイトは対象外ですが、事業者の取引先が引き続き違法な表示を継続すると、この取引先にもリスクになります。違反広告は、消費者だけでなく、広い範囲に影響します。
| ・製品の効果の範囲を、他のものまで広げない ・広告を掲載するプラットフォームにも違反表示をさせない努力が求められる ・販売代理店がある場合は、代理店の表示も正しく修正する必要がある |
⑶ 大木製薬株式会社に対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年5月17日 |
| 処分 | 課徴金納付命令 4655万円 |
| 事業者 | 製薬メーカー |
| 商品/サービス | 除菌製品(雑貨) |
| 広告の種類 | パッケージ、自社ウェブサイト、動画広告、プラットフォーム上の自社店舗サイト |
| 広告の期間 | 2020年9月1日~2021年10月31日 |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり→合理的根拠と認められず。 |
② 表示内容と適用法令
2023年度の3号案件も、1号案件、2号案件と同様に、空気の清浄に関するもので、社会の関心の高い製品に対して消費者庁が行った処分です。
二酸化塩素の作用で身の回りの空間のウイルスや菌の除去の効果があるとする表示が問題になったもので、1号案件と共通するところが多い案件です。
本製品も雑貨に分類されるので、問題になる法令は景品表示法の優良誤認表示であり、表示と実際の性能の間に「著しい」違いがあるかどうかが問題になります。
結果、本製品に関する資料では、そのような効果が認められなかったものです。
③ コメント
⑴の案件は大きな話題になりましたが、この製品は、⑴と表示された内容が共通しているので、類似製品として調査対象になったように思われます。よく話題になっている他社製品と類似の製品が別の会社から販売されますが、先行製品の表示に問題があると、類似製品もその機会に監視対象になります。
そして、消費者庁が、そのタイミングで類似製品に対しても相次いで処分を行うことはこれまでにも見られます。公平な対応ですが、事業者は、他社製品と同じような広告を安易にせずに、自社製品の効果にエビデンスがあるのかどうかを冷静に判断しましょう。
| ・類似製品を販売する場合は、自社製品のエビデンスもしっかりと確認する |
⑷ 株式会社W-ENDLESSに対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年5月19日 |
| 処分 | 課徴金納付命令 530万円 |
| 事業者 | インターネット広告業者 |
| 商品/サービス | 味噌汁(食品) |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト |
| 広告の期間 | 2020年11月20日~12月28日 |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり→合理的根拠と認められず。 |
② 表示内容と適用法令
2023年度の4号案件は、食品に対して消費者庁が行った処分です。
なお、本製品は食品に分類されるので、問題になる法令は景品表示法の優良誤認表示のほか、薬機法の医薬品的表示の禁止、健康増進法の虚偽誇大表示も問題になります。
事業者は資料を提供しましたが、資料では、そのような効果が認められなかったものです。
③ コメント
問題になった表示を見ても、「痩せる」や「筋力アップ」などのNGワードはありません。しかし、消費者庁は、掲載された画像など広告の全体をみて、「この食品を摂取するだけで痩身効果が得られるような表示をしたもの」と認定しました。
このように、消費者庁の審査は、広告全体を見て、「消費者を誤認させる広告になっているかどうか」を判断します。
一般的には、「NGワードを使用しなければ問題がない」といった誤った認識で広告をしてしまうケースが多いのですが、この認識では、違反表示になるリスクを回避できません。
また、この広告は、食品なのに「痩せる」という表示をしています(痩身効果)。このような広告は、医薬品的表示になり、薬機法や健康増進法にも違反します。
広告期間は1か月程度と短期ですが、500万円をこえる課徴金の納付命令が出されています。
なお、この事業者は、食品メーカーではなく、インターネット広告業者ですが、消費者庁は、本商品をこの事業者が供給する商品だと認定しています。おそらく適切な広告取扱ガイドラインも設けており、コンプライアンスに関する意識がなかったわけではなかったと思いますが、実際に広告を運用する際にルールの遵守が徹底できていなかったかもしれません。大切なことは、ガイドラインに沿った事業遂行ができるように、しっかりとした広告チェック体制をつくることが必要です。
| ・広告審査はNGワードや言い換えに囚われず、画像を含めた広告表現を全体的に確認する ・広告期間が短期であっても課徴金額が高額になる可能性を意識する ・広告取扱ガイドラインを設けるだけでなく、それを運用できる体制構築が重要 |
⑸ 株式会社バウムクーヘンに対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年6月14日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 食品メーカー |
| 商品/サービス | ペット用サプリメント(ペットフード) |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、アフィリエイトサイト |
| 広告の期間 | 2022年6月8日~2023年5月16日(非連続) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり→合理的根拠と認められず。 |
② 表示内容と適用法令
5号案件は、ペットフードに対して消費者庁が行った処分です。
問題になった表示は、目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていくココ・・・ 若々しかった目の輝きもなくなったような・・・」、犬の飼い主が目が白濁している犬を抱えているイラストと共に、「ココ・・・」及び「私にもできることが何かあるはず!!」、本件商品の容器包装の画像を掲載した上で、犬を抱えた犬の飼い主のイラストと共に、「私も試してみます!」、目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」としたものです。
なお、本製品はペットフードに分類されるので、問題になる法令は景品表示法の優良誤認表示のほか、薬機法の医薬品的表示の禁止(動物用医薬品等の範囲に関する基準などの通達)が問題になります。
事業者は資料を提供しましたが、資料では、そのような効果が認められなかったものです。
③ コメント
この広告でも、「白内障」といった病名に関するワードは使用していません。しかし、消費者庁は、広告全体から、この食品を摂取するだけで白内障の改善効果が得られるような表示をしたものと認定したものです。ケース⑷のと同様に、NGワードのチェックでは違反広告を防止できないのです。
また、この事例は、ニュースなどでも取り上げられました。この広告では「皆様に選ばれて 7冠達成!」 「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」などと広告していましたが、リサーチ業者が行った調査は、回答者に対して、ある7つの項目について、「この商品と他の事業者が販売する同種商品に関する各事業者のウェブサイトの印象」を聞いたもので、また、回答者には条件を付けず、その事業者に登録している会員全員を対象に行ったものでした。つまり、この商品と他の事業者が販売する同種の商品に関して、7つの項目をそれぞれ客観的な調査方法で調査したものではなかったとされた点です。
つまり、実際の調査内容と、広告で表示され ていた内容が異なっていたのです。
ただし、別に新しいルールが示されたわけではなく、以前からも、アンケートなどを掲載するときは、正確で客観的な情報を掲載しなければならず、一部を取り出したりすることは違法とされていました。本件でも、その昔からのルールが適用され、不適切な表示だったとされました。
薬機法に関する広告ルール(業界のルール)では、調査した情報を広告で使用する場合も、「公的な情報」か、「信頼できる業者による情報」に限定しています。雑誌などのアンケート結果を引用する広告は非常に多いですが、調査情報を利用するときは、正確であること、客観的なものであることをしっかり確認しましょう。
| ・広告審査はNGワードや言い換えに囚われず、画像を含めた広告表現を全体的に確認する ・調査情報を使用するときは、調査内容や調査方法を正確にする |
⑹ 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年6月23日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | PCメーカー |
| 商品/サービス | ノートパソコン(雑貨) |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、アフィリエイトサイト |
| 広告の期間 | 2022年10月4日~2023年2月8日(全体) |
| 違反行為 | 有利誤認表示 |
| 資料提出 | - |
② 表示内容と適用法令
6号案件は、15品目のノートパソコンの価格表示に対して消費者庁が行った処分で、2023年度初の有利誤認表示の事案です。
事業者のウェブサイトにWEB価格(通常価格)とキャンペーン価格が表示されていたところ、このWEB価格とキャンペーン期間の表示が問題とされたものです。過去の販売価格を比較対照価格とする典型的な二重価格表示と、キャンペーン期間中はその価格で購入できるとする期限限定表示の事案です。
消費者庁は、事業者が表示した価格表示は、いずれも不当なものとして、有利誤認表示と認定しました。
③ コメント
セールやキャンペーンで、通常の価格よりも安く販売する(値引き)ことは問題ありません。
ただ、その場合、通常の価格と値引きした価格の2つの価格を表示します。このように、広告のなかで二つの価格を表示するときは、「二重価格表示」というルールがあります。
特に、通常の価格(過去の販売価格)と並べて表示するときは、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」という通達があり、具体的なルールが多数定められています。
この事案では、実際にはその価格で販売したことがなかったこと、キャンペーンの後も同じ価格で販売されていたことから、違反広告となりました。
典型的な違反事例で、特別なポイントはありませんが、価格は消費者が特に気にするものです。そのため、すぐに発覚しますし、消費者庁は今も厳しい対応をしています。
| ・二重価格表示をするときは、常にルールを確認して表示することが必要 |
⑺ 株式会社ドミノ・ピザジャパンに対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年6月27日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 宅配ピザ業者 |
| 商品/サービス | ピザなど(食品) |
| 広告の種類 | チラシ |
| 広告の期間 | 2022年10月~2023年4月(全体) |
| 違反行為 | 有利誤認表示 |
| 資料提出 | - |
② 表示内容と適用法令
7号案件は、有名な宅配ピザ業者の価格表示に対して消費者庁が行った処分で、6号案件に続き有利誤認表示の事案です。
媒体がチラシだったことが話題になり、ニュースにもなった事案ですが、チラシに表示された価格やそこからクーポン割引を受けた価格で購入できるように表示していた価格表示が問題になったものです。
消費者庁は、実際には、この表示に加え、サービス料が加算されるものであり、チラシに掲載された価格表示は、有利誤認表示と認定しました。
③ コメント
このケースは、(二重価格表示ではなく)商品の販売価格を一つだけ(単体で)表示する場合のルールです。このルールは、非常にシンプルで、実際の販売価格を正確に表示する、というただそれだけのものです。つまり、事業者は、実際に消費者が支払う総額を正しく表示することが求められます。
最近では、特定商取引法の改正により、通信販売ではそのような価格を正確に表示することが求められています。本件は、チラシだったということもあり、特商法の通信販売の対象外ですが、景品表示法のルールはチラシにも適用されます。
なお、消費者庁は、全国の約1000店舗の、半年間のチラシを詳細に検討しており、大変な労力をかけた事案だったと思われます。
| ・価格表示をするときは、消費者が実際に支払う金額を正確に表示する ・特商法の対象になる媒体以外でも景品表示法は適用されるので注意する |
⑻ さくらフォレスト株式会社に対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年6月30日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 食品メーカー |
| 商品/サービス | (機能性表示食品) |
| 広告の種類 | 容器包装、パンフレット、自社ウェブサイト |
| 広告の期間 | 2022年6月8日~2023年5月16日(非連続) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり→合理的根拠と認められず。 |
② 表示内容と適用法令
8号案件は、機能性表示食品に対して消費者庁が行った処分です。
問題になった表示は、本商品を摂取すると、血圧を下げる、酸化LDLコレステロールを減少させる、中性脂肪を低下させる、とする食品の効果に関するものです。
本製品は機能性表示食品に分類されるので、問題になる法令は景品表示法の優良誤認表示のほか、薬機法の医薬品的表示の禁止、健康増進法の虚偽誇大表示の禁止が問題になります。
事業者は資料を提供しましたが、資料では、そのような効果が認められなかったものです。
③ コメント
8号案件は、食品のなかでも「機能性表示食品」が対象になりました。
機能性表示食品は、保健機能食品の一つで、特定保健用食品(トクホ)とは、国の許可は不要(届出のみ)なことが異なります。
保健機能食品は、例外的に、広告のなかで特定の機能(効果)を表示できます。
※一般食品の場合は、たとえ一定の効果があっても、その効果を表示できません。
ただし、機能性表示食品は、トクホとは異なって国の許可が不要なので、事業者の判断で販売し、効果を表示できます。それだけ、事業者には重い責任があります。
本件の商品は、資料によっても表示された効果が認められなかったとされていますが、「機能性表示食品」は、一般消費者に対して「通常の食品よりも身体によさそう」という強い印象を与えので、本当にその効果があることを資料で説明できるようにすることが大切です。
機能性表示食品(つまり、国は許可していない)にもかかわらず、「国が認めた」などと虚偽の広告を目にすることも多いので、広告には注意が必要です。
| ・機能性表示食品の機能は、表示することを裏付けるエビデンスがあるのか慎重に判断することが必要 |
⑼ 沖縄特産販売株式会社に対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年7月26日 |
| 処分 | 課徴金納付命令(2464万円) |
| 事業者 | 食品等の販売会社 |
| 商品/サービス | 食品(摂取、噴霧) |
| 広告の種類 | ダイレクトメール、商品同梱チラシ |
| 広告の期間 | 2019年5月7日~2021年4月4日 |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | なし |
② 表示内容と適用法令
9号案件は、8号案件に続いて食品に関する事案で、「養力珪素」と称する食品に対して消費者庁が行った処分したものです。
ダイレクトメールと製品に同梱したチラシに、この食品を摂取・噴霧すると、血液をサラサラにする効果、高血圧・高血糖・糖尿病を改善する効果、シミ・シワ・イボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果など、多数の効果が得られるかのような表示が問題にされたものです。
事業者は資料の提出をせず、消費者庁は、事業者が表示した内容を優良誤認表示と認定しました。
③ コメント
食品の広告では、効果の表現が厳しく制限されています。食品の効果は、健康増進法で8種類の「健康保持増進効果等」に分類されていますが、保健機能食品ではない一般食品では、このうちの4つの内容しか表現できません。
また、医薬品のような、病気を治したり、身体の機能を高めるような効果の表現は薬機法で禁止されています(未承認の医薬品の広告になります)。
この事例は、健康増進法や薬機法にも同時に違反している典型的なケースです。
なお、本件は広告の方法がダイレクトメールとチラシのみで、インターネット広告と比べると、広告にふれた人の数は多くないと思われますが、消費者庁はそのようなケースにもしっかりと対応していますし、販売期間が約3年間であったことから課徴金額も高額になっています。
| ・改めて、食品広告における効果の表現には注意すること ・医薬品的表現は絶対にしてはいけないこと |
⑽ 北海道電力株式会社に対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年7月28日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 電力会社 |
| 商品/サービス | 家庭用の電気・都市ガスの小売供給 |
| 広告の種類 | 検針票とセットで配布したリーフレット、チラシ |
| 広告の期間 | 2020年12月3日~2021年12月3日(全体) |
| 違反行為 | 有利誤認表示 |
| 資料提出 | - |
② 表示内容と適用法令
10号案件は、電力契約とガス契約のセット契約の価格表示に対して消費者庁が行った処分で、2023年度2件目の有利誤認表示の事案です。
リーフレットや未契約の消費者へのダイレクトに添付したチラシのなかで、「おトク」と記載した金額を表示し、都市ガス契約を別会社から切り替えて電力契約とセットで契約するだけで、電気料金とガス料金の合計額において「おトク」と記載された金額相当の利益が得られるような表示をしていたことが問題とされたものです。実際には、ポイントサービスに加入して毎月のログイン等をしなければ付与されないポイントが含まれており、契約しただけでは利益を得られないものでした。
景品表示法の第5条第2号では、6号案件のように複数の価格を表示する場合のルール(二重価格表示)のほか、単体で価格を表示する場合のルールや、価格以外の取引条件に関するルールもあり、本件は、この「価格以外の取引条件」が問題になりました。
消費者庁は、事業者が表示した内容を不当なものとして有利誤認表示と認定しました。
③ コメント
有利誤認表示では、複数の価格を表示する場合の違反事例が比較的多いため、二重価格表示に関する認識は少しずつ定着しているように思います。しかし、価格以外の取引条件にもルールがあります。本件は、この「価格以外の取引条件」を表示する場合のルールに違反したケースです。
景品表示法の有利誤認表示に関する運用基準などは、価格に関するルールが中心となっていて、本件のような「価格以外の取引条件」については詳細な説明がありません。しかし、それは、基本的な考え方が共通するためです。
景品表示法の基本的な考え方は「事実を正確に表現する」ということです。そのため、「価格以外の取引条件」についても、価格と同じく、消費者に誤解させないように「事実を正しく伝えること」が必要になります。
今回のケースで参考になるのは、単体で販売価格を表示する場合に注意が必要なケースである「表示された販売価格は特別な条件を満たす場合だけなのに条件を表示しない場合」です。これを「価格以外の取引条件」の場合にすると、「表示された取引条件は特別条件を満たす場合だけなのに、その条件を表示しない場合」になります。
本件の広告で「おトク」と記載された消費者のメリットは、「価格以外の取引条件」です。消費者側からすると、この契約をすると、この「おトク」が手に入ると思うためです。
今回の表示は、契約をするだけで「おトク」が手に入ると思わせるものでしたが、実際には、ポイントサービスに加入するなど、いくつかの条件を満たさないといけないものでした。その点が不明確であったため、この表示は「有利誤認表示」と判断されてしまいました。
現在、電力契約や携帯電話契約などでは、様々な取引条件が付いており、非常に複雑です。事業者は、様々な工夫をすることで、消費者にメリットがある取引条件を付けることも一般的です。しかし、その場合は、「そのメリットが手に入るための条件を正確に明示すること」が必要です。
| ・価格以外の取引条件をつけるときは、その取引条件が叶うための特別な条件を正確に表現する。不正確に表現して、消費者を「エサで釣る」ようなことはしないこと |
⑾ 株式会社バンザンに対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年8月1日 |
| 処分 | 課徴金納付命令(6346万円) |
| 事業者 | 教育事業会社 |
| 商品/サービス | オンライン個別学習指導サービス |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、パンフレット、YouTube動画広告 |
| 広告の期間 | 2022年4月4日~7月19日 |
| 違反行為 | 優良誤認表示、有利誤認表示 |
| 資料提出 | なし |
② 表示内容と適用法令
11号案件は、オンラインを利用した教育事業を行う対象事業者の表示に対して、優良誤認表示と有利誤認表示の2つを認定して処分した事案です。
※同一案件に対して、本年1月に既に措置命令が出されていますが、改めて課徴金納付命令が出されたものです。
まず、「利用者満足度や口コミ人気度などが1位」という表示は、調査会社が行った調査が、対象事業者のサービスと競合事業者のサービスを利用したユーザーを対象にした客観的な調査ではなかったので、優良誤認表示とされました。
また、「一定の期限までの申込みをした場合と入会前の面談を受けた場合に限って返金保証制度が利用できるような表示」と、「一定の期限までの申込みをした場合に限って追加授業を受けられるような表示」は、実際には、期限後に申し込んだ場合も同じ制度を受けられたため、有利誤認表示とされました。
対象事業者は、業者の調査の裏付けとなる資料の確認をしていなかったとされ、優良誤認表示について課徴金対象行為とされました。
③ コメント
ⅰ 優良誤認表示について
5号案件と同じく、調査情報が問題になったケースです。消費者庁は、調査会社を利用した「満足度1位」「人気ナンバーワン」といった表示に対して、注目していることがわかります。
このような広告は、インターネット広告を中心に広く行われていますし、口コミと並んで、高い広告効果もあります。一般消費者は、買うかどうかを決めるときに、他のユーザーが実際に使った体験に注目しますし、最近始まったステルスマーケティング規制も、そのような消費者の意識を裏切る行為に対しては、厳しく規制していますので、ルールが共通しています。
調査情報に関するルールは5号案件でも解説していますが、新しいルールではありませんし、表示内容を正しく裏付ける調査に基づいて広告しなければいけません。
そして、この事案は、対象事業者のサービスと競合事業者のサービスを利用したことがないユーザーを対象に調査していたという点で、非常に杜撰な調査であったと思われますし、その調査を鵜呑みにしてしまった対象事業者に対しても、消費者庁は裏付け資料を十分に確認しなかった点を指摘しています。
本当に消費者から支持されているのであれば、その事実を正確に伝えることは全く問題ありません。調査情報を活用するときは、
・調査会社が信頼できるところかどうかを確認
・調査情報を裏付ける資料があるかどうかを確認
⇒資料が無い場合は調査情報を使わない
⇒資料がある場合にも、内容を冷静にチェック
することが大切です。
ⅱ 有利誤認表示について
有利誤認表示は、10号案件と同様に「価格以外の取引条件」に関するものです。
消費者に魅力ある特定の制度について、「一定の時期までに申し込まなければ利用できない」という表示は、これまでにも多くの違法事例があります。
対象事業者はその制度をしっかりと実施していて、利用者もそのサービスを受けることができたので、一見、不利益は無いようにも見えますが、「急がないと制度を利用できない」と思わせてしまい、その結果、契約した消費者がいる場合は、厳しく判断されます。
| ・調査情報を利用した広告をするときは、信頼できる調査会社かどうかを確認することが必要 ・調査結果を鵜呑みにせず、裏付け資料の提出を求め、資料内容を確認することも重要 ・商品やサービスに、期間を限定したり、対象者を限って特別なオプションを付けるときは、その期間や対象者を守ることが必要。通常のサービスを、期間限定のものや特定の人に限定であるかのような表示はしないこと |
⑿ 中国電力株式会社に対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年8月30日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 電力会社 |
| 商品/サービス | 家庭用の電気の小売供給 |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、パンフレット |
| 広告の期間 | 2022年4月1日~2023年1月12日(全体) |
| 違反行為 | 有利誤認表示 |
| 資料提出 | - |
② 表示内容と適用法令
12号案件は、10号事案と同じく、大手の電力会社に有利誤認表示として措置命令が出された事案です。
対象事業者は、自社のスタンダードなコースと比較して、自社の別コースのほうが電気料金が安価であるような表示をしたものの、実際には安価にならない場合があったとされ、有利誤認表示になりました。
景品表示法の第5条第2号では、6号案件のように複数の価格を表示する場合のルール(二重価格表示)のほか、単体で価格を表示する場合のルールがあり、本件は単体での価格表示が問題になりました。
③ コメント
有利誤認表示では、二重価格表示のルールが複雑なので、どうしてもそちらにばかり意識がいきがちです。でも、単体の販売価格に関するルールにも注意しましょう。
「単体の販売価格」に関するルールでは、
ⅰ 実際の販売価格より安い価格を表示する場合
ⅱ 実際には商品価格以外の費用が発生するのにそのことを明示しない場合
ⅲ 表示された価格は特別な条件を満たす場合なのにその条件を明示しない場合
の3つが特に重要です。
本件は、最も基本的な1番目のルールに違反したものです。
おそらく、対象事業者もルールを知らなかったわけではないと思います。その理由は、本事案で「安価にならない場合があった」と認定されているように、別コースのほうが、スタンダードなコースよりも安価になるケースが多かったように思われるためです。
しかし、広告の内容が、消費者に対して「必ず安くなる」ような印象を与えてしまう場合は、その数が少なくても安価にならない場合があるかぎり、実際とは異なる表示となってしまい、有利誤認表示になります。
対象事業者は、ほとんどのケースでスタンダードコースよりも別コースのほうが電気料金が安くなることを認識して(問題となった)表示をしたものの、「実際には安価にならないケースが発生してしまった」という可能性があったように思います。
より詳細に検討しておけば、安くならない場合ケースがあることに気づき、「絶対に安くなる」ような広告を回避できたと思われます。
この事例からは、
・電気料金のように、消費者の利用状況等によって料金が変動するものは、詳細なシミュレーションをしないと安価になるかどうかが判断できない可能性があること
です。
このように、その判断を確実にできないときは、「利用状況によっては安価にならない場合があること」などをわかりやすく明記するなど、消費者が誤解しないような表示にしておくことが必要です。
| ・利用状況などで価格が変動する場合には、詳細なシミュレーションを事前に実施して確信できない限りは、「絶対に安くなる」かのような表示はしないようにすること・ケースによって変わり得る場合は、消費者を誤解させないように、その点を明記すること |
⒀ マルキユー株式会社に対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年10月5日 |
| 処分 | 課徴金納付命令(1774万円) |
| 事業者 | 釣具メーカー |
| 商品/サービス | 疑似餌(ぎじえ) |
| 広告の種類 | 商品パッケージ、自社ウェブサイト、販促ツール、会報、小冊子、カタログ |
| 広告の期間 | 2016年4月1日~2023年2月20日(全体) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり →表示を裏付ける合理的根拠ではない |
② 表示内容と適用法令
この案件は、釣具メーカーが製造する疑似餌(魚の餌に似せて作られた人工の餌)に関する表示が問題になり、課徴金納付命令が出された事案です。
広告をした事業者は、本製品には、使用後に水中に残っても、水中の微生物によって分解される性能(生分解性)があることを表示していましたが、この性能があることの裏付けがないものとして優良誤認表示になりました。
③ コメント
本事案はごく一般的な優良誤認表示の事案で、特徴はありません。ただし、事業者のカタログには、事業者がフィールドにおいて生分解性の経過を観察し記録していたことが記載されています。「生分解性…の調査報告」と題され、執筆者が事業者の研究開発課の従業員であり、具体的な場所、測定の頻度、水と二酸化炭素に分解されていったこと、分解までの期間にも述べられています。
公表内容によれば、事業者は根拠となる資料を提出したということですが、その内容は不明なものの、おそらくこのカタログに記載された調査内容に関連するものだったと思われます。もっとも、消費者庁からは合理的な根拠ではないと判断されています。
本製品のように、特殊な性能(生分解性)を有するとされ、広告などでも、その特殊な性能をアピールする場合は、消費者にとっても、この製品の購入を決めるうえで重要なものとなります。自然環境を大切にしたい釣り人からすれば、自然に分解される本製品は魅力的なものだったと思われます。
特殊な性能をアピールする場合には、その性能を裏付ける合理的な資料が必要になります。
| ・特殊な性能をアピールする場合には、その性能を裏付ける科学的な資料などを必ず備えておくこと ・科学的な資料などの裏付けがなかったり不足している場合は、その性能を表示しないこと |
⒁ 糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年10月31日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | ①広告代理店、販売代行、動画制作会社 ②家電メーカー ③家電メーカー ④貿易会社 |
| 商品/サービス | 炊飯器 |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、新聞広告、動画、プレスリリース配信サービス |
| 広告の期間 | ①2022年9月28日~2023年2月6日(全体) ②2022年10月18日~2022年12月6日(全体) ③2022年9月29日~12月21日(全体) ④2021年8月1日~12月21日(全体) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり →表示を裏付ける合理的根拠ではない |
② 表示内容と適用法令
事業者の業種は様々ですが、4つの事業者が広告をしていた電気炊飯器の表示が問題になったケースです。いずれの事業者も、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりでありながら、この炊飯器で炊くと、糖質(でんぷん)が5割程度カットできるように表示していましたが、そのような性能の裏付けが無いとして、優良誤認表示になりました。
③ コメント
本事案もごく一般的な優良誤認表示の事案です。
※なお、糖質カット炊飯器については、2024年にも、別の4事業者に対して措置命令が出されています。
結局は、その性能を裏付ける合理的な根拠がないのに表示をした、という一言に尽きるのですが、この炊飯器のターゲットが、消費者の健康意識やダイエット願望にあったことは明らかで、このような表示をすることで、消費者の大きな注目を集めることができるものの、根拠がないというのは、結局は、消費者を騙しているのと同じことです。
上記の各事業者の表示時期を見ても、かなり重なっていることが分かるように、これらの事業者は、他社製品が売れているのを見て、真似して販売をしたように思われますし、とても独自に実験や検証をしたうえで製品を開発し、そのうえで表示をしているのか疑問です。
売れればよいのではなく、良い製品を売るというのがビジネスの原点ですし、広告というのも、その延長にあるものです。事業者が良いものかどうかわからないままに、良いものとして販売しているのであれば、消費者が「詐欺だ」と考えるのも当然ですし、広告ルールはさらに厳しくなっていくだけです。
細かなルールはたくさんありますが、優良誤認表示は、ビジネスの鉄則を守っていれば、違反するはずもないものです。
なお、措置命令では、事業者4社に対し、この表示が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底するよう求めています。しかし、現時点でこの公表を確認できるのは3番目の会社だけであり、ほかの3社は周知徹底をしたのかどうかも不明ですし、仮にしたとしても、すぐにその周知を抹消したものと思います。その場合は、そもそも「周知徹底」に該当するのか疑念ですが、それ以上に、自社に都合の悪い内容はすぐに抹消してしまうようでは、今後も同様の表示をするように思われても仕方がないですし、本年の景表法改正により、違反を繰り返す事業者への重罰規定が設けられていることを認識することが必要かと思います。
| ・自社で把握していないような性能表示はしないこと。優良誤認表示はそれだけで十分に回避できる ・措置命令で消費者への周知徹底が命じられた場合は、正しく従うこと |
⒂ レック株式会社に対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年11月22日 |
| 処分 | 課徴金納付命令(669万円) |
| 事業者 | 洗剤等の家庭用品メーカー |
| 商品/サービス | 除菌製品 |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、新聞広告、動画、プレスリリース配信サービス |
| 広告の期間 | 2019年11月28日~2020年10月28日(全体) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり →表示を裏付ける合理的根拠ではない |
② 表示内容と適用法令
対象事業者は、知名度の高い清掃用品を多く取り扱う大手メーカーですが、問題となったのは、他にも複数の違反事例が生まれた除菌製品に関する表示です。表示内容も、ウイルスに対する除菌効果であり、共通しています。
この事案でも、合理的根拠が無いものとして優良誤認表示となりました。
③ コメント
除菌製品に対する先行した案件と同様であり、法的には、ごく一般的な優良誤認表示の事案です。
なお、この業者も、消費者からも支持される多数の優良製品を販売してきた実績のある業者であり、2021年に受けた再発防止命令に対して取消訴訟を提訴した対応を見ても、何の検証もせずに販売したものではないと思われます。
結局、表示を裏付ける合理的な根拠の内容が問題となるのであり、消費者庁は、厳格なものを求めていることが伺えます。
| ・合理的な根拠になりうるか、製品の性能を裏付ける資料内容の検討は徹底的に慎重に行うべき |
⒃ 株式会社アリュールに対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年12月5日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | ECサイト運営業者 |
| 商品/サービス | 機能性表示食品 |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、外部ウェブサイト |
| 広告の期間 | 2023年3月10日~2023年8月22日(全体) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり →表示を裏付ける合理的根拠ではない |
② 表示内容と適用法令
対象事業者は、ECサイト運営やサイト制作を行っていた事業者のようですが詳細は不明です。ただ、機能性表示食品に関して、痩身効果を謳ったよくある事案であり、合理的根拠が無いものとして優良誤認表示となりました。なお、この事業者は、そのほか、消費者庁が認定した機能性表示食品などを記載した点については、消費者庁は、そのような事実はないことを明示しています。
③ コメント
痩身効果を謳って優良誤認表示となるケースは非常に多く、本案件も同様の事案です。繰り返しになりますが、食品広告において、瘦身効果を謳うことは医薬品的表示として薬機法にも違反しますし、機能性表示食品のような保健機能食品の場合でも、食品広告では絶対にできない表現です。
また、この事案で指摘されている「消費者庁が認めた」といった表現は、類似の表現をよく目にするものの、機能性表示食品は届出による制度であり、消費者庁のような国の官庁が認めるということはあり得ません。明白な虚偽表示となりますので、注意が必要です。
なお、対象事業者は、本命令の1週間後に破産手続開始決定を受けているようです。
| ・食品広告で「痩身」「痩せる」は絶対にしてはいけない ・機能性表示食品の広告で「国が認めた」表示も虚偽表示になる |
⒄ 株式会社ハハハラボに対する措置命令事案
① 事案の概要
| 公表年月日 | 2023年12月19日 |
| 処分 | 措置命令 |
| 事業者 | 化粧品等の販売会社 |
| 商品/サービス | 機能性表示食品 |
| 広告の種類 | 自社ウェブサイト、外部ウェブサイト |
| 広告の期間 | 2023年3月10日~2023年8月22日(全体) |
| 違反行為 | 優良誤認表示 |
| 資料提出 | あり →表示を裏付ける合理的根拠ではない |
② 表示内容と適用法令
対象事業者は、化粧品などをECで販売している業者で、アリュールに対する事案と全く同様に、痩身効果を謳った機能性表示食品の広告が優良誤認表示となったケースです。
また、この案件でも、調査情報が問題となっています。調査結果において本製品が「第1位」であるような表示をしたものの、客観的な調査に基づくものではなかったとして、優良誤認表示だと認定されています。
③ コメント
痩身効果に関することはアリュールに関する事項と同じなので省略します。
調査情報に基づく「第1位」表示、「No1」表示ついては、その後も同様の摘発事例が相次いでいます。
4 景品表示法の違反を防ぐためには?
⑴ 景品表示法やガイドラインの内容を社内で周知する
景品表示法違反を防ぐためには、ガイドラインを含めたルールを社内で理解し、また、広告物を社内でチェックできる体制を作ることが必要です。
ただ、ガイドラインの内容も膨大で、医薬品や化粧品、食品のように、景品表示法以外にも広告ルールが別途存在するものもあります。また、法改正も頻繁にあるため、これを常にキャッチアップできるようにすることも必要です。
近年は、Webマーケティングの飛躍的な発達と、それに伴う広告違反事例の増加から、社内でのコンプライアンスでも不可欠のものとされ、証券取引所の上場審査でも広告審査体制の有無が厳しく求められています。
我々のような広告ルールを扱う弁護士などの外部専門家に頼るだけでなく、社内における体制の構築が強く求められています。
⑵ 違反事例のチェック
本稿でも、最新の違反事例を紹介し、そのポイントや、防止するための注意点を解説していますが、最新の違反事例をチェックすることは、監督官庁の最近の関心がどこにあり、ミスをしやすい盲点はどこにあるのか、社会情勢の変化のなかで新たな問題点があるのかなどを知る機会にもなりますし、他人の失敗から学ぶことは実際の事例を素材にした学習ができるため、検討する素材としては極めて有益です。
本稿では、今後も、定期的に最新事例をアップデートしますが、定期的な情報収集が必要になります。
⑶ 外部専門家のサポート
上記のように、景品表示法を始めとする広告ルールの理解が不可欠としても、専門的 な内容も含まれるため、社内だけで判断できない場合や、適法でありながらも、より広告効果の高い表現にするためには、外部専門家のサポートも必要になります。
景品表示法違反は大きなペナルティになるので、少しでも不安があれば、広告ルールに詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
GVA法律事務所では、執筆者を始め、広告ルールに精通した専門家により、これまでにも多くの事業者のサポートをしております。化粧品や食品など、複雑な広告ルールを分かりやすくまとめた書籍も出版し、好評をいただいています。
書籍名:Q&Aでわかる 医薬品・美容・健康商品の「正しい」広告・EC販売表示
出版社名 :技術評論社
発行年月日 :2023年9月16日
編著者 :早崎 智久 弁護士、五反田 美彩 弁護士
また、サポートでは、社内体制において必要になる広告ルールを効率的に確認するためのツールと、最新のルールや基本的な事項などを月例で解説するセミナーもセットで、ご利用しやすい価格でご提供しています。
◎GVA法律事務所によるサービス
- 広告の表現のチェック、違法な場合の代替表現の提案
- マーケティング企画のチェック
- 社内での研修、研修資料の作成
- 広告チェックのためのマニュアルの提供
- 広告ルールに関する定例セミナーの開催
- 社内体制の構築のサポート
社内体制の構築や日常的な広告チェックにお悩みの事業者の方がいれば、まずは、お気軽にお問い合わせください。
5 まとめ
本稿では、景品表示法のルールの概要、違反した場合の罰則等を踏まえ、2023年度の違反事例の解説をしています。
景品表示法を始めとした広告ルールは、近年、厳しい規制が相次いで導入されていますが、基本的な考え方に変更はありません。社内で広告審査ができる体制を設け、外部専門家のサポートが受けられるようにすることで、十分な対策を立てることができます。
事業者の素晴らしい商品やサービスを多くの人に伝えるために広告があり、事業活動には不可欠なものですが、ルールを守ることで、本当に価値のある広告をすることができます。ルールの理解を深めながら、新しいマーケティング活動を行っていくことが、永続的な事業活動をするために大切です。