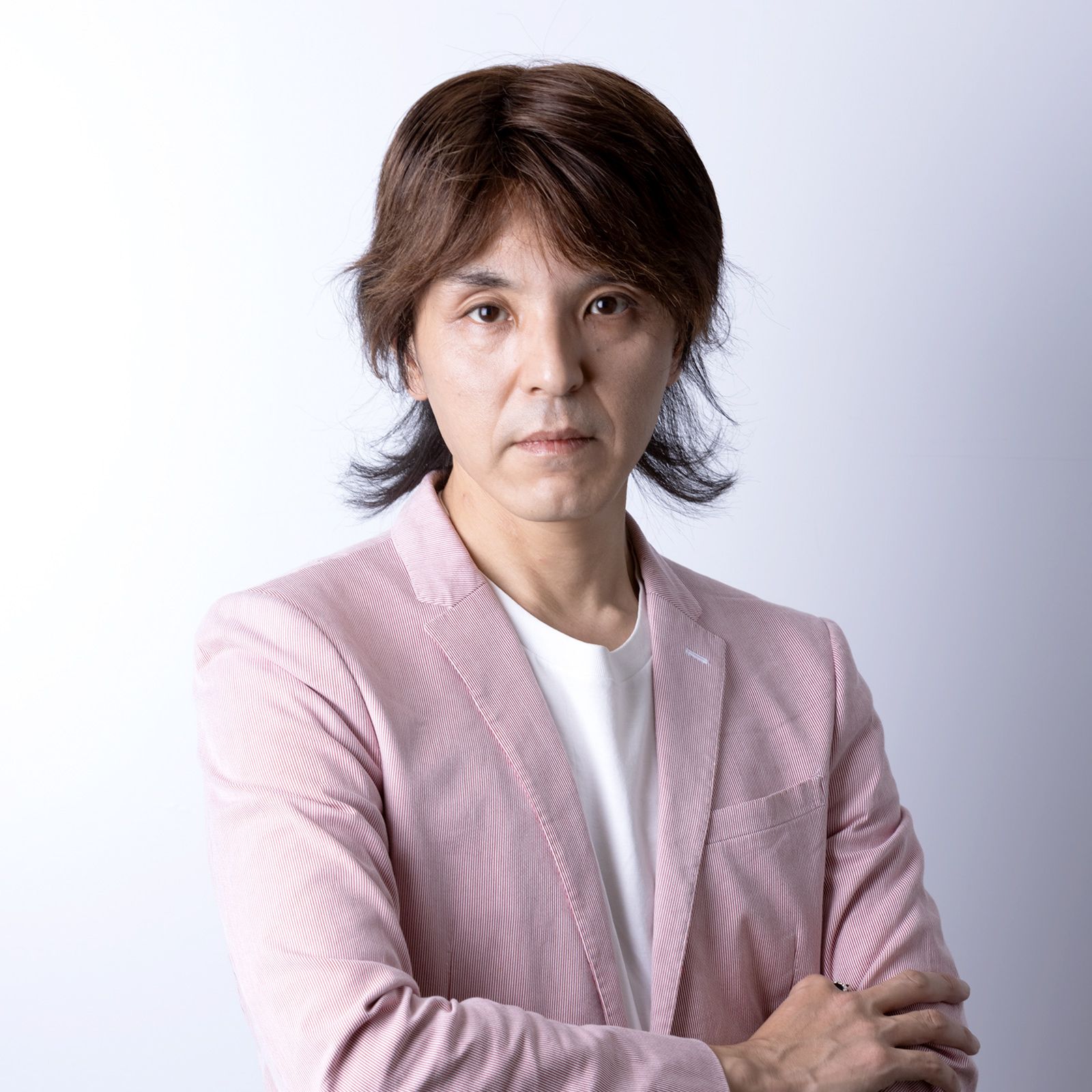執筆:弁護士 早崎 智久、弁護士 山本 大介(メディカル・ビューティー・ヘルスケアチーム)
(※2023年5月30日に記事内容をアップデートいたしました。)
1.はじめに
商品としては医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品・サプリメントなど、サービスとしては医療機関、整体などの医療隣接業、美容エステなど、世の中にメディカル・美容・ヘルスケア分野の商品・サービスは数多く存在します。
それらの商材を取扱う際には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」、「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」をはじめ、「医療法」、「医師法」、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」など、商材ごとに様々な法律の規制を受けます。
そのうち薬機法では、令和3年8月1日に「薬機法等の一部を改正する法律」の一部が施行され、「広告規制違反に対する課徴金制度の導入」がなされ、違反広告に対するサンクションが強化されています。
そこで、GVA法律事務所として、本連載では、メディカル・美容・ヘルスケア分野の商品・サービスを取扱うにあたってどのような広告が違法とされ、どのようなサンクションが課されるのかについて、問題となった具体的な事例を元に、適用される法律及びそのサンクションを、定期的にご紹介いたします。
第1回目は、ステルスマーケティングに関して違反となった事例を扱います。
2.ステルスマーケティングによる初の違反事例
(1)事例の概要
令和3年、インスタグラムの利用者に対して商品サンプルを配布し、「バストアップ」というハッシュタグを付けて投稿することを依頼していた事業者が景表法上の措置命令を受けました。
(2)適用された法律
景表法は、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示をしてはならない」(第5条柱書、第1号)と規定し、不当な表示を禁止しています(優良誤認)。
景表法に違反した事業者に対しては、行為の差止めや再発防止策に関する事項の公示等の措置命令(第7条)がなされる可能性があります。また、違反行為によって得た売上に対して課徴金納付命令(第8条)がなされる可能性もあります。
さらに、措置命令等に違反した場合、刑事罰(第36条乃至第41条)に処せられる可能性もあります。
(3)事例の解説
① ステルスマーケティングとは
まず、ステルスマーケティングとは、広告を閲覧する消費者に対して、広告であることを明記せず、むしろ広告ではないように見せかけて、消費者を欺いて広告を行う宣伝手法のことをいいます。最近よく見られるやり方としては、高評価の口コミであるように装うことですが、昔からも、「やらせ」や「サクラ」といった方法で行われています。
② ステルスマーケティングに対する法規制
英語圏では、アンダーカバー・マーケティング(英: Undercover Marketing)と呼ばれるゲリラ・マーケティングの1つとして認知されており、EU指令や米国連邦取引委員会法では、『消費者に対する不公正な欺瞞に当たる行為』として、明確に禁止されています。
そして、日本では、内閣府の告示により、令和5年10月1日から明確に規制されることとなりました。告示自体はわずか数行ですが、同時に公表された運用基準を併せて参照することで、どういったものがステルスマーケティングに該当するのかが詳細に分かります。これまでも典型的なステルスマーケティングの事例であると考えられていた、①事業者の広告であるにもかかわらず、広告であると分かりにくいものというケースはもちろん、②事業者と一体的な地位にある従業員による自社商品やサービスの広告であるにもかかわらず、広告であると分かりにくいものや、③事業者が広告代理店やインフルエンサー等の第三者に依頼して作成された広告であるにもかかわらず、広告であると分かりにくいものについてもステルスマーケティングに該当することが示されました。
②については、事業者と一体的な地位にあるかどうかは、役職や担当する業務の内容等種々の事情を考慮して判断されることとなりますが、極端にいえば、従業員により自社の商品をおすすめする投稿がステルスマーケティングに該当すると認定されてしまうリスクがあるということを意味します。
そのため、事業者としては、従業員によるSNS利用の管理の重要度が一層増したと言ってよいでしょう。
また、③については、事業者が広告代理店に広告内容を一任した場合にも適用される場合がありますから、十分な注意が必要です(令和5年10月施行のステルスマーケティング規制については、弊所記事「ステルスマーケティング規制の解説」をぜひご覧ください。)。
加えて、これまでに刑事事件となったものの報告はないものの、上記の景表法の罰則のほか、軽犯罪法第1条34号に「公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者」と明記されており、ステルスマーケティングは、これに該当することがあり得るため、悪質な事案に対しては、今後、景表法だけでなく軽犯罪法が適用される可能性は十分にあると思います。
③ 本事例について
消費者庁は、本商品サンプルについて、実際に宣伝効果が認められないと判断しました。そのため、この事業者は、商品サンプルについて実際に宣伝効果が認められないにもかかわらず、他の商品よりも優良である旨消費者を誤認させたとして、再発防止を求める措置命令を受けました。
本事例は、事業者が直接行った表示ではなく、インスタグラマーを使ったステルスマーケティングにおいても、景表法上の責任を問われるという点で、初めての違反事例となります。
昨今は、インフルエンサーを使った広告手法も主流になっています。しかし、インフルエンサーによる広告であっても、実際には事業者の広告と見做されることにより、事業者が景表法上の責任を問われ得るため、インフルエンサーを含めた委託先の表示内容についても法律に違反していないかどうかきちんと管理することが必要となります。
あわせて、消費者庁は違反の可能性のある表示を発見した際、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることがありますが(第7条第2項)、これに対応できるよう、きちんと表示に関するエビデンスを確保しておくことも重要となります。
3. 本事例から学ぶポイント
① 広告自体はインスタグラマーが行っていても、依頼した事業主の広告と見做される
② ステルスマーケティングは「適法」という認識は誤り
③ ステルスマーケティングは、令和5年10月から明確に規制されることとなった
4.終わりに
商品やサービスについて適法に提供するためには、景表法やその他の法律をきちんと把握し、遵守する必要があります。自社の商材がどの法律の適用を受けるのか、当該法律に違反しないためにはどのようなことに気を付ければいいのか、事業者の方々が気を付けるべきことはたくさんあります。
GVA法律事務所では、事業者において景表法その他関連法規に違反しない広告物を作成するための体制整備のサポート、作成された広告表現に対する弁護士によるリーガルチェックの予防法務から、実際に違反してしまっていた場合の行政対応を含めた事後対応まで、全面的にサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2022年2月28日 公開
2023年5月30日 更新