
執筆:弁護士 森川 そのか( AI・データ(個人情報等)チーム )
1. はじめに
AI技術の進化により、多くのビジネス分野でのAI導入が加速しています。AI導入は、業務効率化や新たなビジネス価値の創出に寄与する一方で、法的な課題も多く存在します。本記事では、法律事務所の視点から、企業がAI導入を進める際に注意すべき法的観点とビジネス展開のポイントについて解説します。
本記事が、貴社が安心してAIをビジネスに取り入れ、競争力を高めるための一助となりましたら幸いです。
2. AI導入のメリットと課題
メリットの概要
AI導入は、業務効率化、コスト削減、顧客満足度の向上など、多くのメリットをもたらします。例えば、製造業では生産プロセスの最適化、小売業では顧客データ分析を通じてパーソナライズされたサービス提供等が挙げられます。AI導入によって、企業が競争優位性を得られる可能性が高まります。
業種別の事例
具体的な導入事例を一部紹介します。
小売・飲食: 需要予測や価格の決定・調整、チャットボットやロボットによる接客などがあります。例えば、築地すし好はポケトークを導入し外国人の接客に役立てています(※1)。また、焼肉きんぐはアイリスオーヤマの配膳ロボットServiを用いて接客や配膳等を効率化しています(※2)。
(※1)https://pocketalk.jp/column/case-study/sushiyoshi
(※2)https://www.irisohyama.co.jp/b2b/robotics/case-studies/servi/case001/
製造・メーカー: 不良品の検知や製品の設計・デザイン、工場でのロボット操作などが挙げられます。例えば、キューピー株式会社では製造ラインにて株式会社ブレインパッドの機械学習AIを導入し、原材料の不良品検知に役立てています(※3)。
(※3)https://www.brainpad.co.jp/doors/contents/02aidevelopmentstorykewpie/
金融・保険:クレジットカードの不正検知、保険料の最適化などがあります。例えば住信SBIネット銀行では、不正送金対策のAIモニタリングシステムを自社開発し、不正取引に係る判断の高速化・効率化を試みています(※4)。
(※4)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000037968.html
3. 導入の流れ
AI導入プロセス
AI導入にあたっては大まかに以下のプロセスを経ることになります。
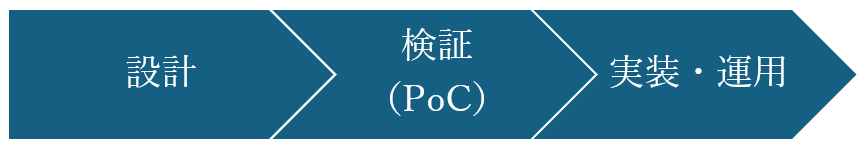
【設計段階で行うこと】
①AI導入の特定・目標設定
従来の業務課題を洗い出し、業務のどの部分にAIを導入するかの検討・決定
達成したい成果(例:業務効率化、コスト削減、顧客満足度向上など)の具体化
業務プロセスの見直し(例:発注業務の精度を上げたい場合、現状の発注は毎月いつ頃に誰が行っており、それにかかる工数がどれくらいなのか等を把握。)
②データの確認
必要なデータの定義・特定・収集/手元にあって利用可能なデータの確認
利用予定のデータの品質確認
データの取得・利用における法的規制(個人情報保護法、GDPR、など)の確認・遵守
③実務での活用イメージ検討
AIに予測してほしい集計期間、粒度、タイミング等を検討
複数のAIソリューションを比較(上記によってどのソリューションにするかが決まる。)・内製か外部ベンダーの利用か等の決定
最初に設定した目標と選定したAIによる実現可能性の評価
④初期費用の検討
検証期間の設定(2~3カ月程度で終える計画が望ましい。)
検証に必要な初期費用の見積
予想される法的又はその他のリスクについてリストアップとそれらの解決のための費用の算定
【検証(PoC)段階で行うこと】
⑤モデル構築・検証・最適化
モデル構築(適切なデータ選定、準備)/精度検証/チューニング
モデル最適化
法的又はその他のリスクの程度の検討
⑥業務への適用可否検討
業務プロセスの再設計
内部監査・外部監査を通じたリスク管理
継続的な法的コンプライアンスの確保
⑦本番実装計画の策定
AIが創出する価値、AI導入・運用に係るコストの試算
契約書におけるデータ所有権や知的財産権の明確化/ベンダーとの契約条件の確認と交渉
【実装・運用段階に行うこと】
⑧業務への活用・システム実装
現場へのモデル導入
社内ガイドライン等の作成・業務プロセスの変更・従業員のトレーニング
対外的な説明
⑨AI制度モニタリング・再学習
AI予測精度の定期モニタリング
モデルの再学習・再構築
法的リスクの発現可能性の確認
これらのステップを踏むことで、企業はAIを効果的にビジネスに導入することが可能です。また、設計・検証・運用の各ステップにおいて、法的リスクの検討や契約書締結等の場面が生じるため(下線部参照)、それぞれの段階において適切な法的アドバイスを受けると、より法的リスクの低下につながります。
(参考:https://www.meti.go.jp/policy/itpolicy/jinzai/AIguidebookDemandForecastMFGFIX.pdf )
課題と注意点:
上記のステップを踏むにあたっては、以下の内容に留意する必要があります。
データの質と量: AIの性能はデータに依存するため、高品質で十分な量のデータが必要です。
技術的ハードル: AI技術の理解と専門知識が必要です。必要に応じて外部の専門家を頼ることも考えられます。
組織の変革: AI導入には組織文化や業務プロセスの変革が伴うため、組織の変革とそれに対する協力が必要です。
セキュリティ・プライバシー: データ保護とプライバシーの観点から、適切なセキュリティ対策が必要です。
倫理的な問題の考慮:法的には問題が無い場合であっても、AIの決定が倫理的な問題を含んでいないか等を確認する必要があります。
4. 法的規制とコンプライアンス
総論
AI導入における法的規制を俯瞰したい場合はこちらの記事をご覧ください。
https://gvalaw.jp/blog/b20230531-2
著作権法、その他知的財産法
特に生成AIは著作権法上の課題があります。こちらの記事で詳解しております。
https://gvalaw.jp/blog/b20230810
個人情報保護法・GDPR
AI導入において、個人情報保護は極めて重要です。GDPRや個人情報保護法などの法規制について具体的に解説し、データ収集・利用の際の遵守事項や企業の責任を明確にする必要があります。必要に応じて、企業が法的要求に適合するためのガイドライン作成が望ましい場合もあります。
個人情報保護法についてはこちらの記事が参考になります。
https://gvalaw.jp/blog/b20220701
https://gvalaw.jp/blog/b20240702
GDPRについてはこちらで詳解しております。
https://gvalaw.jp/blog/b20230629
その他透明性と説明責任
AIによる意思決定プロセスの説明と情報提供等、透明性確保のための技術的手法やガバナンス体制の整備が必要になります。
5. 法律事務所が提供する、AI導入の法的リスクの管理と評価
契約書締結サポート
AI導入において契約書を作成する場合においては、技術的詳細やデータの利用権・知的財産権など、多くの点を考慮する必要があります。ベンダーとの契約交渉時に留意すべき事項やリスク管理策について具体的に検討します。契約書に盛り込むべき条項や、紛争解決のための手続きについても詳しく説明し、企業が安心して契約を締結できるようサポートします。
リスク評価と予防
AIシステムの運用中には、予期しない法的リスクが発生する可能性があります。これらのリスクを事前に評価し、適切な予防策を講じることが重要です。具体的なリスクの程度の評価や、リスク軽減のための内部監査・外部監査の活用について提案します。また、リスク発生時の対応策や、継続的なリスクモニタリングのサポートも行い、企業が持続的にリスク管理を行えるよう支援します。
6. まとめ・無料法律相談のご案内
上述の通り、AI導入に際しては各段階において法的留意点やコンプライアンスが重要となってきます。企業がAIを導入する際に直面する可能性のある法的リスクとその対策について理解を深め、成功に導くための基本的なガイドラインを提供します。また、当法律事務所ではAI導入に関する無料法律相談を受け付けており、具体的なご相談にも対応しています。企業が法的リスクを最小限に抑え、AIを効果的に活用するためのサポートを行っています。
7. 終わりに
本記事がAI導入に関する法的な留意点やビジネス展開のポイントの参考になりましたら幸いです。さらに詳細を知りたい方や具体的な法的アドバイスを希望される方は、お気軽に弊所までご連絡ください。










