
執筆:弁護士 水谷 守
(※2023年8月29日に公開。2024年5月1日に記事内容をアップデートいたしました。)
2023年8月29日 公開
2024年5月1日更新
企業経営において株主総会は重要であり、経営者だけでなく、法務部のメンバーや投資家などの立場でも株主総会を理解しておくことは大切です。
株主総会をやらないと何かデメリットがあるのか?
株主総会を実施するにはどんなスケジュールでやるの?
株主総会ってどういうことを決定するの?
今回は初めての方にも「株主総会とは何か?」であったり、具体的に何をすれば良いかを解説していきます。株主総会に関する聞いたことある単語の説明など、株主総会の基本(ときどき発展)を記載していきますので、経営者の方は勿論、法務部の方や投資家の方にも役立つ情報が満載です。ぜひ最後まで読んでみて下さい。
1. 株主総会とは?
株主総会とは、株主が直接参加して会社の意思決定を行う機関のことをいい、会社の経営に関する重要な意思決定は株主総会の決議によって行われます。特に、取締役会を設置していない場合には、多くの事項を株主総会で決定することになります。
取締役会を設置していない場合
⇒会社法に規定している事項や会社に関する一切の事項について決議する
取締役会を設置している場合
⇒会社法と定款に規定している事項についてのみ決議する株主総会決議事項につき、株主総会決議を経ないで業務執行をすることは、当該行為が法的に無効になり得るばかりでなく、場合によって株主から取締役としての忠実義務(会社法355条)、善管注意義務(会社法330条、民法644条)違反等を理由に損害賠償請求を受けたり、スタートアップ企業の場合は重大なコンプライアンス違反として、事後の資金調達やIPO等の障害になるなど、会社経営にとっての重大なリスクになりかねません。
しかし、そもそも株主総会で決議しなければならない事項を知らなければ、決議が漏れた状態でビジネスを進めてしまうことも少なくありません。したがって、会社経営者にとって、株主総会の決議を把握しておくことは重要です。
本稿では、スタートアップ企業等で会社設立直後の取締役会を設置していない場合を前提として、株主総会の基本や招集手続、さらには決議の種類や種類ごとの決議事項を紹介します。
(1) 定時株主総会
定時株主総会とは、毎事業年度の終了後一定の時期に招集される株主総会のことをいいます(会社法296条1項)。事業年度については、1年を一事業年度と設定している会社が多く(後掲江頭p328)、その場合は毎年1回定時株主総会を開催すべきこととなります(なお、会社計算規則59条2項により、原則として1年を超える期間を一事業年度とすることはできません)。定時株主総会を漏れなく行うためにも、自分の会社の事業年度について把握しておくことが重要です。
株主を召集する時期にも注意しましょう。定時株主総会の具体的な招集時期は、議決権行使に関する基準日の定めとの関係から、基準日(多くの場合、事業年度終了日)から3か月以内(会社法124条)とする必要があり、例えば毎年3月末を事業年度末としている会社の場合、定時株主総会は6月末までに開催しなければなりません。
(2) 臨時株主総会
定時株主総会に限らず、必要がある場合には、株主総会はいつでも招集したうえで開催することができます(会社法296条2項)。このような定時株主総会以外で必要な時に開催される株主総会を、臨時株主総会といいます。

【定時株主総会】
毎事業年度の終了後一定の時期に召集される株主総会のこと。事業年度については1年を一事業年度と設定している会社が多く、さらに定時株主総会は事業年度末日から3か月近く後に開く場合が多い。
【臨時株主総会】
定時株主総会以外で、必要がある場合に開催される株主総会のこと。2.株主総会の招集手続き
まず、取締役会非設置会社の場合、株主総会の招集は、取締役の決定に基づき、定款の規定に従って代表取締役が招集することが多いです。
そして、非公開会社(非上場会社)の場合、多くは定款の定めに基づき、株主総会の日の1週間前までに原則として書面(郵便等)で各株主に対して通知を送付する必要があります(会社法299条1項、2項)。なお、取締役会非設置会社では、1週間より短い招集期間を定款で規定することも可能です(会社法299条1項)。
招集期間は、招集通知の発出日(投函の消印日)と実際の株主総会の開催日を除いて中●日間を確保する必要があります。例えば、招集期間が1週間の場合、中7日間を確保する必要があるため、8月21日に招集通知を発送した場合は、8月29日以降に開催すべきことになります。
なお、全株主の同意がある場合は、原則としてこの招集手続を省略することも可能です(会社法300条)。
このように、具体的な事情を考慮しつつ、株主総会を行う時期から逆算して手続を行う必要があります。
【送付の時期】
公開会社 | 非公開会社 | 非公開会社で取締役会非設置 |
|---|---|---|
取締役が株主総会の日の2週間前までに発送 | 取締役が株主総会の日の1週間前までに発送 | 定款で1週間よりも短い期間とすることも可能 |
【株主総会の招集手続の例~事例~】
▼事例
GVA株式会社は、非公開会社かつ取締役会非設置会社である。8月29日に株主総会を開催したいが、いつまでに招集通知を発送すれば良いか?なお、定款には招集期間に関する規定はない。
▼解説
① 取締役会非設置会社では、取締役決定に基づき、定款の規定にしたがって代表取締役が招集することが多い。
② 招集期間は、招集通知の発出日(投函の消印日)と実際の株主総会の開催日を除いて中7日間を確保する必要がある(会社法299条)
③ 今回は8月29日に株主総会を開催したいので、8月21日に招集通知を発送する必要がある。
3. 株主総会決議の種類
次に、株主総会決議の種類について解説していきます。会社法上、株主総会の決議にはいくつかの種類が存在するため、間違えて決議しないように注意が必要です。
(1) 普通決議
普通決議とは、基本的には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う決議のことをいいます(会社法309条1項)。特に法令で定めが無い場合には普通決議により決議されます。
【普通決議の設例】
GVA株式会社の株主は、以下3人(株主A、株主B、株主C)である。株主総会において普通決議が行われる際には、
① 株主Cが出席する必要がある(出席の要件)。
株主C:200÷350(全体)=57%
② 決議の際にもCの賛成が必要となる。

主な普通決議事項は以下のとおりです(引用条文は全て会社法です。)。

取締役・監査役等の役員の選任、解任(339条、341条)
役員の報酬の決定(361条1項、379条1項、387条1項)

剰余金の配当(454条1項)
例外として、取締役会設置会社は取締役会で手続をおこなうことも可能。
1.取締役会の決議で一事業年度に金銭の配当を行うことができる旨の規定が定款にある場合(454条5項)
2.(a)会計監査人を設置し、(b)取締役の任期をその選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする取締役会を設置している株式会社で、(c)剰余金の配当を取締役会の決議で行うことができる旨の規定が定款にある場合
合意による自己株式の取得(156条1項)
譲渡制限株式の譲渡承認(139条)
株式分割の決定(183条)

計算書類の承認(438条2項)
定時株主総会において欠損の額を超えない範囲で決定する資本金の額の減少(447条1項・309条2項9号)
準備金の額の減少(448条1項)
剰余金の額の減少による資本金・資本準備金の増加(450条2項、451条2項)

取締役の競業取引や利益相反取引の承認(356条1項)
※取締役会を設置している場合には取締役会が承認する(365条1項)
・競業取引(356条1項1号)
取締役が自己や第三者のためにその会社の事業の部類に属する取引を行うこと。
・利益相反取引直接取引(356条1項2号)
⇒取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をすること。
間接取引(356条1項3号)
⇒会社が、取締役以外の者との間で、会社と取締役との利益が相反する取引をすること。(2) 特別決議
特別決議とは、基本的には、その株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う決議をいいます(会社法309条2項)。
【特別決議の設例】
GVA株式会社の株主は、以下の3人(株主A、株主B、株主C)である。
① 特別決議の際には、株主Cが出席する必要がある(出席の要件)。
株主C:200÷350(全体)=57%
② 特別決議の際には、以下の組み合わせの賛成が必要になる(全員出席とする)。
・全員の賛成
・株主B+株主C:300÷350=85%
・株主A+株主C:250÷350=71%

主な特別決議事項は以下のとおりです(引用条文は全て会社法です。)。
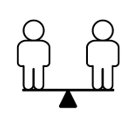
株主平等の原則の上から株主の利害に関わる事項
・譲渡制限株式の買取り等(140条2項、5項)
・特定の株主からの自己株式取得(156条1項、160条1項)
・現物配当(454条4項)
会社支配に関わる重要事項
・累積投票により選任された取締役、監査役、監査等委員である取締役の解任(309条1項)
・役員等の責任の一部免除(425条1項)
募集株式・新株予約券の発行等に関わる重要事項
・全株式譲渡制限株式会社等における募集株式や新株予約権の発行等(199条2項、200条1項、202条3項4号、204条2項、205条2項、238条2項、239条1項等)
・特に有利な払込金額による募集株式の発行等、特に有利な条件による新株予約権の発行等(199条2項、201条1項、238条2項、240条1項)
株主の地位に関わる事項
・一般承継人に対する株式売渡請求(175条1項)
・全部取得条項付種類株式の取得(171条1項)
・株式の併合(法180条2項)
組織再編行為等の会社の基礎の変更
・定款変更(466条)
・事業譲渡等(467条1項)
・合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付(783条1項、795条1項、804条1項、816条の3)
・資本金の額の減少(447条1項)
・解散、会社の継続(471条3号、473条)(江頭p372-373を参考に作成)
(3) 特殊決議
特殊決議とは、特別決議よりも厳重な要件が要求されている事項の決議をいいます。特殊決議は2種類あります。
第1に、基本的には、その株主総会において議決権を行使することができる「株主」の(議決権ベースではなく、株主の頭数)半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です(会社法309条3項)。以下の設例では、この特殊決議を「特殊決議A」といいます。
【特殊議決Aの設例】
GVA株式会社の株主は、以下3人(株主A、株主B、株主C)である。
① 特殊決議Aの際には、2人以上の出席が必要となる(出席の要件)。
② 特殊決議Aの際には、以下の組み合わせの賛成が必要になる(全員出席とする)。
・全員の賛成
・株主B+株主C:300÷350=85%
・株主A+株主C:250÷350=71%

この方法で決議すべき事項は以下のとおりです(引用条文は全て会社法です。)。

1. 定款変更により株式を譲渡制限株式に変更すること(309条3項1号、107条1項1号、同条2項1号)
2. 組織再編行為によって、株式が譲渡制限株式等に変わること(309条3項2号、同項3号)(江頭p373を参考に作成)
第2に、基本的には、総株主の(議決権ベースではなく、株主の頭数)半数以上で、総株主の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う決議です(会社法309条4項)。以下の設例では、この特殊決議を「特殊決議B」といいます。
【特殊議決Bの設例】
GVA株式会社の株主は、以下3人(株主A、株主B、株主C)である。
① 特殊決議Bの際には、2人以上の出席が必要となる(出席の要件)。
② 特殊決議Bの際には、以下の組み合わせの賛成が必要になる(全員出席とする)。
・全員の賛成
・株主B+株主C:300÷350=85%

この方法で決議すべき事項は以下のとおりです(引用条文は全て会社法です。)。

全株譲渡制限会社において、剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会の議決権につき株主ごとに(属人的に)異なる取り扱いを行う旨の定款変更(当該定めを廃止するものを除く)を行う場合(309条4項)(江頭p373を参考に作成)
(4) 書面決議(みなし決議)
以上、決議の種類についてご説明しましたが、書面決議という方法を用いることによって、会議を省略することができます。これを書面決議(みなし決議)といいます。具体的には、議決権を行使できる株主の全員が、書面等により提案内容に同意の意思表示をすることで、実際に株主総会を開催することなく、提案を可決する旨の株主総会決議があったものとみなすことがみとめられています(会社法319条1項)。
書面決議は、株主が取締役のみ等だけで全員の同意を得ることが容易なケースでは、招集手続を経る必要がないため、機動的に株主総会決議を得る方法として良く活用されます。また、スタートアップ企業における増資時には、株主間契約等で新株発行自体が各株主の事前承認事項とされているケースも多いことから、書面決議が用いられることも多いです。
【株主総会の省略方法~書面決議~】
株主総会の省略する方法⇒
書面決議という方法を用いることによって、会議を省略することが可能(会社法319条1項)。書面決議の方法⇒
議決権を行使できる株主の全員が書面等により提案内容に同意の意思表示をする。
株主=取締役のみ等で全員の同意を得ることが容易なケースでは、招集手続を経る必要がないためよく活用される。(5) 小括
少し長かったので、一度ここまでのまとめをします。
株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があり、株主総会を行う日から逆算して招集を行う必要があります。
株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議の3種類があります。普通決議は、出席株主の議決権の過半数で行われ、一般的な運営関連事項に用いられます。特別決議は、より厳格な基準を要し、組織再編や会社の基礎変更など重要事項に必要です。特殊決議は、特別決議よりも更に厳しい要件が求められる決議です。
株主全員の同意により会議を省略して決議する書面決議という方法もあります。
以上がここまでのまとめとなります。とはいえ、実際に株主総会の決議事項を暗記することは非常に困難ですし、会社の状況にあった手続を行うことも簡単ではないと思います。そこで、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。GVA法律事務所では初回無料相談を行っていますので、少しでも気になることがあればせっかくなので無料分だけでもぜひご利用下さい!
4 .主な株主総会決議事項の内容
ここからは、株主総会において主に決議される事項をピックアップして解説していきます。
(1) 決算の承認
会社は、毎事業年度の終了後、会社の業績についての報告と承認を行う義務があります。具体的には、毎事業年度の終了後、計算書類と事業報告を作成する必要があります(会社法435条2項)(注1)。そして、定時株主総会において、計算書類と事業報告を提出して(会社法438条1項)、計算書類については普通決議による承認を受ける必要があり(同条2項)、事業報告については内容を報告する必要があります(同条3項)。
※(注1)計算書類とは、①貸借対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書、④個別注記表、さらにこれらの付属明細書のことを指します(江頭p629-p630)。
(2) 役員の選任決議
役員(取締役及び監査役)の選任は、基本的には株主総会の普通決議によって行われます(会社法329条1項)。役員には任期があるため、任期が満了していないかを注意する必要があります。
取締役の任期は、定款で規定されることが多く、2年(正確には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、以下同じ。)とされる例が一般的ですが、非公開会社では、定款の定めにより10年まで延長することが可能です(会社法332条1項、2項)。監査役の任期も、同様で定款の規定によりますが、4年(4年より短期は不可)とされることが多く、非公開会社では、最長10年とすることが可能です(会社法336条1項、2項)。
任期満了後に再び同じ人が役員に就任する場合でも(「重任」といいます。)、再度株主総会の普通決議によって選任する必要があることに注意が必要です。役員の異動は登記事項(会社法915条第1項)ですので、選任手続後の登記を怠った場合には、過料の制裁を受ける場合がある(会社法976条1号)ので重任決議・登記漏れに気を付けましょう。
(3) 役員の報酬決議
取締役が会社から受ける報酬、賞与その他の職務執行の対価である財産上の利益(報酬等)については、基本的には株主総会の決議により定めなければなりません(361条1項)。
報酬等のうち、金額が確定したものについては、その額となります(361条1項1号)。実務的には、株主総会の普通決議によってその総額(取締役が複数いる場合は取締役全員の役員報酬の総額)の最高限度額を定めて、その範囲内で実際の拠出額を取締役の過半数で決定することが多いです(江頭p467)。
また、報酬等が会社のストックオプションである場合には、スタートアップ企業は通常全ての株式に譲渡制限を付けているので、株主総会特別決議によってストックオプションの内容を決定する必要があります(238条2項、309条2項6号)。
(4) 競業取引・利益相反
取締役による競業取引や利益相反取引が行われる場合もしばしばあり、その場合には株主総会で決議する必要があります。
① 競業取引
取締役が、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは(競業取引)、その取引について重要な事実を開示して株主総会の普通決議による承認を受ける必要があります(356条1項1号)。
「会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている取引と目的物(商品・役務の種類)さらに市場が競合する取引をいいます(江頭p453)。また、規定上は、取締役が自己または第三者のために個々の取引行為をすることが承認の対象となっているため、取締役が他の競業会社の取締役を兼任するだけでは競業取引には当たりませんが、代表取締役として兼任する場合には、包括的に承認を受けるのが通例となっています(江頭p453-454参照。)。
競業取引の具体例としては、日本国内でスーパーマーケットを展開しているA社の取締役が、新たに日本国内でスーパーマーケットを展開する会社を代表取締役として設立しようとしたときには、競業取引として株主総会の承認を受ける必要があります。これは簡単な例ですが、実際上判断が容易ではない場合もあることに注意が必要です。
② 利益相反取引
利益相反取引とは、簡単にいうと、取締役と会社の利益が相反する取引をいいます。取締役が利益相反取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して株主総会の普通決議での承認を受ける必要があります(法356条1項柱書)。利益相反取引は2種類あります。
1つ目は、直接取引です(356条1項2号)。これは、取締役が当事者として(自己のために)、または他人の代理人・代表者として(第三者のために)、会社と取引をすることをいいます。たとえば、取締役が会社との間でお金を貸し借りする場合が直接取引に該当し、株主総会の普通決議による承認が必要となります。
2つ目は間接取引です。これは、会社が取締役以外の者との間で会社・取締役間の利害が相反する取引をいいます。たとえば、会社が取締役の債務を保証する場合がこれに該当します(会社が取締役の債務を保証するのは、会社と取締役に対して債権を有する者との間の取引です。)。
利益相反取引も、その該当性の判断が悩ましいケースも多く、スタートアップ企業の投資契約又は株主間契約等で、会社と取締役双方が契約当事者に含まれる場合などは、利益相反取引に該当するおそれがあるとして、承認決議を取得しておくべきケースが多いです。
5. 株主総会の注意点まとめ
これまでに述べた株主総会の注意点をコンパクトにまとめました。
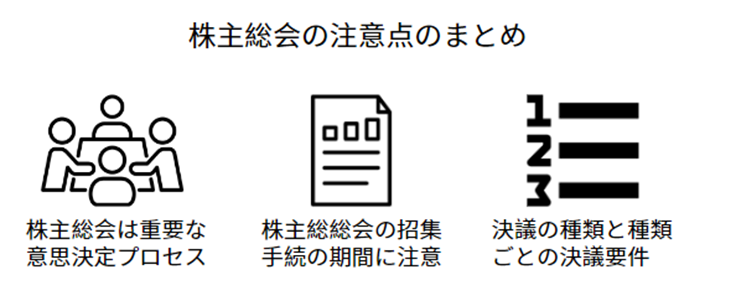
そして、上記のとおり、株主総会決議事項につき、株主総会決議を経ないで業務執行をすることは、当該行為が法的に無効になり得るばかりでなく、場合によって株主から損害賠償請求を受けたり、スタートアップ企業の場合は重大なコンプライアンス違反として、事後の資金調達やIPO等の障害になるなど、会社経営にとっての重大なリスクになりかねません。株主総会を適切に行うことが大切です!
6. 発展:種類株主総会決議
種類株主総会は、法令に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(会社法321条)。法令に規定する種類株主総会の決議事項は主に以下のとおりです。
事項 | 決議事項(引用条文は全て会社法) |
① | ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合における当該行為の承認(322条1項) |
② | 拒否権付種類株主を設けた場合における拒否権の対象事項(108条1項8号、同条2項8号、323条) |
③ | 種類株主総会により取締役・監査役を選解任出来る株式を設けた場合における拒否権の対象事項(108条1項1項9号、同条2項9号、347条) |
④ | 種類株式に譲渡制限又は全部取得条項を付す場合における定款変更、譲渡制限株式の募集(111条2項、324条3項1号、199条4項、200条4項、238条4項、239条4項) |
(江頭p323を参照)
表中の①については、定款により、種類株主総会の決議を不要とする定めを設けることができ、スタートアップ企業における種類株式の内容として、法令上可能な範囲で種類総会決議を排除することが一般的です。しかし、株式の種類の追加といったラウンド変更をする際には、定款の変更に関わらず必ず種類株主総会の決議をする必要があり(会社法322条3項、322条1項1号イ)、種類株主総会の決議漏れに注意が必要です。
なお、上記のケースで種類株主総会の決議が必要な場合は、普通種株主による普通種類株主総会の決議も必要となるため、新たな種類の株式を発行した増資の際には、手続きに遺漏が無いように弁護士等の専門家に相談をすることをお勧めします。
7.まとめ
以上のように、株主総会決議の基本をご説明しました。実際の会社の状況によって準備すべきことや決議事項が変わりますので、少しでも不安な点があればやはり弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。GVA法律事務所では以下をはじめとして、株主総会に関する様々なサポートをしています。
株主総会のスケジュール作成
株主総会で必要なドキュメント作成
決議漏れが判明した場合のリカバリー対応
GVA法律事務所では初回無料相談を行っています。さすがに無料相談でドキュメント作成等をすることはできませんが、せっかく無料なので少しでも気になることがあればぜひお問い合わせ下さい!
8. 参考文献
江頭憲治郎『株式会社法第8版』(2021)有斐閣
監修
弁護士 熊谷 直弥
(2012年の弁護士登録以来、一貫して企業法務を扱う。中小企業から上場企業まで広く担当し、契約法務、人事労務、紛争、渉外法務、商標等で研鑽を積む。2019年GVA法律事務所入所後、スタートアップ企業の法務支援に注力し、IPOやその先の成長までの伴走を複数経験。顧問先スタートアップSaaS企業の監査役を務める。 所内のWEB3チームのリーダーとして、NFT関連ビジネスや暗号資産、STO、その他トークンビジネス等の研究及び実務を対応。NFT書籍の監修の他セミナー等でのNFTに関する情報発信も多数。)










