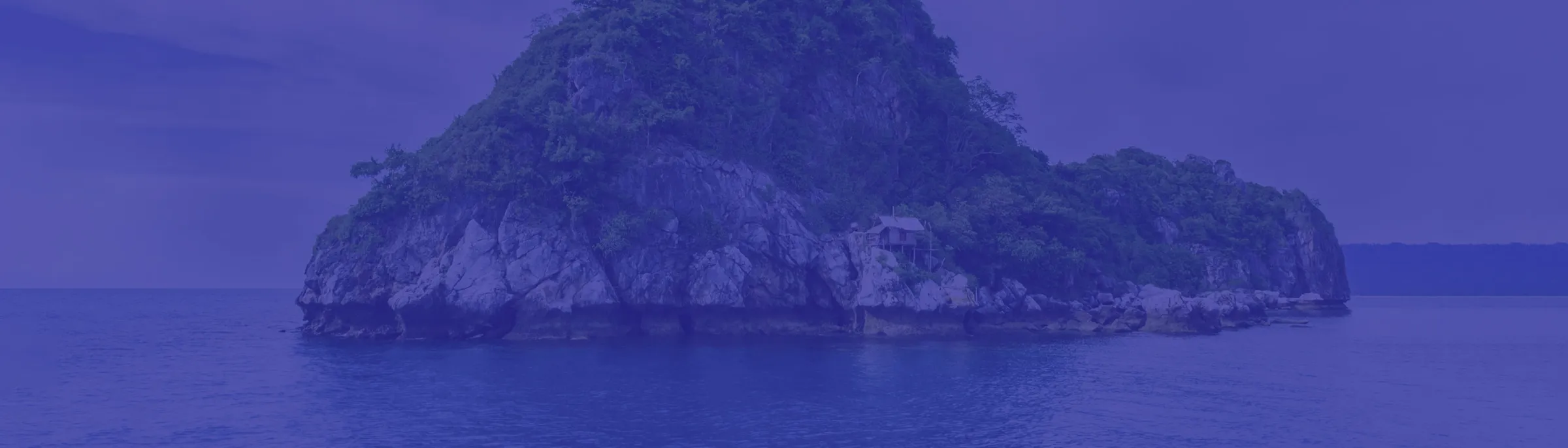Interview

宇宙・航空
GVA法律事務所による宇宙・航空領域をリードする2社代表スペシャルインタビュー

インターステラテクノロジズ株式会社
代表取締役
稲川 貴大 様

株式会社ElevationSpace
代表取締役CEO
小林 稜平 様
まず初めに両社の事業について、また最近のトピックをご紹介ください
インターステラテクノロジズ株式会社 稲川 貴大 様(※以下、IST 稲川様)
民間企業独自にロケットを開発して打ち上げる、という事業を行っています。
当社の観測ロケットMOMOという、宇宙空間に到達後降りてくるロケットや、新しく開発中の超小型人工衛星用ロケットZEROという人工衛星を地球周回軌道に投入するロケットなどの開発を行っています。
やっていることはロケットの打ち上げですが、ビジネスとしてはお客様の荷物をお預かりして宇宙へ運ぶ宇宙輸送サービスです。まずは、実験装置や人工衛星などの輸送を考えておりますが、将来的には有人ロケットも視野に入れて一歩ずつ技術開発をしている企業です。

株式会社ElevationSpace 小林稜平様(※以下、ELS小林様)
昨年2月に立ち上げた東北大学発ベンチャーです。
共同創業者の東北大学准教授の桒原先生の研究室では、これまでに15機以上の研究開発の実績があります。この技術を活用して、大学からも正式に許可をいただく形で、会社を立ち上げました。
高度400kmにある宇宙ステーションでは、宇宙飛行士が、無重力環境で様々な実験を行っていますが、寿命の関係で2030年頃になくなってしまうと言われております。現在、それに代わるプラットフォームを作ろうとしています。人がいる宇宙ステーションではなく、無人での人工衛星によって、同じような宇宙での実験の場所を提供しようとしています。

創業のきっかけを教えてください
IST 稲川様
会社を設立する前、2005年に「研究会」という形でスタートしたのが前身です。当時は、小型の人工衛星がまだ生まれていない頃で、衛星がどんどん大型化・高性能化していくという時代でした。そんな中でも、私たちは、そんな中でも「これから小型の人工衛星の時代が必ず来る!」とほとんど予言のようなことを言っていました。そこから逆算した上で、小型ロケットを民間で作ろうと開発をスタートしたのが始まりです。
ELS 小林様
私は建築学の出身で航空宇宙専攻ではなかったのですが、まず最初に宇宙建築という分野に出会いました。宇宙ホテルとか月面基地とか地球の外に建てる建築物ですね。それに出会ったのが自分の人生が変わったきっかけでもあり、宇宙分野に興味をもったきっかけでもありました。その後は宇宙建築の分野に没頭し、ありがたいことにコンペティションでは日本1位や世界2位も頂きました。
当時も今も、宇宙で人が生活できる世界を実現したい、ということが自分の一番やりたいことであることは変わりません。
共同創業者の桒原先生と出会ってから会社設立まで1年数ヶ月は、ずっとElevationSpaceを立ち上げるために、先生や他の何名かと活動していました。それを経て昨年2月にElevationSpaceを立ち上げました。今やっていることは単純に無人の人工衛星ではありますが、私たちの衛星の一番の特徴は、人工衛星が宇宙空間から地球に戻ってくるという点です。これは、人が宇宙に行くためにも欠かせない技術です。宇宙に行ったきりというのはあり得ませんので。そういった将来的に行っていきたい事業、人が宇宙で生活するところの事業から逆算してElevationSpaceを立ち上げ、今の事業に取り組んでいます。
創業後、どちらも資金調達をされていますがその背景にはどのようなものがあったのでしょうか?

ELS 小林様
2021年の2月に会社を設立した後は、クラウドファンディング、株式での資金調達、補助金いくつか、含めて約5億円の資金調達を行っています。直近では、3月にシードラウンドで3.1億円の資金調達を行っております。今回の資金調達は、これまで宇宙系に投資していなかった株式会社ジェネシアベンチャーズさんにリード投資家として入っていただいたのが他とは少し違う特徴です。私たちの事業の特徴として、たとえば材料メーカーや創薬系の企業など地球上の産業に取り組まれているお客さんが多いということもあるかと思います。
資金調達の際は、投資家の方にはかなり多くの方々に声をかけ、想定していたよりも時間がかかってしまいましたが予想より大きく投資していただき、良い投資家さんに出会えたので結果的にはよかったです。投資家選びにおいては、日本だけではなくてグローバルのマーケットを見据えていました。日本から近いアジア関連のマーケットが今後宇宙系でも伸びてくるのではないかと思っていたので、アジアに強みがあるベンチャーキャピタルに参画していただいたのは、意義のあることでした。
また、資金だけではなくその後のサポートや関係性をどのように築いていけるかはとても重視しました。設立してまもない企業なので、外部のリソースをどのくらい使えるか、サポートをどれくらい得られそうかというのがまずひとつ。もうひとつは、投資家さん自身がどんな人となりなのかは重視しました。投資家の方との密なやり取りは当然その後もあるので当たり前です。実際に投資くださった担当の方は実績もあり、人柄も株式会社ElevationSpaceの考え方にあっていたので社外取締役にも入っていただいて、経営にコミットする形で今でもやり取りを密にさせていただいています。

IST 稲川様
直近の資金調達はシリーズDで、18.7億円程度を調達しています。ロケットの開発は製造業の側面が大きく、とにかくお金がかかります。サービスとしては輸送業だが、ロケットを開発するには工場が必要。さらに、ものづくりの総合格闘技と言われるロケット開発・製造にはあらゆる分野の人材の採用が必要なため、かなり広い範囲で大型の資金調達を毎回行っています。
小林さんがシードラウンドで3億円を集めていると聞くと、隔世の感があります。
ISTの事業開始は2013年で、当時は宇宙業界を理解している人が少なく、シリーズAの時は非常に苦労しました。
そのため、最初は、個人投資家が多かったですね。一部事業会社もありましたが、金額的には圧倒的に個人の投資家が多かった。個人の投資家の方には、回収期間を長く捉えてもらえたり、社会貢献、人類の進歩の視座で納得していただけていました。
その当時から考えると、あれから月日が経って、だいぶ宇宙産業=成長産業としてみられるようになってきたなと感じます。民間がロケットを打ち上げていいのか、という議論から法曹界と我々でうるさく国に要望をして、宇宙活動法をつくってもらったこともあり、ここ数年で変わってきたなと思います。
今から事業を立ち上げると、資金調達しやすいのでうらやましいなと思っています。やっと宇宙産業が認知された感じですから。
最近のラウンドでは、上場会社だとサイバーエージェントさん、INCLUSIVEさん、IMVさん、KADOKAWAさんにも入っていただいています。
ちなみに、ロケットは物を打ち上げるということばかり注目されがちですが、ロケットの発射場も大事なんです。そうなると、北海道のまちづくりや地方創生もかかわってきます。それ以外にも、リモートセンシングや通信産業にも革新がおこると思っています。一次産業、二次産業、ビッグデータ解析の分析産業などいろいろなところに貢献ができると思っています。
事業を立ちあげた当初はかなり苦労しました。MOMOを打ち上げるためのクラウドファンディングでしたが、ロケットの打上げ目的は、防災のためのセンサーで計測するという真面目な用途だったので、それだけだとなかなか認知が広がらなかったんです。
なので、企業の広告として、企業名をドンと機体にのせてみたり…3号機は企業さんのゆるキャラを描いたりもしました。クラウドファンディングでPRの方法を探りながらコアなファンを集め、さらに企業さんと色々繋がることができるようになるまでは本当に大変でした。一度、ロケットを打ち上げると色々メディアに取り上げていただけるので、一般への認知が広がりました。一方で、堀江(※堀江貴文さん)が創業した会社のため、ホリエモンロケットと言われることも多いのですが、実は真面目なものづくりの会社で、誰もが宇宙を身近に使えるようにしたいという思いでやっているんです。例えばですが、企業の方々に北海道の工場へ直接お越しいただいて、実際に機体や現場をみていただき、ロケットの成功・失敗も含めてのストーリーを知っていただくような活動もしています。
例えばロシアとウクライナ問題なども含めて、宇宙ベンチャーの現在地についてどのように思われますか?
IST 稲川様
実は、これまで宇宙輸送というのはロシアやウクライナの技術がかなり入っていました。世界的なロケットのシェアにおいて10ー30%がロシアやウクライナの技術で宇宙輸送されてきていたんです。それが今回の件で、ロケットの供給が2−3割いきなりなくなってしまった状態です。もちろん、戦争は不幸なことで、何があっても許されることではないですが、宇宙にモノを運ぼうとしたとき、明らかに輸送が足りていない状態であり、そのシェアを取っていかなければと思っています。
また、ウクライナ戦争では民間の宇宙技術が使われました。例えば、ジャーナリストが民間の人工衛星(リモートセンシング衛星)を使ってロシアの戦車の隊列が今どこにいるのかを分析することが可能となったり、これまでの戦争と現代の戦争は違うな、とつくづく感じることが多いです。
宇宙を使うことで、有事・戦争の進め方は大きく変わります。業界の人間だけでなく、一般の人や意思決定するような人たちの場面でもそこが認知されるようになりました。産業の盛り上がりとともに、業界にいる我々が、しっかりとしたサービスを提供しなくてはならないなというプレッシャーを感じています。
ELS 小林様
今回の戦争について、私たちの事業にとっては悪い影響よりも良い影響の方が多いかなと思っています。ロシアも宇宙ステーションの運営に強く関わっていますが、戦争の影響で、今後どのように関わっていくか不透明性が高くなっており、宇宙ステーション自身が今後どうなっていくのかがかなり不透明性が高くなっている状況にあります。現時点で、宇宙ステーションについて2025年以降どうなるかは決まっていません。ロシアがどのようなスタンスを取るかは大きな影響があると思っています。宇宙ステーションのユーザーつまり実験する側からすると、今後どうなっていくのかわからないというのは利用しづらい面があると思っています。その点では、私たちもサービス化はこれからではありますが、宇宙ステーションよりもそのようなリスクも少なく、気軽に、高頻度で実験できるような環境を提供できると思っておりますので、その意味ではプラスの側面が多いと感じています。
悪い影響と言えばインパクトがそこまで大きくないですが、部品が調達しづらい環境にはあります。納期が少しかかったりですね。私たちは2023年末打上げを目指して最初の人工衛星技術実証機を開発しているのですが、納品問題の衛星開発への影響は多少感じているところです。
現在地としては、弊社は業界の中で通常の衛星と比べて、かなり尖った技術を持っていると思っています。私たちのコアである大気圏再突入技術と呼ばれる技術ですね。これは宇宙から地球に戻ってくる技術ですが、日本では民間で持っているプレーヤーはいないんです。JAXAやNASAといった国の機関がずっと研究開発してきたもので、世界でも民間で持っているプレーヤーはSpaceX等極めて限られています。国内で再突入して戻ってきた人工衛星は片手で数えるほどしかないのです。まだまだ実例がない開発に取り組んでいるという意味で、通常の人工衛星開発に比べると、技術的なハードルがかなり高いということは承知しています。
更に、戻ってくるという観点で他の人工衛星と違うことが多くあります。小型衛星ですと、推進機器をそもそも積んでいない衛星も多く、積んでいたとしても推力は1ニュートンも無いものがほとんどなのですが、宇宙から戻ってくるためには大きな推力が必要で、そうすると100ニュートン級のエンジンを使うことになります。私たちは自社で開発しているのですが、これも小型衛星用では世界最高クラスのものになっております。
また再突入のときに燃え尽きないように耐熱の技術も重要です。通常の人工衛星であれば大気圏で燃え尽きてしまいます。さらには大気圏を突破したあとに、パラシュートを開いて減速するための技術や海で回収するための技術が必要になります。このように通常の人工衛星にはない技術が多いので、経験しているプレーヤーが少ないという点ではとても高い難易度の課題にチャレンジしている自覚はあります。技術顧問の渡邉先生は、JAXAで30年ほど再突入技術の研究開発をリード、唯一宇宙ステーションから物資を持ち帰ってきた日本の再突入カプセルの研究開発をリードされていた方です。数少ない知見のある方を仲間に入れて、研究開発をしています。
IST 稲川様
再突入の技術は非常に興味がありますね。私たちは、現在液体ロケットを開発していますが、将来的にはやはり有人ロケットをやりたいですね。例えば、地球に帰ってくる際に熱にどうやって耐えるのかは大きな課題です。小林さんのところは多分アブレーション冷却でやられると思うんですが、別の革新的な技術もあるべきだと思っています。宇宙輸送システムとして、パラシュートとカプセルの合わせ技が今後重要になのではないかと思います。今後新しく開発する技術として、実現性はわからないですが、国と連携しながらやっていきたいです。
日本での法制度についてはどのように思われますか?
IST 稲川様
実は、宇宙活動法というものは、国に依頼して作ってもらった経緯があります。これは、民間がロケットを打ち上げる際の法律です。国の研究開発は、JAXAがやっていたので元来そこに法律は必要なかったんです。そこに、民間が参入することになり、どのロケットからどう規制するかの整理が必要になりました。日本は産業育成の観点でポジティブな規制としてくれました。弊社が手掛けるMOMOについては、他国の上を飛ばずに日本から打ち上げて海に落ちる観測ロケット、サブオービタル弾道飛行ロケットになりますが、これは活動法の許認可の対象外になります。もちろん、他の法律や政令(高圧ガス保安法、危険物の規制に関する政令など)を10個くらいきちんとクリアする必要がありますが、あとは自主規制をクリアすれば打ち上げていいという建て付けにしてくれました。国の許認可を得るとなると、膨大な書類が必要で手続きが大変だったので、研究開発がやりやすくなりました。これが宇宙活動法の良いところです。
次のZEROについては、人工衛星用ロケットになるので他の国の上を飛ぶ可能性があります。そのため許認可の対象にはなりますが、過度に強い規制にはなっておらず、他国の事例もみて合理的な基準にしてもらいました。
法律を作る際には、これからベンチャーもでてくるというところで、「あまり強い規制にするとベンチャーがでてこられなくなりますよ」と我々からも提言しましたし、他の方々からも賛同していただき同じように声をあげていただいたので、我々のようなニュースペースとよばれるベンチャー企業がロケットを打ち上げられる体制にしていただいたと思っています。宇宙活動法の建て付けをつくってもらったのはとてもありがたいことでした。
とはいえ、実際に打ち上げるときは法律をクリアするための対応はそれでもそれなりに大変ですし、それ以上に大変なのは地元のステークホルダーへの理解を得ることです。ロケットの打ち上げともなると警戒区域がものすごく広くなり、半径1.5kmを封鎖します。海についてはもっと広範囲です。地上の道路も封鎖しなければなりませんし、漁師さんやタンカーにもご理解をいただく必要が出ます。そのための準備としてロケット打ち上げの3ヶ月程前からきちんと理解していただくための活動をしています。これについてはどこか一つでもNGがでるとうまくいかないです。法で線引きできることだけでなくそれ以外の地元のルールを壊さぬよう、ご理解いただいてご協力いただくことが非常に重要になります。アメリカの場合は、軍に隣接した射場だと、もともと規制がかけやすい場所だったりしますが、日本はそうではないので、そこをうまくやらなければならないという大変さが現場レベルではあります。
宇宙ビジネスの低価格化と言われていますがどう捉えられていますか?
ELS 小林様
低価格化はしてきていると感じています。宇宙開発の価格で一番インパクトが大きいのは打ち上げの価格だと思います。稲川さんは世界中の事例を色々ご存知かと思いますが、打ち上げに関しても色々な選択肢が増え、民間が入ってきたことで商業化されて競争が生まれているのでそこが背景にあります。ロケットや衛星以外でいくと宇宙ステーションはいまだに国主導でやっているのですが、実験や宇宙を使った取り組みを商業化させていきたい。それにより、宇宙をより安く気軽に使える状況を、私たちも作っていきたいと考えています。
IST 稲川様
我々も低価格コンセプトでやっていますが、それ以上に重要なのは、国の開発だと確実に成功させたいというモチベーションが根幹にあるので、アプリケーションは非常に限定的・保守的になり、あまり新しいことができないということです。官から民主導にかわることで、アプリケーションの幅が広がってきました。国主導の進め方では新しいことがやりづらかったのですが、いろいろなアプリケーションの幅が広がってきたことにより官から民へと変わってきました。小林さんの宇宙から実験したものを持ち帰るということなどもそうですね。国の開発だと真面目な用途に寄ってしまう。国の審査を経たものしか許されなかったんです。アプリケーションが自由になっていくというのが、民間がやる本質的な意味だと思っています。もっと自由に、新しい技術を取り入れるインセンティブが生まれています。宇宙業界のアポロ計画から50年たっての進歩のスピードは正直ほかの業界より遅いと思っていますが、官から民へ変わることで、他の産業と同じスピードで技術開発が進み、技術革新がされていくという、イノベーションのサイクルが回り始めるというところが、本質的なところなのかなと思っています。
アメリカやロシアがリードしがちな宇宙産業ですが、日本がグローバルで戦うために何が必要だと思いますか?
IST 稲川様
日本って、やっぱりとてもいい国なんです 。製造業が強く、自動車産業を筆頭に中小企業から大企業までものづくりの技術力がある。ぱっとこういうことできませんかと聞いても、できると答えてもらえるし、特急でとお願いしてもやってもらえるという日本の環境は、とても貴重な基盤です。でも今後何十年もそれが続くかというと、正直難しいと思っています。今なら、人・設備・会社もある。こういう時代だからこそ、宇宙産業がきちんと日本に根付いて、日本のなかの一産業として根付くといいなと思います。宇宙は、いまのところ三次産業になるのですが、製造業からサービスまで含めた産業を作っていかなければという思いはあります。それゆえ、日本でやる意味はあると思っています。
我々が打ち上げる北海道はとても良い場所だといえます 。ロケット打ち上げは地球の自転の関係で東が海にひらけていることが非常に重要なのですが、世界を探してもこんなにロケット発射に適した場所はそうそうないと思っています。もともと30年ほど前に種子島にロケットの発射場を作る計画が動いているときに、他に宇宙基地になるような場所を探していました。いま弊社が拠点としている大樹町は「うちに来ませんか?」と手を挙げていたのですが選定からもれてしまったのです。場所もあるし気運も高まっている地域なんだけれども、実際には物が作られなかったという経緯があって、30年程たってから、こんなにいい場所があって地元の理解もあるんだ、ということで、大樹町に本社を置いたという経緯があります。
ELS 小林様
日本の製造業という観点は強くあるなと思っています。そこに加えてという観点ですと、宇宙産業はアメリカやロシアも主導してきましたが、日本でもアメリカやロシアと比べたら規模は小さいものの、主体的に取り組んでおり、実績のある国だといえます。技術にしても再突入の経験もあるしロケットを打ち上げた経験があります。技術の素養があり、製造の側面でもしっかり整っている日本の立ち位置としては宇宙産業においてとても強い。さらに宇宙は、軍事や安全保障と近い立場にあり、中立的な立場である日本は、グローバルにサービスを展開していきやすいのではないでしょうか?
今後の構想などありましたらお聞かせください
IST 稲川様
有人ロケットの技術を使った、P2Pという構想があります。地球の裏側に最速でいこうとすると、宇宙空間を通って、第一宇宙速度に近い速度を得て降りてくるのが最速です。軌道の最適化をするとそうなるのですが、ここにロケットを使うと90分切るくらいでいけるようになるのです。これが一番最終的なP2Pの移動手段になります。技術の延長線上として参入していき、宇宙空間を定期的に人が移動するというのを実現したいです。宇宙技術を持っている企業として、そこの中核を担えるようになりたいです。
ELS 小林様
2023年末打上げに向けて200キロ程度の技術実証機を開発しています。その次にサービス提供する本格的な機体は1トン級の衛星を想定しており、2026年ころからのサービス化を目指しています。年に6回程度の打上げ、2か月に1回程度の頻度でユーザーが気軽に実験できる、宇宙を使えるという世界を着実に作りたいと思っています。その先としては再突入技術を活用して事業展開していきたいです。まずは、宇宙ステーションなどに無人宇宙船で物資をもっていき、持ち帰ってくるというところに参入し、それを有人化し、有人宇宙船で人を輸送できるようにしていきたいです。そのあとは有人宇宙技術を使って、宇宙ホテルや宇宙ステーションを事業として展開していきたいと思います。
今の法曹界にご意見をお願いいたします
ELS 小林様
GVAさんには日々お世話になっています。日々の契約書まわりもそうですし、資金調達がスタートアップにとっては大きなイベントですが、その対応もスピーディーにかつ会社の観点からこういうところが必要なんじゃないか、こういうところは交渉できるんじゃないかというアドバイスをいただいています。大変ありがたいですし、ぜひ長くご一緒できればと思っています。
現時点でクリティカルなものがあるわけではありませんが、再突入というところでも法律的なルールは変えていかなくてはいけないところがあると思っています。そもそも宇宙から衛星が戻ってくるということは国がやっていたところしかないので、使いづらいルールになっています。どこに衛星を落とすかという観点を緩和していかない限りはユーザーの手元に届くまでに非常に時間がかかってしまう。使いやすいサービスにしていくためには、法律面を民間として使いやすいようにクリアしていかなくてはならないと思います。民間としても働きかけていきたいと思っておりますので、そのあたりも含め是非サポートいただきたいです。
IST 稲川様
ロケット・宇宙の使い方がこれからいろいろ増えます。というときに、気になることが一つあって有人宇宙飛行は、アメリカではすでに民間の人が宇宙にいく建て付けが国内で法整備されていますが、日本はまだなんです。お客さんを乗せて宇宙に運ぶサービスができたとして、法的にどうしたらいいのかという課題が残ります。航空局は審査できないと思うので、航空機と同様には考えられないのです。
宇宙空間を活用していくなかで、例えば軌道上サービスとして宇宙のゴミ掃除、燃料補給をします、ものづくりをしますというサービスが出てくると、色々ぶつかる壁が出てくると思うのです。宇宙空間って、公海上と同じように、どこの国のものでもないなかで、なんらかの活動をしますというときに、法律はどうなるんだっけという話によくなります。国際的な法律のほかに個別の契約というところで結構複雑なことになると思います。今そういうもので具体的なものはないし、先行例もほとんどないです。こういうやりとりから宇宙産業自体が作られると思っていて、ここをどう契約にして整理していくか、というところが面白いですし、難しくて悩ましいです。ここについて専門家の方々の意見をいただきたいな、ととても期待しています。
【インターステラテクノロジズ株式会社】

インターステラテクノロジズは、圧倒的に低価格で便利な宇宙輸送サービスにより宇宙へのインフラを構築し、誰もが宇宙に手が届く未来の実現を目指すスタートアップ企業です。北海道大樹町に本社を置き、東京支社と福島支社、室蘭技術研究所(室蘭工業大学内)の4拠点で開発を進めています。観測ロケット「MOMO」は2019年5月に国内民間企業で初めて宇宙空間に到達、2021年7月には2機連続での宇宙到達に成功しました。次世代機となる超小型人工衛星用ロケット「ZERO」も開発を本格化させています。

【株式会社ElevationSpace】

ElevationSpaceは、東北大学吉田・桒原研究室でこれまで開発してきた10機以上の小型人工衛星の技術を基に、2021年2月に設立された東北大学発宇宙スタートアップです。
国際宇宙ステーション(ISS)は、2000年の本格利用開始からこれまで、基礎科学的な実験から創薬などの産業利用まで幅広く利用されてきました。しかし、構造寿命などの関係から2030年末に運用が終了する可能性が高く、宇宙利用を行う場所が無くなると考えられています。
そこで、ElevationSpaceは小型人工衛星内での宇宙実験や製造を可能とする小型宇宙利用・回収プラットフォーム「ELS-R」の提供を目指し、現在は2023年後半打上予定の技術実証機を開発しています。

弁護士法人GVA法律事務所 宇宙・航空チーム
弁護士法人GVA法律事務所では、ロケット・人工衛星・ドローンの製造・運用やデータ利活用事業等を行っておられる宇宙・航空関連企業の皆様に、国内外の契約交渉や資金調達を含む幅広い法務サポートを提供しております。
今回お二人からお伺いしたとおり、宇宙ビジネス分野においては遵守すべきルールが整備されていない点が多く、日々進歩する情報のキャッチアップも非常に重要です。弁護士法人GVA法律事務所では、宇宙法や宇宙ビジネスに関する豊富な知見と経験を基に最新の情報をご提供し、お客様のサポート、そして業界の発展に今後も尽力してまいります。
担当チーム:宇宙・航空チーム