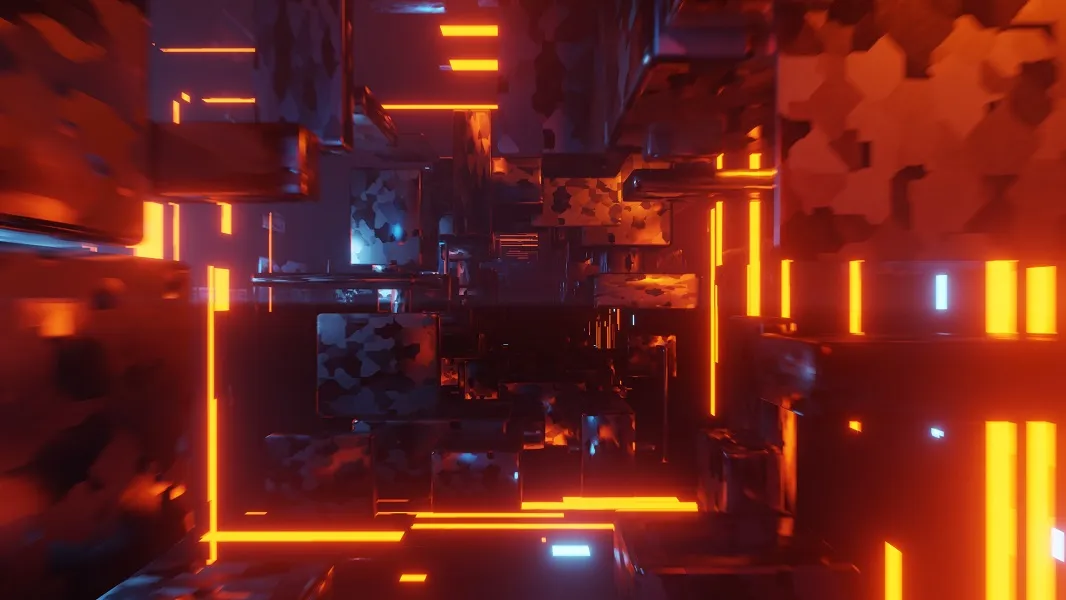第2回 法的課題の検討(前編)
第1回では、「メタバース」の意味を検討しました。
前回ご紹介したとおり、メタバースは極めて自由であるため、その反面として、乗り越えなければならない法的課題が山積みである、というのが現状です。
そこで、今回は、メタバースに関する法的課題を縦覧的に取り上げて、事業者が取り組むべき課題について、若干の検討を加えていこうと思います(第1回をお読みでない方はぜひ第1回からご覧ください。)。
目次
第1回 メタバースとは
⑴ 定義
⑵ MMORPGやデジタルツインとの違い
⑶ 従来のメタバースとの違い
第2回 法的課題の検討(前編)
⑴ 著作権法などの知的財産権の観点
ア アニメのキャラクターアバターやゲームのステージの再現
イ 現実世界の再現
ウ 現実のモノの再現
エ 絵を描く、歌をうたう、楽器を演奏するなど、メタバース上の芸術的行為
オ ユーザーによる配信
第3回 法的課題の検討(後編)
⑴ 肖像権やプライバシー権の検討
ア 現実の人を再現したアバター
イ 現実の第三者になりすますアバター
ウ 第三者のアバターを再現したアバター
⑵ その他のリスク
第4回 メタバースに参入する事業者が採るべき対策
⑴ 事業者自身がメタバースを提供する場合(メタバースを運営する場合)
⑵ 他社が提供するメタバースプラットフォームを利用する場合
⑶ おわりに
⑴ 著作権法などの知的財産権の観点
ア アニメのキャラクターアバターやゲームのステージの再現
筆者が実際にメタバースの世界に飛び込んでみて、最も目にしたものが著作権などの知的財産権の侵害となる可能性の高い世界やアバターでした。
具体的には、有名なアニメのキャラクターのアバターが自由に配布されていたり、ゲームのステージを再現した世界が存在していたというものです。こういった第三者の作品をもとにつくられたアバターや世界の提供を適法に行うためには著作権者の許諾が必要となります。
事業者が進んで著作権侵害を行うことは考えにくいものの、例えばアバターの制作をクリエイターに委託する場合には、そのアバターが著作権などの知的財産権を侵害していないかどうかをきちんと確認する必要があります(度々世間を騒がせる「トレースパクリ(トレパク)」も、多くの場合著作権侵害となります。)。ただ、全てを逐一確認することは現実的には不可能ですから、クリエイターとの業務委託契約書に知的財産権を侵害していないことを表明し保証させる条項を組み込むことが有効です。
イ 現実世界の再現
一方、現実社会に存在する建物や、公園などの屋外に設置されたベンチなどを再現してメタバース上に設置することは、著作権法第46条に基づいて適法に行う余地があります(メタバース上の設置は、建築以外の方法による複製にあたり、同条第2号には該当しないという説明が可能であるためです。)。
著作権法第46条(公開の美術の著作物等の利用)
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
ただし、建物や設置物自体が美術的な要素を含む場合(例えば、東京タワーや東京スカイツリーなど)には、本条の4号に該当する可能性があります。つまり、その美術的な建物が設置されている世界に参加するために入場料を徴収するという場合には、販売目的であると判断されるおそれがあり、そういった場合には、著作権法の原則どおり、著作権者の許諾が必要となるということになります。
また、販売目的なく建物の再現を行ったときであっても、アレンジが加えられている場合(例えば、幹の形状が東京スカイツリーになっている樹木を設置するなど)を行った場合には、著作者が有する同一性保持権(著作者の意に反して、著作物やその名前等を変更されない権利。著作権法第20条第1項前段。)を侵害するリスクがあるので注意が必要です。
他方、美術的な要素を含まない建物であっても、その建物に看板や企業ロゴがついている場合には、建物の再現は一概には適法とはいえません。その看板に描かれたものや企業ロゴは建物とは別の著作物ですから、コピーにより著作権を侵害してしまいますし、企業ロゴが商標登録されている場合、その表示態様によっては商標権侵害となるおそれもないとはいえません。
ウ 現実のモノの再現
メタバース内で、現実に存在する商品等を再現したアイテムやオブジェクト(衣服や自動車など様々なものがあり得ます。)を利用する場合にも注意が必要です。
まず、絵画や写真、彫刻、モニュメントなどの創作作品については、原則として著作権者による許諾が必要です。
また、創作作品以外のオブジェクトであっても、前述した建物のように、それ自体が美術的な要素を含む場合には、建物の再現と同様に著作権侵害のリスクがあります。
さらに、著作権以外の知的財産権の侵害も考えられます。例えば、バッグのアイテムに対して商標登録された有名ブランドバッグのロゴを勝手につけることは商標権侵害や不正競争防止法違反になり得ます。
ただし、商標権はあくまで、登録された指定商品・指定役務の範囲で認められますから、メタバース上での利用は登録商標の指定商品・指定役務の範囲外となる可能性があります。そのため、物理的な商品を販売しているにとどまる企業であって、「第9類」や「第42類」等、ソフトウェア・プログラムに関する区分についての登録を欠いている場合には、商標権者からの主張を退けられる可能性も否定できません。もっとも、権利者の許諾なく登録された商標を含むアイテムを登場させることは、事業者として適切ではないと言わざるを得ないでしょう。
エ 絵を描く、歌をうたう、楽器を演奏するなど、メタバース上の芸術的行為
メタバース上であっても現実と同様に様々な芸術的行為が可能です。この場合、オリジナル作品であれば、著作権は原則としてその作品の作成者に帰属します。ただし、メタバースの提供者がその規約において、メタバースの提供者に帰属すると定めた場合には、メタバースの提供者に著作権を譲渡するものとすることができます(譲渡することができない著作者人格権について、著作者は提供者に対して行使するできない旨の規定を併せて設けることが一般的です。)。
他方で、既存の作品の演奏や、いわゆる「歌ってみた」などについては、既存の作品の著作権者の許諾が必要です。日本における音楽著作権は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)などの管理団体が集中管理を行っているため、こういった団体から個別に許諾を得る方法が基本となります。
なお、メタバース提供者が、管理団体と包括利用許諾を締結した場合には、個別の許諾を省略することも可能となります。
(※JASRACは、利用許諾を締結したサービスを公開しています。https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html )
ただし、包括利用許諾がある場合であってもCD音源をそのまま流す場合(オフボーカルも含みます。)には、当該CD音源を創作した者の権利(著作隣接権)を侵害してしまいますから、同権利者による許諾が必要となります。
また、編曲や替え歌を行う場合には、建物アレンジの箇所でも述べたように、同一性保持権を侵害してしまいますから、著作権者から、更に編曲や替え歌についても個別の許諾を得る必要があります。
オ ユーザーによる配信
近時、ゲームの配信動画が大変な人気を博しており、配信者も動画配信プラットフォームや視聴者からの投げ銭によって収益化を行うケースも少なくないことは皆さん既にご存知のところかと思います。こういったゲーム配信は、ゲーム画面という著作物を利用しますから、配信者はゲームメーカーなどの著作権者から許諾を得る必要があるのが原則です。
もっとも、ゲーム配信は、ゲームやメーカーの広告にもつながる点で事業者にとっても有益な場合もありますから、ゲーム事業者がゲーム配信に関するガイドラインをあらかじめ公表して、包括的に許諾するケースも増えています。
では、メタバース内における行動の配信でも同じことがいえるでしょうか。実は必ずしも一筋縄ではいきません。後述の「3メタバースに参入する事業者が採るべき対策」の(1)でも述べますが、メタバース上には、ユーザー作成のアバターやアイテム、提携事業者の看板など、メタバース事業者以外の著作物であふれていることが想定されます。そのため、メタバース事業者が自らの著作権の範囲で配信を許諾したとしてもそれだけでは足りず、他のすべての著作権者からも配信の許諾を得なくてはならない、ということになります。確かに、「写り込み」のレベルであれば許諾が不要となる場合も考えられますが(著作権法第30条の2)、配信者の立ち位置によっては全画面に投影されることも当然に想定されますから、すべてを「写り込み」と処理するのは困難でしょう。そうすると、やはり他のユーザーを含めてすべての著作権者から許諾を得なくては配信ができないということになってしまい、とても現実的とはいえません。
そのため、このような不都合を避けるために、ユーザー作成のコンテンツの著作権それ自体はユーザー自身に帰属するとしても、ゲーム配信やスクリーンショットの公開などの用途については、第三者による著作物の利用をあらかじめ許諾するものとする旨をメタバース事業者の利用規約に定める必要があります。
また、メタバース空間を自社では準備せず、メタバース空間を運営する事業者(本稿では、メタバース事業者の中でも特に「メタバース運営者」といいます。)と提携してメタバース事業を展開することも大いに考えられます。この場合、メタバース運営者との契約書において、上記の問題を回避できるようにできるように条項を整備する必要があるでしょう。ただし、メタバース運営者自身が不十分な利用規約を定めている場合も考えられますから、準備をある程度進めていたのに、意図していた事業が適法に実施できないことが判明してしまうという事態を避けるために、提携するメタバース運営者の選択の際には、十分な吟味を行うようにしましょう。
次回(第3回)に続きます。
監修
弁護士 箕輪 洵
(スタートアップ企業を中心に、上場企業から中小企業まで企業法務を幅広く対応。知的財産法を得意とし、特にメタバース法務、エンターテインメント法務に注力。)