はじめに:進出パターンと本稿の目的
東南アジアでビジネスを始める場合には、いくつかの進出パターンがありますが、現地でのビジネス規模が拡張していけば、いずれ現地子会社(現地法人)を設立する流れになることが多いかと思われます。本稿では、その現地法人設立について具体的なイメージを持っていただけるように現地進出の実例を解説します。ただし、設立の手順や運営コストには各国毎に独特の違いがあります。本稿内で全ての国について詳しく紹介するのは難しいため、ここでは筆者が最も経験しているタイを例として取り上げつつ、主な実務ポイントをまとめます。
東南アジア進出の具体像(タイ進出を事例として)
1. 現地法人設立の基本ステップ
タイで会社をつくるには、ざっくり次のような手順が必要です。書類がそろっていれば形式上は数週間で完了しますが、実際には書類準備や役所対応にそれなりの時間と労力がかかるので、最低でも1か月半程度の時間は必要でしょう。なお、タイの投資奨励制度(BOI)を利用して恩典を受けつつ法人設立をする場合は、その審査に半年ほどかかる点にも注意してください。
- 会社名や住所、株主・取締役など基本情報を決定
- 商号(会社名)の事前予約
- 商業登記申請(DBD:Department of Business Development)
- 銀行口座の開設
- 資本金の払込み
- VAT(付加価値税)の登録
- 社会保険の登録(従業員を雇う場合)
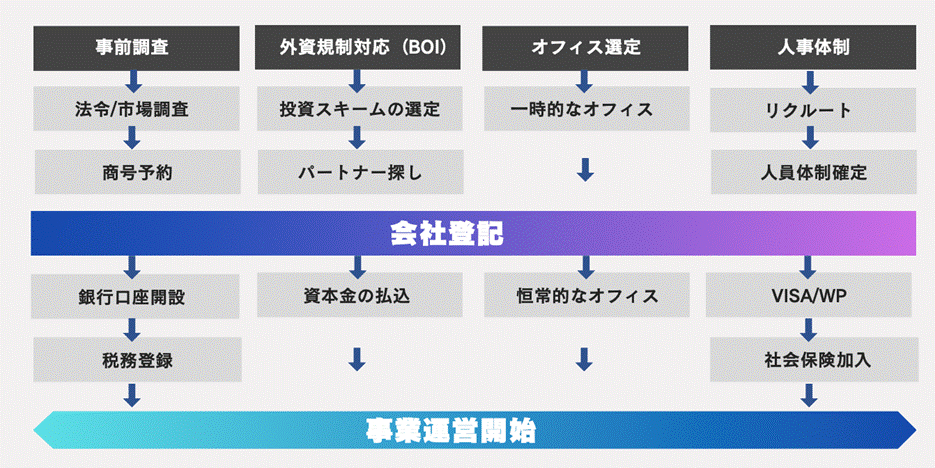
2.ビザ・就労許可(就労ビザ・ワークパーミット)
タイの場合、日本人スタッフを駐在させる場合、就労ビザ*とワークパーミット**の取得が必須になります。タイで就労ビザを維持するためには、外国人1人に対してタイ人4人を雇用する必要があり、日本人駐在員の給与も月額5万バーツ(約22万円)以上が条件です。この数字はランニングコストに大きく影響しますので、人員計画や資本計画は、初期段階からビザ取得要件を見据えて立てておくことをおすすめします。なお、タイを含む一部の国ではビザ申請・更新過程において不透明な金銭要求が報告されています。現地の協力事業者に手続を委託する場合であっても、常に法令に基づいた運用を行うことが求められることを留意しましょう。
*就労ビザ(Non-Immigrant B Visa)
タイで就労する外国人が入国・滞在するためのビザで、就労前に本国のタイ大使館や領事館で申請します。最初の有効期間は90日とされているケースが多いので、入国後90日以内にワークパーミットを取得した上で年次更新が必要です。
**ワークパーミット(Work Permit)
就労ビザ取得後、タイ国内で実際に働くために必要な就労許可証です。許可された職務以外の業務は原則禁止で、転職時などには再申請が求められます。
3.専門家費用と会計・税務対応
現地法人を維持するには、会計や税務、社会保険などの手続きに関するコストも無視できません。毎月のVAT申告、社会保険料の納付、年次決算書の作成・監査、人事労務の手続きなど、基本的には現地語対応が前提です。そのため多くの日系企業は会計事務所やコンサル会社にアウトソーシングしており、費用は月額数万円から十数万円が目安となります。このようなコスト及び資金繰り全体を総合的にシミュレーションし、想定する規模及び期間に応じた運営計画を立てておくと安心です。
4.ランニングコストの試算
東南アジア展開において、「思ったより固定費がかかる」という声は少なくありません。たとえばバンコクで小規模オフィスと数名のスタッフで現地法人を運営する場合、月々おおよそ以下のコストを見込む必要があります。
オフィス賃料:約50,000バーツ(約22万円)
… 20〜25㎡の小規模サービスオフィス相当
タイ人スタッフ給与:計100,000バーツ(約44万円)
… 1人あたり約25,000バーツ(約11万円)×4名
日本人駐在社長給与:約100,000バーツ(約44万円)
… 就労ビザ・ワークパーミット維持のための最低基準に準拠した水準
会計・税務アウトソーシング費:約30,000バーツ(約13万円)
… 記帳、VAT申告、決算対応、労務管理等を含む外部委託費用
その他雑費:約30,000バーツ(約13万円)
… 光熱費、通信費、SaaS利用料、雑費等
合計:約310,000バーツ/月(約136万円) → 年間:約3,720,000バーツ(約1,630万円)
タイでの法人維持費は年間1,600万円前後。日本よりは割安に感じるかもしれませんが、スタートアップには決して小さくない負担です。参考までに、ベトナムで同様の体制をとった場合のコスト例も挙げておきます。ベトナムは現地スタッフ雇用の義務が比較的軽く、より少人数で事業を始めやすい点がメリットです。
オフィス賃料:約21,600,000 VND(約13万円)
… Grade B〜C相当のサービスオフィス(25㎡)を想定
ベトナム人スタッフ給与:計30,000,000 VND(約18万円)
… 中堅事務職×2名(1人あたり約15,000,000 VND=約9万円)
日本人社長給与:約78,000,000 VND(約45万円)
… 月額約3,000米ドルを想定(2025年レート)
会計・税務ファーム費:約7,000,000 VND(約4万円)
… 記帳、VAT申告、決算対応、PIT申告含む
その他雑費:約15,000,000 VND(約9万円)
… 光熱費、通信費、SaaS利用料などを想定
合計:約151,600,000 VND/月(約89万円) → 年間:約1,819,200,000 VND(約1,070万円)
上記はあくまで一例ですが、現地で実務を担っている筆者としては、現実的な水準だと感じています。進出計画の検討にあたり、参考にしていただければ幸いです。
展開戦略の見極め
1.多国展開を前提とした視点
東南アジアにおける事業展開は、多くの場合、一国にとどまらない多国展開を前提とします。
ASEAN諸国の個別市場規模は、米国や中国のように単独で圧倒的なボリュームを持つわけではなく、東南アジア全体をひとつのエコシステムとして捉えて初めて、スケーラブルな事業展開が成立するケースが多いためです。そのため、インドネシア・ベトナム・フィリピン・タイ・マレーシアといった複数国への同時あるいは段階的な展開を視野に入れることになります。
ここで問題となるのが、「各国すべてに現地法人を設立すべきか」という点です。現地法人の設立と維持には相応のコストと手間が伴います。設立時の法的・会計的ハードルだけでなく、法人を維持するためのランニングコスト(具体的なコストは上を参照してください)も積み重なります。そのため、多国展開に際して安易に複数法人を同時に立ち上げることは、資金制約のあるスタートアップにとって大きなリスクになります。
したがって、展開対象国ごとに「現地法人を設けて自ら展開する国」と「現地パートナー(販売代理店・業務提携先など)を通じて間接展開する国」とを峻別し、コスト効率の良い進出モデルを構築する必要があります。この選別にあたっては、以下のような複数の観点を総合的に勘案することが求められます。
- 地理的な利便性(物流や営業拠点としての優位性)
- 社会インフラ及びデジタルインフラの整備状況
- 現地人材のスキル水準・英語対応能力・採用容易性
- 物価や人件費などの運営コスト
- 許認可制度・外資規制の柔軟性
- 外国企業に対する制度的優遇の有無(例:BOI、PEZAなど)
2.シンガポールHQ設立の是非
この文脈でよく登場するのが「シンガポールにリージョナルHQ(地域統括会社)を置くべきか否か」という問いです。シンガポールは高度に整備された物理インフラ・法制度・金融制度を有しており、アジアにおけるビジネスのハブとして世界的に評価が高い国です。また、法人税率が低く、キャピタルゲイン課税がない点など、節税メリットを重視する大企業グループには大きな魅力となっています。しかしながら、スタートアップが「とりあえずシンガポールに拠点を置いておく」ことには慎重であるべきです。第一に、現実として多くの日本のスタートアップは日本法人をExitの母体としており、資金調達やIPOを日本国内で行う予定がある場合、シンガポール法人の存在は必ずしもExitにおける直接的な優位性をもたらしません。第二に、スタートアップの多くは収益モデルや利益体質が確立していない段階にあるため、そもそもシンガポールの節税メリットを享受できるほどの課税所得を有していないことが多いように思われます。
加えて、シンガポール法人を設立・維持するにも一定の固定コストが発生します。取締役の現地居住要件、会計・監査・年次報告義務、ライセンスの取得・更新手続きなどを考慮すると、シンガポール拠点を設置することは非合理となる場合も十分有りえます。むしろ、物価・人件費が低く、実際のオペレーションが行いやすい国(例:ベトナム・フィリピン・マレーシアなど)に本社機能の一部を集約させる選択肢や、まずはタイやベトナムに法人を構え、他国には販売提携で展開し、将来的に市場規模や顧客数に応じて法人設立を検討する段階的モデルの方が現実的な選択肢になる場合も多いかと思われます。
まとめ:成長段階とExit戦略を見据えた柔軟な進出計画
東南アジア進出は、単なる会社設立やコスト試算にとどまらず、自社の成長段階・資金計画・将来のExit戦略までを見据えた経営判断が重要です。どの国に法人を置き、どこを提携による展開にとどめるかは、短期的なコストだけでなく中長期の市場成長性や人材戦略とも深く結び付きます。各国の規制や経済環境は変化し続けるため、初期は小規模かつ柔軟に着手し、事業の伸びに合わせて拠点を拡張する段階的アプローチこそ、リスクを抑えながら持続的な成長を実現する最も現実的な道筋といえるでしょう。
以上











