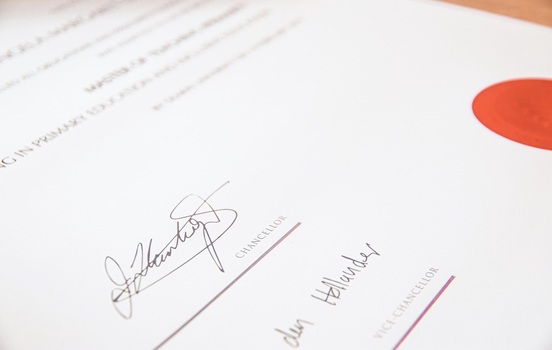執筆:弁護士 靏 拓剛(国際チーム)、弁護士 公文 大(国際チーム)
タイにおける株式管理の重要性
タイでも、日本と同様、株主は会社の所有者と位置づけられています。そして、会社の重要な事項、例えば、取締役の選解任、取締役の報酬、配当、定款変更、増資・減資などは、株主総会の決議によって決定しなければなりません。そのため、タイの非公開会社においても、「誰が株主か」は会社の経営に重大な影響を及ぼす要素の一つです。
ところが、タイでは、株式が十分に管理されていない会社が散見され、管理が不十分なまま放置していると、最悪の場合、例えば次のような事態に陥るリスクがあります。
いつの間にか真の株主が誰か分からなくなっていた。そのため、株主総会で何かを決議しても、その決議の正当性に疑義が残ってしまう。
このような事態は、会社の事業運営においても支障が出るだけでなく、M&Aにおけるデュー・デリジェンスにおいても主要なリスクとして指摘される事項です。この株式管理が不十分であったために、事後的に大きな問題に繋がったという事例は、意外にも少なくありません。つまり、会社を円滑に維持・運営していくうえで、株式を適切に管理することは極めて重要な業務のひとつだと言ってよいでしょう。そこで、本稿では、タイの非公開会社における株式の基本的ルールやその管理方法について整理します。
なお、タイでは無記名株券(株券に株主名が記載されていない株券)の発行も可能であるとされています。しかしながら、無記名株券が発行されているケースは稀であり、一般的に記名株券(株券に株主名が記載されており、その株式の株主が特定されている株券)が発行されています。そこで、本稿は、株券が記名株券であることを前提としています。
株券発行の必要性
株券について若干言及したので、まず株券について整理しておきましょう。まず、タイと日本で大きく異なる点の一つが、タイでは、株主に対して必ず株券を発行しなければならないという点です。日本では株券を発行しない(株券不発行会社)ことがむしろ通常であるため、タイにおいては、そもそも株券を発行していなかったという事例が少なくありません。しかし、タイにおいて株券発行は会社の義務とされています。したがって、タイではこの選択できないのだという点を押さえておきましょう。
株券の発行が必要だとして、株券保有者はどのような立場に置かれるかについても説明しておきます。まず、タイの株券は、あくまでも「証拠証券」としての性質しか持っていません。つまり、株券は「株券の所持者=株主である可能性が高い」ということを示す証拠の一つとして位置づけられています。必ずしも「株券保有者=株主」ではないということです。
「株券保有者=株主」ではないのであれば、株券は重要ではないのでは?という疑問も出るところでしょうが、真実の株主と株券の所持人がずれてしまっていると、本当は誰が真実の株主かについて混乱が生じることは間違いありません。そのため、会社としては、例えば株式が譲渡されて株主に変動が生じる場合には、譲受人に株券が交付されたことを確認し、誰が株券を保持しているかを正確に把握しておくことは、必須と言ってよいでしょう。
株主名簿とBOJ5
■株主名簿
次に、会社が必ず作成し、管理しておかねばならない株主名簿について整理します。
1.株主名簿の意義
株主名簿は、会社の株主、各株主の株式の保有状況、株式の譲渡歴などが記載される会社の内部記録です。会社は、株主名簿を作成・保管すべき義務を負っています(CCC1138条)。そして、会社は、この株主名簿に基づき、誰が株主として権利行使(株主総会での議決権行使、配当金の受領など)できるかを判断していくことになります。したがって、その内容は正確でなければなりません。なお、株主名簿は、株主であれば誰でも閲覧・謄写が可能です(CCC1139条1項、CCC1140条)。
2. 株主名簿の記載事項
株主名簿に、記載すべき事項は、次のとおりです(CCC1138条)。
- 株主の氏名、住所
- 各株主が保有する株式の種類、払込済の額、株式番号、株券番号
- 各株主が株主となった日
- (株式譲渡等により株主でなくなった場合)各株主が株主でなくなった日
ここで、「株式番号」という馴染みのない用語が出てきました。実は、日本と異なり、タイの株式には、全て株式番号が付されており、特定の番号を付された株式は、それ以外の番号を付された株式とは区別されています。つまり、例えば株式を100株譲渡する場面でも、その譲渡株式が、1〜100番の株式なのか、1001番から1100番の株式なのかは異なると考えるのがタイの実務です。
ただし、これらの株式番号は、一度付与されたら変更できない性質のものではありません。実はこの仕組みがタイの株式帰属の確認を難しくしている理由の一つでもあるのですが、株式番号は、会社の裁量で再編できるとされており、それまでの株式番号を廃し、随時新たに番号を指定することが可能です。この場合には、株券の再発行及び株主名簿においてその旨が記録されることが必要になります。
3. BOJ5
取締役は、少なくとも毎年1回、定時株主総会の後14日以内に、定時株主総会開催時の全ての株主、及び、前回の定時株主総会後に株主でなくなった者が記載された株主リストをタイ商務省事業開発局(Department of Business Development。以下、「DBD」といいます。)に提出しなければなりません(CCC1139条3項)。この際にDBDに提出する株主リストが、「BOJ5」と呼ばれる書類です。
このBOJ5は、上述した株主名簿と非常によく混同される書類です。このBOJ5は、DBDに対して提出されるものなので、日系企業の間では、このBOJ5があたかも「正式な株主名簿である」と扱われている場合もあります。また、このBOJ5は、誰もがDBDで閲覧できる書類なので、「タイでは株主が登記される」という誤解もしばしば生じています。
しかしながら、BOJ5は、あくまでも、株主名簿に基づいて作成され、DBDに提出される報告書類に過ぎず、株主名簿そのものではありません。また、事実上の問題として、BOJ5は年に1回提出すればよいので、株主の変動があっても「まだBOJ5の提出時期じゃないから」とアップデートをしないまま放置することも可能です。つまり、BOJ5は必ずしも株主の所在を正確に記録する文章ではないことには、十分な注意が必要です。実際、タイの会社の中には、株主名簿を作っておらず、このBOJ5の写しをもって株主名簿だと扱っている会社もあります。しかしながら、このような運用は避けるべきであり、BOJ5とは別個に必ず株主名簿を作成し管理すべきです。
4. 小括
株主名簿は、「誰を株主として扱うべきか」を判断する際の基礎となる重要な書類です。
そのため、株式譲渡など、株主やその保有株式数に変動が生じた場合には、その変動を確実かつ速やかに反映する必要があります。
また、BOJ5は年に1回の提出しか要求されていませんが、DBDに提出され登録されている株主構成と株主名簿上の株主構成に差異がある場合、「どちらの記載が真実なのか?」などという無用の混乱を招くことにもなりかねません。そのため、何か変動があった場合には、株主名簿を書き換えるだけでなく、速やかにBOJ5をDBDに提出して登録を変更し、両者の内容を一致させておくことが望まれます。
実務上の留意点とまとめ
ここまで述べて来たとおり、タイでは、日本との制度差を理解した上で、株券と株主名簿を作成・管理し、「誰が株主で、それぞれが何株を持っているか」を記録とともにしっかりと把握しておくことが大切です。この点、「誰が株主か」などは日常的な業務の中では滅多に問題にならないため、株式管理はどうしても後回しにされがちです。しかし、これを疎かにしておくと、会社の重大な意思決定が満足にできないという事態にも繋がりかねません。
なお、本稿の冒頭に述べた「いつの間にか真の株主が誰か分からなくなっていた。そのため、株主総会で何かを決議しても、その決議の正当性に疑義が残ってしまう。」という話は、過去に実際にあった事例であることも、念の為申し添えておきます。
なお、タイの株式管理において、これについてはもう稿を改めて説明しますので、次回についても是非ご一読下さい。
補論:タイ法人と外国法人
株式管理に関係して、タイでは、「法人の国籍」が問題となることがあるため、この点を補足しておきます。
まず、タイの会社は、タイ法人と外国法人に区別されます。これは、「その会社の株式の過半数をタイ人(又は他のタイ法人)が保有しているかどうか」による区別であり、タイ人(他のタイ法人)が過半数を保有していればタイ法人、外国人が過半数を保有していれば外国法人と整理されます。
この区別が重要なのは、その会社が行うことのできる事業の範囲や条件に直結するからです。タイでは「外国人事業法」という外資規制法制により、外国法人が営むことができない事業分野(小売、サービス、建設、不動産関連など)が定められており、その対象範囲は非常に広範です。外国法人としてこれらの事業を行うためには、外国人事業許可の取得、あるいは投資委員会(BOI)の投資奨励措置の認可などの例外的な手段が必要となります。しかし、これらの許可・認可を得ることは容易ではなく、また追加の条件や制約(タイ人従業員の雇用義務、最低資本金の要件等)が課されることも少なくありません。
したがって、タイ法人として存続している会社においては、株式譲渡によって持株比率が変動する場合に、タイ人(又はタイ法人)による持株割合が過半数を割り込まないよう、常に慎重に管理する必要があります。特に、
- 小規模な株式移動や相続によって、意図せず外国法人に転換してしまうケース
- グループ再編等によってタイ側出資比率が薄まり、外資規制の網にかかるケース
は実務でしばしば問題となります。
また、一度外国法人とみなされてしまうと、後から株主構成を修正しても、当局がそれを「遡及的に」認めるとは限りません。そのため、株式管理においては「単に誰が株主か」を確認するだけでなく、「外国法人かタイ法人か」という法人ステータスの維持・監視を含めたチェック体制を整備しておくことが極めて重要です。